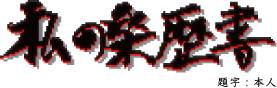2011/11/01
20(第二部)
日本経済の低迷=デフレの状況は未だに出口の見えない厳しい見通しの中にあります。御承知のように新聞やテレビで連日報道されている経済に関する様々な論評や分析を見聞きしても、一体この先どのようになってゆくのか? 社会全体が暗中模索の状態であるように思います。11/24の朝日新聞は、今後の景気についての記事に多くの紙面を割いていましたが、5面に連載中の「経済漂流」では、1998年当時のITバブルに関する記述がありました。私はその記事の中で触れられていたIT系企業やその経営者の方々と面識がありその当時にも色々な場面でお会いしたり、具体的なビジネス上のおつき合いもありました。渋谷区を中心とした「ビットバレー」と呼ばれる地域に本拠を置いている新興ベンチャー企業のいくつかとも仕事上の直接の関係があったり、情報交換などもしていました。この朝日新聞の記事の通り、1998年頃のIT系業界は全体的に「浮かれた」ムードが漂い、世間の不景気感とはかけ離れた「異常」な雰囲気がありました。団塊の世代以後の30代や40代前半のビジネスマンが主役となって、新しい事業や新しい市場を生み出そうとする気運が高まっていました。旧世代や旧秩序に対する強い不満を背景に、日本の長期不況と対照的なアメリカの好況との矛盾を目の当たりにしながら、IT産業における日本の「遅れ」に着目して新しいビジネス・モデルやテクノロジーを導入する新規事業が数多く立ち上がったのです。
こうした一種異常な「ムード」の中で、私自身もデジタル革命とインターネット時代の真只中で仕事を続けてきたことと、アメリカの凄まじい変化を実感していたことによって、日本の新しいマーケットの誕生を確信していました。基本的にその「確信」は現在でも変わっていないのですが、その新しいマーケットの誕生には様々な条件があること、とりわけ産業構造の転換に繋がる巨大な社会システムの変化については、私の想像を遥かに越えるエネルギーが必要なことについては、その「ムード」の中では正直なところ気がついていませんでした。ソニーの一員であった頃にはデジタル産業への転換は日常的なことであり、プレイステーションとバイオの成功やソネットの立ち上げも順調に進んでいて、私の関わった新しい事業はいずれも順風満帆に推移していると見えていたからです。携帯電話は急成長し、i-modeの登場でインターネットも一気に普及していました。スターバックスやユニクロは急速に店鋪を増やして増収増益、UFJやディズニー・シーも大盛況、ホンダやトヨタも業績を伸ばしていて、日本は本当に不景気なのだろうか? と思う程に、IT関連企業に限らず新しいビジネス・モデルやテクノロジーをグローバルな視点で展開する企業はしっかりとした業績を上げていました。それは2002年の現在でも言えることなのですが、例えばここで例に挙げたスターバックスやユニクロ、UFJの場合は今年に入って少し様子が変わってきた様です。携帯電話ビジネスも急成長期から安定期に入ったと言われますし、自動車も2001/9/11のテロ事件後のアメリカ経済の減速によって先行きが不透明になってきました。
改めて1998年頃の私は、ネットワーク・ゲームの開発と市場性に傾注していて、インターネットの新しいエンタテインメント・コンテンツとしての将来性を探っていました。ソネットにおけるポストペットの成功に気を良くして、次はネットワーク・ゲームだ! とばかりに気負い込んでいたとも言えます。1997年のアメリカでのビジネス・ショー「E3」で発見したコロラド州デンバーのベンチャー企業VR-1社との出合いや日本のITバブルを演出したいくつかの企業との関係によって、ゲーム・ビジネスの新しい展開や制作業務の変化について、とくに新しいテクノロジーの必要性を強く感じていたことも背景にありながら、目の前で演じられているいくつかのバブル劇の有り様に気を取られていたことも否めません。VR-1社との関係は1998年初頭頃から急速に密接なものになりました。まずはソネットで取り組みを始めたネットワーク・ゲーム・サイトのメニューとして、VR-1の深海シミュレーション・ゲーム「SARAC」のライセンス契約交渉が始まりました。(このゲームは現在でもソネットの「Party Crew」でサービス中の本格的なリアルタイム・マルチ・プレイヤー型のネットワーク・ゲームの一つですが、このゲームのオペレーションにVR-1社の基幹サーバー技術である「コンダクター・ソリューション」が使われています。これはMicrosoft Gaming Zoneが提供している戦闘機バトル・エア・シミュレーター・ゲーム「Fighter Ace」を代表として、アメリカ以外にもライセンサーを開拓しており、VR-1のネットワーク・テクノロジーの中核を形成する技術です。)この「SARAC」のライセンス契約交渉を通じて、VR-1社CEOだった30代半ばの若いビジネスマンMike Monitz氏との交流が始まりました。Monitz氏はハーバード・ビジネス・スクール出身の若き秀才であり、彼のパートナーであるテクノロジー・サイドのTOPで、当時31才だった天才型のMark Vange氏とのコンビネーションはアメリカンITベンチャーの典型的なスタイルを持ち、世界各国の多くの有力企業や投資組合などの資金を集めてIPOを目指して精力的に活動していました。Monitz氏はMicrosoftやHewlett PackardなどのIT系企業ばかりでなく、米軍関係者やカナダのエンジェル、コンピューター業界の年金ファンドなどの投資家を開拓し、98年当時で約1億ドルの資金を集めていました。私は彼のその若さと情熱に大いに感服して、アメリカの新しいビジネスのダイナミズムを目の当たりにして正直、圧倒されました。そして、この若き経営者に日本の市場と投資家についての情報を提供し、ソネットとのライセンス契約以上の個人的な関係を築いて、彼とVR-1社をサポートしようと思ったのです。
こうした一種異常な「ムード」の中で、私自身もデジタル革命とインターネット時代の真只中で仕事を続けてきたことと、アメリカの凄まじい変化を実感していたことによって、日本の新しいマーケットの誕生を確信していました。基本的にその「確信」は現在でも変わっていないのですが、その新しいマーケットの誕生には様々な条件があること、とりわけ産業構造の転換に繋がる巨大な社会システムの変化については、私の想像を遥かに越えるエネルギーが必要なことについては、その「ムード」の中では正直なところ気がついていませんでした。ソニーの一員であった頃にはデジタル産業への転換は日常的なことであり、プレイステーションとバイオの成功やソネットの立ち上げも順調に進んでいて、私の関わった新しい事業はいずれも順風満帆に推移していると見えていたからです。携帯電話は急成長し、i-modeの登場でインターネットも一気に普及していました。スターバックスやユニクロは急速に店鋪を増やして増収増益、UFJやディズニー・シーも大盛況、ホンダやトヨタも業績を伸ばしていて、日本は本当に不景気なのだろうか? と思う程に、IT関連企業に限らず新しいビジネス・モデルやテクノロジーをグローバルな視点で展開する企業はしっかりとした業績を上げていました。それは2002年の現在でも言えることなのですが、例えばここで例に挙げたスターバックスやユニクロ、UFJの場合は今年に入って少し様子が変わってきた様です。携帯電話ビジネスも急成長期から安定期に入ったと言われますし、自動車も2001/9/11のテロ事件後のアメリカ経済の減速によって先行きが不透明になってきました。
改めて1998年頃の私は、ネットワーク・ゲームの開発と市場性に傾注していて、インターネットの新しいエンタテインメント・コンテンツとしての将来性を探っていました。ソネットにおけるポストペットの成功に気を良くして、次はネットワーク・ゲームだ! とばかりに気負い込んでいたとも言えます。1997年のアメリカでのビジネス・ショー「E3」で発見したコロラド州デンバーのベンチャー企業VR-1社との出合いや日本のITバブルを演出したいくつかの企業との関係によって、ゲーム・ビジネスの新しい展開や制作業務の変化について、とくに新しいテクノロジーの必要性を強く感じていたことも背景にありながら、目の前で演じられているいくつかのバブル劇の有り様に気を取られていたことも否めません。VR-1社との関係は1998年初頭頃から急速に密接なものになりました。まずはソネットで取り組みを始めたネットワーク・ゲーム・サイトのメニューとして、VR-1の深海シミュレーション・ゲーム「SARAC」のライセンス契約交渉が始まりました。(このゲームは現在でもソネットの「Party Crew」でサービス中の本格的なリアルタイム・マルチ・プレイヤー型のネットワーク・ゲームの一つですが、このゲームのオペレーションにVR-1社の基幹サーバー技術である「コンダクター・ソリューション」が使われています。これはMicrosoft Gaming Zoneが提供している戦闘機バトル・エア・シミュレーター・ゲーム「Fighter Ace」を代表として、アメリカ以外にもライセンサーを開拓しており、VR-1のネットワーク・テクノロジーの中核を形成する技術です。)この「SARAC」のライセンス契約交渉を通じて、VR-1社CEOだった30代半ばの若いビジネスマンMike Monitz氏との交流が始まりました。Monitz氏はハーバード・ビジネス・スクール出身の若き秀才であり、彼のパートナーであるテクノロジー・サイドのTOPで、当時31才だった天才型のMark Vange氏とのコンビネーションはアメリカンITベンチャーの典型的なスタイルを持ち、世界各国の多くの有力企業や投資組合などの資金を集めてIPOを目指して精力的に活動していました。Monitz氏はMicrosoftやHewlett PackardなどのIT系企業ばかりでなく、米軍関係者やカナダのエンジェル、コンピューター業界の年金ファンドなどの投資家を開拓し、98年当時で約1億ドルの資金を集めていました。私は彼のその若さと情熱に大いに感服して、アメリカの新しいビジネスのダイナミズムを目の当たりにして正直、圧倒されました。そして、この若き経営者に日本の市場と投資家についての情報を提供し、ソネットとのライセンス契約以上の個人的な関係を築いて、彼とVR-1社をサポートしようと思ったのです。
19(第二部)
ネットワーク・ゲームへの関心は私の中でどんどん大きくなって行きましたが、その最大のきっかけは1997年頃から続々と登場したネット対戦型ゲームのサイトでした。中でも簡単なアプリケーションですぐに始められるPIA-to-PIA型の少人数ゲーム、例えば将棋や囲碁、マージャンといった私にとってはとても馴染みのある国産ゲームのサイトにはまりました。将棋や囲碁については、かつてパソコン通信の時代からネット対戦のフォーラムやSEGAの囲碁サービスなどが存在しましたが、いずれも一対一の対戦ですからそれ程の驚きはなかったのですが、4人リアルタイム対戦のマージャンは新鮮でした。当時の人気No.1マージャン・サイト「東風荘」には、毎晩最低2時間は繋いでいました。日に日に登録者数が増加しサバーの負荷増大のためになかなか繋がらなくなったり、対戦中にしばしば回線状態の不安定でゲームが中断したり、同時チャットやメッセンジャー・ソフトが加わってサービスの幅が広がったり・・・毎月のペースで何か新しい試みが追加されて行く様子はインターネットの急速な広がりと進歩を手に取るように見聞きすることの出来る一つの大きな現象でした。
前回もご紹介したアメリカのソニー・オンライン・エンタテインメント社は「Ever Quest」の開発に着手していて巨大な予算を投じて「マルチ・プレイヤー型ネットワークゲーム」の一つの理想形を模索していました。同時期にMicrosoftは3Dエア・コンバット・シミュレーターのマルチ・プレイヤー・ゲームを開発し既にサービスを始めていました。いずれもPCゲームソフトのサバイバルを目指して、プレステやサターンなどの家庭用ゲーム機に対抗する新しい遊びの方向として「ネットワーク・ゲーム」を選択したのです。そして、このMicrosoftの戦闘機対戦ゲームの開発を行った制作会社を知ったのは1997年にロス・アンゼルスで開かれたコンピュータ・ゲームのエキスポ「Electronic Entertainment EXPO E3」でした。このエキスポの最大の目玉はもちろんプレステとサターンでしたが、任天堂を加えた日本の3大メーカーのアメリカ市場での熾烈な競争を象徴する巨大なブースに並んで、日本のゲーム・ショーにはあまり登場しないPCゲームの制作会社が多数参加していました。アメリカの大手ゲーム・ソフト会社もゲーム機用のソフトと並んでPC用ゲームを数多く手掛けていて、日本とのPCの普及度合いの違いを浮き彫りにしていました。その中で、ブースのデザイン、社名とそのロゴのユニークさによって異彩を放っていた制作会社の一つで、デンバーに本社を構えるという「VR-1」という会社に強い興味を覚えました。
ネットワーク・ゲームの技術はゲームの設計力を裏付ける通信環境に関する知識とインターネット上のサーバー周辺技術によって支えられています。現在の日本ではブロードバンドへの急速なシフトが進んでいますが、5年前のアメリカではやっと14.4Kから28.8Kへのが始まった頃でした。PC内蔵モデムが標準化した頃でもあります。この頃のいわゆる「ナローバンド」環境でのネットワーク・ゲームは、サーバー/クライアント型のマルチユーザーを対象とするゲームを目指していたとは言え、現実的には世界中で完璧なシステムを達成したところはまだ一つもありませんでした。「VR-1」社の目標はこの「サーバー/クライアント型マルチユーザー対応ネットワーク・ゲーム」のプラットフォーム作りであり、実証例として先に述べたMicrosoftの3Dエア・コンバット・シミュレーターを稼動させようとしていたのです。この97年のEXPOではβ版のデモを見せていましたが、この戦闘機対戦ゲームの他にもタンク・バトルや潜水艦シミュレーター、RPGなど10種類近いゲームソフトのデモを行っていました。「VR-1 Conductor」と呼ばれるフロント/エンド・サーバーの制御機能はゲームのみならず、インターネットの様々なサービスへの応用も考えられるユニークなもので、インターネット通信の根本的な欠点に対する有力なソリューションでもあったのです。
私はこのユニークな技術を有するベンチャー企業に強い関心を持ち、So-netのゲーム・サービスへの利用を考え始めました。この会社に出資していた投資家にはMicrosoft、PSI Net、ドイツ・テレコム、ヒューレット・パッカードなどの有力企業グループが名を連ねていましたが、日本からの投資にはさほどの関心がなかった様子でした。私はソニーを始めとして、国内の投資家を見つけることも考えながら、この会社の技術力と高い理想に共感していました。このEXPOからの帰国後に日本市場とのアクセスを仲介するLAのコンサルティング会社とその日本窓口の会社から、全く別途のルートの照会を受けた時には偶然とは言え何か「縁」を感じて、早速具体的な接触を開始しました。その時の私のステータスは、So-netのエグゼクティブ・プロデューサーでしたが、既に私の古巣であるソニー・ミュージックを退社して、POW社というゲーム制作会社の役員を兼務していました。このPOWの創立者である和田氏と専務の本山氏とはSMEのマルチメディア本部の時代に、いくつかのユニークなPS用ゲーム・タイトルの制作を共にしていました。その縁もあり、和田氏の暖かい支援によってPOWの役員に招聘され、同時にSo-netの山本社長のご配慮によってエグゼクティブ・プロデューサーとしてのステイタスも頂いて、ネットワーク・ゲームを中心とした新しいインターネット・コンテンツの開発を委嘱されました。この二つの重責を担って、インターネットの最先端とも言えるアメリカのベンチャー企業との付き合いが始まってゆきます。
前回もご紹介したアメリカのソニー・オンライン・エンタテインメント社は「Ever Quest」の開発に着手していて巨大な予算を投じて「マルチ・プレイヤー型ネットワークゲーム」の一つの理想形を模索していました。同時期にMicrosoftは3Dエア・コンバット・シミュレーターのマルチ・プレイヤー・ゲームを開発し既にサービスを始めていました。いずれもPCゲームソフトのサバイバルを目指して、プレステやサターンなどの家庭用ゲーム機に対抗する新しい遊びの方向として「ネットワーク・ゲーム」を選択したのです。そして、このMicrosoftの戦闘機対戦ゲームの開発を行った制作会社を知ったのは1997年にロス・アンゼルスで開かれたコンピュータ・ゲームのエキスポ「Electronic Entertainment EXPO E3」でした。このエキスポの最大の目玉はもちろんプレステとサターンでしたが、任天堂を加えた日本の3大メーカーのアメリカ市場での熾烈な競争を象徴する巨大なブースに並んで、日本のゲーム・ショーにはあまり登場しないPCゲームの制作会社が多数参加していました。アメリカの大手ゲーム・ソフト会社もゲーム機用のソフトと並んでPC用ゲームを数多く手掛けていて、日本とのPCの普及度合いの違いを浮き彫りにしていました。その中で、ブースのデザイン、社名とそのロゴのユニークさによって異彩を放っていた制作会社の一つで、デンバーに本社を構えるという「VR-1」という会社に強い興味を覚えました。
ネットワーク・ゲームの技術はゲームの設計力を裏付ける通信環境に関する知識とインターネット上のサーバー周辺技術によって支えられています。現在の日本ではブロードバンドへの急速なシフトが進んでいますが、5年前のアメリカではやっと14.4Kから28.8Kへのが始まった頃でした。PC内蔵モデムが標準化した頃でもあります。この頃のいわゆる「ナローバンド」環境でのネットワーク・ゲームは、サーバー/クライアント型のマルチユーザーを対象とするゲームを目指していたとは言え、現実的には世界中で完璧なシステムを達成したところはまだ一つもありませんでした。「VR-1」社の目標はこの「サーバー/クライアント型マルチユーザー対応ネットワーク・ゲーム」のプラットフォーム作りであり、実証例として先に述べたMicrosoftの3Dエア・コンバット・シミュレーターを稼動させようとしていたのです。この97年のEXPOではβ版のデモを見せていましたが、この戦闘機対戦ゲームの他にもタンク・バトルや潜水艦シミュレーター、RPGなど10種類近いゲームソフトのデモを行っていました。「VR-1 Conductor」と呼ばれるフロント/エンド・サーバーの制御機能はゲームのみならず、インターネットの様々なサービスへの応用も考えられるユニークなもので、インターネット通信の根本的な欠点に対する有力なソリューションでもあったのです。
私はこのユニークな技術を有するベンチャー企業に強い関心を持ち、So-netのゲーム・サービスへの利用を考え始めました。この会社に出資していた投資家にはMicrosoft、PSI Net、ドイツ・テレコム、ヒューレット・パッカードなどの有力企業グループが名を連ねていましたが、日本からの投資にはさほどの関心がなかった様子でした。私はソニーを始めとして、国内の投資家を見つけることも考えながら、この会社の技術力と高い理想に共感していました。このEXPOからの帰国後に日本市場とのアクセスを仲介するLAのコンサルティング会社とその日本窓口の会社から、全く別途のルートの照会を受けた時には偶然とは言え何か「縁」を感じて、早速具体的な接触を開始しました。その時の私のステータスは、So-netのエグゼクティブ・プロデューサーでしたが、既に私の古巣であるソニー・ミュージックを退社して、POW社というゲーム制作会社の役員を兼務していました。このPOWの創立者である和田氏と専務の本山氏とはSMEのマルチメディア本部の時代に、いくつかのユニークなPS用ゲーム・タイトルの制作を共にしていました。その縁もあり、和田氏の暖かい支援によってPOWの役員に招聘され、同時にSo-netの山本社長のご配慮によってエグゼクティブ・プロデューサーとしてのステイタスも頂いて、ネットワーク・ゲームを中心とした新しいインターネット・コンテンツの開発を委嘱されました。この二つの重責を担って、インターネットの最先端とも言えるアメリカのベンチャー企業との付き合いが始まってゆきます。
18(第二部)
デジタル時代の本格的な始まりの時期=1995年前後は日本国内はバブル崩壊後の景気停滞期であり、一方アメリカはITブームが巻き起こる好景気の真只中にありました。この時代の先端にあった新しい産業市場の担い手は国内で言えばソフトバンク、NTTドコモ、ソニーに代表される企業で、その周辺にハードウェア&ソフトウェアに加えてコンテンツという(古くて)新しい担い手が注目を集め始めます。「コンテンツ」という言葉が一般化したのはまさに1995年頃からですが、デジタル革命がもたらした新たな価値の表現です。端的な例は音楽や映像の「記録」であり、アナログからデジタルへと記録方式が飛躍的な変化を遂げる中で、放送と通信の融合が進んでいるプロセスと同時進行で、アナログ記録のデジタル変換技術や大容量データの圧縮技術が急ピッチで開発されました。
放送にとっての「プログラム」はコンピューターにおけるソフトウェアと同様に、インフラ(=ハードウェア)を機能させるために最も重要な「要素」であり、ネットワークの概念も放送における放送局同士の連係という形で発展してきました。CNNのような「ニュース専門」チャンネルなどは特にニュースソースの「売買」をビジネスの中心に据えた新しいタイプの放送局であり、メディアの価値を「コンテンツ」に置いて成功した最も典型的な例という事が出来ます。彼らにとっての最大の収益源は全世界の放送局との「ネットワーク」であり、そのネットワークを維持発展させるための最大の「商品」は彼らが独自に集めるユニークなニュース・コンテンツです。そのニュース素材を絶え間なく、しかも誰よりも早く収集し、全世界に配達することが最も重要な仕事であり、その為に取材のネットワーク作りと取材方法の開発には巨大な投資をし続けています。「ビデオ・ジャーナリスト」の育成などはその典型的な例ですが、一人でカメラマン、エディター、インタビュアーそしてコメンテーターをマルチにこなす人材を世界中に開発してきました。インターネットの発展はこのような放送の「コンテンツ」についても、放送局とならぶ新たなパーソナル・メディアとして取り込んで行くことになりました。つまり、元来「双方向」を前提とする通信がPCを端末とする回線経由の「一方向」通信として使うことによって、放送の機能を包含することになったのです。
So-netでの「コンテンツ」ビジネスの展開について、「ポストペット」の次に何をやるか? 1997年頃、既にアメリカが先行していたインターネット向けコンテンツ開発の中でも「放送」のパーソナル化を睨んだ試みは比較的遅れていました。最大のネックは「コンテンツ」のデータ容量の大きさと回線速度の遅さでした。ストレスなく放送並みのクォリティを提供するにはユーザーの通信環境も非力でしたし、また動画の送受信などはデータの大きさから見て10年は無理とすら考えられていました。そうした高いハードルを前に、果敢に技術開発を進めていたアメリカの企業がありました。一例はアメリカのリアル・ネットワークス社であり、アカマイ社です。リアル社はストリーミング技術、そしてアカマイ社はキャッシュ技術の会社で、どちらも現在では世界標準と呼べる技術を提供するまでに成長しましたが、いずれもインターネットの弱点を解決するために、基礎技術の研究に精力を注ぎ込んできた新興企業です。その基礎技術の中核は「データの圧縮」と「データの蓄積」を軸としたものですが、データベースと回線の間に置かれる中継用のデバイス・ソフトウェア(ミドルウェアとも呼ばれます)の技術開発です。一方、プラウザーの機能についてはMicrosoftのInternet Explorerの独占に等しい状況の中、動画再生のプラグインとしてはMacomedia FLASHが標準となりつつあり、またストリーミング用にはリアル・プレイヤーが一般化し始めていました。
Sonyのオンライン・サービス会社としてはアメリカのソニーオンライン・エンタテインメント社(SOEA)が1996年に設立され、アメリカで音楽配信やネットワーク・ゲームのサービスを始めようと動き始めていましたが、この会社自体は基本的にサービスとマーケティングの会社であった為、技術面ではソニー・ピクチャーズとソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)のサンディエゴのPC部門が支える形でした。(この楽歴書で前回触れたデモンストレーション・イベントはこのSCEのPC部門が行ったものだったのです。)このSOEAの代表は有能な女性プロデューサーで、私も何度かニューヨークで彼女と会い、色々な議論を重ねました。特に当時、既に日本国内やシンガポールなどでヒットの兆しが見え始めていた「ポストペット」の米国版ライセンスの売り込みを行いましたが、残念ながら彼らには小学生以下の「子供用ソフト」としてしか見えなかったようで、キャラクターの魅力や可愛らしさを高く評価してくれたものの、アメリカでは「子供」がPCを使ってメールをやり取りするのは全くリアリティがなく、また「ポストペット・パーク」のような有料サービスサイトを小学生が利用することは親が認めないとの見解を得ました。(このようなキャラクターへの認識のギャップは「ドラクエ」や「キティ」も同様で、アメリカではヤング層も一緒になって愛玩するアニメ系のキャラといえば彼らが子供の頃に馴れ親しんだディズニーものやアメコミ系に限られています。すなわち日本産の、しかも最近のキャラクターについては大人の層には愛着もなく、あくまで「子供用」のキャラとしてしか写らない現実があります。)このSOEAとの接触の中でアメリカのインターネット・コンテンツ・ビジネスのリアルタイムな動きを色々と見聞し、最先端のテクノロジーやマーケティングの情報を数多く学ぶことができました。So-netのコンテンツ・ビジネスのこれからの方向性について、やはり先行するアメリカの技術の導入は不可欠だと感じました。
放送にとっての「プログラム」はコンピューターにおけるソフトウェアと同様に、インフラ(=ハードウェア)を機能させるために最も重要な「要素」であり、ネットワークの概念も放送における放送局同士の連係という形で発展してきました。CNNのような「ニュース専門」チャンネルなどは特にニュースソースの「売買」をビジネスの中心に据えた新しいタイプの放送局であり、メディアの価値を「コンテンツ」に置いて成功した最も典型的な例という事が出来ます。彼らにとっての最大の収益源は全世界の放送局との「ネットワーク」であり、そのネットワークを維持発展させるための最大の「商品」は彼らが独自に集めるユニークなニュース・コンテンツです。そのニュース素材を絶え間なく、しかも誰よりも早く収集し、全世界に配達することが最も重要な仕事であり、その為に取材のネットワーク作りと取材方法の開発には巨大な投資をし続けています。「ビデオ・ジャーナリスト」の育成などはその典型的な例ですが、一人でカメラマン、エディター、インタビュアーそしてコメンテーターをマルチにこなす人材を世界中に開発してきました。インターネットの発展はこのような放送の「コンテンツ」についても、放送局とならぶ新たなパーソナル・メディアとして取り込んで行くことになりました。つまり、元来「双方向」を前提とする通信がPCを端末とする回線経由の「一方向」通信として使うことによって、放送の機能を包含することになったのです。
So-netでの「コンテンツ」ビジネスの展開について、「ポストペット」の次に何をやるか? 1997年頃、既にアメリカが先行していたインターネット向けコンテンツ開発の中でも「放送」のパーソナル化を睨んだ試みは比較的遅れていました。最大のネックは「コンテンツ」のデータ容量の大きさと回線速度の遅さでした。ストレスなく放送並みのクォリティを提供するにはユーザーの通信環境も非力でしたし、また動画の送受信などはデータの大きさから見て10年は無理とすら考えられていました。そうした高いハードルを前に、果敢に技術開発を進めていたアメリカの企業がありました。一例はアメリカのリアル・ネットワークス社であり、アカマイ社です。リアル社はストリーミング技術、そしてアカマイ社はキャッシュ技術の会社で、どちらも現在では世界標準と呼べる技術を提供するまでに成長しましたが、いずれもインターネットの弱点を解決するために、基礎技術の研究に精力を注ぎ込んできた新興企業です。その基礎技術の中核は「データの圧縮」と「データの蓄積」を軸としたものですが、データベースと回線の間に置かれる中継用のデバイス・ソフトウェア(ミドルウェアとも呼ばれます)の技術開発です。一方、プラウザーの機能についてはMicrosoftのInternet Explorerの独占に等しい状況の中、動画再生のプラグインとしてはMacomedia FLASHが標準となりつつあり、またストリーミング用にはリアル・プレイヤーが一般化し始めていました。
Sonyのオンライン・サービス会社としてはアメリカのソニーオンライン・エンタテインメント社(SOEA)が1996年に設立され、アメリカで音楽配信やネットワーク・ゲームのサービスを始めようと動き始めていましたが、この会社自体は基本的にサービスとマーケティングの会社であった為、技術面ではソニー・ピクチャーズとソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)のサンディエゴのPC部門が支える形でした。(この楽歴書で前回触れたデモンストレーション・イベントはこのSCEのPC部門が行ったものだったのです。)このSOEAの代表は有能な女性プロデューサーで、私も何度かニューヨークで彼女と会い、色々な議論を重ねました。特に当時、既に日本国内やシンガポールなどでヒットの兆しが見え始めていた「ポストペット」の米国版ライセンスの売り込みを行いましたが、残念ながら彼らには小学生以下の「子供用ソフト」としてしか見えなかったようで、キャラクターの魅力や可愛らしさを高く評価してくれたものの、アメリカでは「子供」がPCを使ってメールをやり取りするのは全くリアリティがなく、また「ポストペット・パーク」のような有料サービスサイトを小学生が利用することは親が認めないとの見解を得ました。(このようなキャラクターへの認識のギャップは「ドラクエ」や「キティ」も同様で、アメリカではヤング層も一緒になって愛玩するアニメ系のキャラといえば彼らが子供の頃に馴れ親しんだディズニーものやアメコミ系に限られています。すなわち日本産の、しかも最近のキャラクターについては大人の層には愛着もなく、あくまで「子供用」のキャラとしてしか写らない現実があります。)このSOEAとの接触の中でアメリカのインターネット・コンテンツ・ビジネスのリアルタイムな動きを色々と見聞し、最先端のテクノロジーやマーケティングの情報を数多く学ぶことができました。So-netのコンテンツ・ビジネスのこれからの方向性について、やはり先行するアメリカの技術の導入は不可欠だと感じました。
17(第二部)
前回は「ポストペットパーク」のコンセプトについて書きましたが、その中で触れた「バーチャル・ワールド」のことをもう少し掘り下げてみたいと思います。まずは身近な素材として、「ファイナル・ファンタジー」のネット版を取り上げたいと思いますが、6月のサービス開始から夏休み期間中を通して、最近の一日当りのアクセスは約12,000名程度と言われています。ブロードバンド常時接続ユーザーが80%ということですが、相変わらず深夜の接続が70%でサーバーの負荷は午前0時前後にピークになるようです。当初の予想通り、コア・ユーザーの平均年齢は20歳以上ということですから、明らかに高年齢のハイエンド・ゲームユーザーのためのソフトウェアということになっています。
ネットワーク・ゲームは私にとっても大きな「テーマ」です。およそ6年前にインターネット・ベースのネットワーク・ゲームの開発に着手しましたが、先行していたアメリカでも28.8Kモデムをネクストスタンダードとして位置付けていたほど、電話回線ベースの通信速度環境の条件設定は不確かなものでした。理論的な「リアルタイム」のネットワーク・ゲームはLAN上ではほぼ完全に実現されていました。もちろんゲーム・カテゴリーによる難易度の違いはありましたが、マルチ・プレイヤー・ゲームの原型といえるアクション・ゲームの「コンバット・シュミレーター」を12台のLAN上のPCで対戦している様子を見たのは95年、米シリコンバレーのゲーム制作会社でのことです。この時の驚きは、既にグラフィクスが3DCGで作られていたこととそれを動かす200MHzCPUの驚異的なスピードを目の当たりにしたことでした。現代の感覚で言えば200MHzCPU搭載機などは秋葉原のジャンク・ショップであれば\10,000程度で売っているようなレベルですが、わずか7年前には超高速の最先端であったことを思うと恐ろしい位の進化のスピードです。このCPUスピードの驚異的な進化に比較して、通信環境の方はかなり遅れているという印象です。この7年前の時点ですらFTTH(家庭用の光ケーブル網)は米国では時間の問題だとの認識が一般的でした。ITバブルに突入してゆく頃のイケイケのアメリカでは当然のことだったかもしれませんが、この頃のアメリカ各地で開かれたコンピューター関連のビジネスショーにでかけるとこうした「夢」のネットワーク社会の到来は西暦2000年をひとつの転機として一気に実現されるという論調で埋め尽くされていました。
さて、ネットワーク・ゲームの究極型は「マルチ・プレイヤー・オンライン・ゲーム」のバーチャル・ワールド・ソフトウェアだと直感したのは1997年にサン・ディエゴのスタジオでプレゼンテーションを受けた時でした。このプレゼンテーションは、一部の関係者にのみ行われたアメリカのソニー・オンラインという新会社のネットワーク・サービスの内容説明で、その目玉として紹介された「エバー・クエスト」のプロトタイプ・コンセプトでした。この「エバー・クエスト」は、ロールプレイング・ゲーム・スタイルのマルチ・プレイヤー・オンライン・ゲームの、現時点での最高傑作であると共に、最も成功した、また最もお金のかかっているゲームです。正式スタートから3年を経過した現在でも世界一のプレイヤー数を誇るゲームであり、かつバーチャル・ワールドの最大の具体例だとも言えるでしょう。ここで展開される「世界」はRPG定番の中世的世界ですが、いずれ近未来を想定した映画「ブレードランナー」のような世界で展開されるバーチャル・ワールドでのシミュレーション・タイプのRPGが登場する予定を聞いていますが、それが実現されると「仮想と現実」の境界がますます曖昧なものになってゆくような気がして、ちょっと恐ろしい気持ちになるのは私だけでしょうか。
バーチャル・ワールドのソフトウェアのアイディアは、これまでのところはコマーシャル性を求める結果、ハリウッド映画のアクション系作品のようなものが大半です。「マトリックス」「ブレイド」「MIB」などの近未来設定のハードコア・ムービータイプが多いために、「殺戮」や「戦闘」といったより一層生々しい「ゲーム・エレメント」が強調されがちです。リアリティが追求されればされるほどサディスティックな世界が展開され、非現実ではありながら異常者やサイコキラーのようなキャラクターがこれでもかというほどに登場する「ワールド」がネットに多数存在するようになるでしょう。エキセントリックなエンタテインメントであるとは言え、バーチャル・ワールドの「裏」の世界がそれほどまでに繁殖すると、ますます青少年への悪影響などが懸念される事態が想定されます。アメリカではゲーム・ソフトにもいわゆる「R指定」が存在しますが、映画やゲームとは比較にならないほど「バーチャル・ワールド」でのシミュレーションがもたらす人間への精神的・心理的な影響は大きいと思います。テクノロジーの進歩がもたらす「負」の効果として、バーチャル・ワールドには私たちがこれまでに未体験の領域が沢山含まれているだけに、時として大きな不安を感じます。PS2の「僕の夏休み」やアニメーションの「千と千尋」のような「仮想世界」が主流になってくれたらなぁ、と思いつつ、我らの「ポストペットパーク」の目指す「世界」の楽しさを、これからもっともっと多くの人に体験してもらいたいと願っています。
ネットワーク・ゲームは私にとっても大きな「テーマ」です。およそ6年前にインターネット・ベースのネットワーク・ゲームの開発に着手しましたが、先行していたアメリカでも28.8Kモデムをネクストスタンダードとして位置付けていたほど、電話回線ベースの通信速度環境の条件設定は不確かなものでした。理論的な「リアルタイム」のネットワーク・ゲームはLAN上ではほぼ完全に実現されていました。もちろんゲーム・カテゴリーによる難易度の違いはありましたが、マルチ・プレイヤー・ゲームの原型といえるアクション・ゲームの「コンバット・シュミレーター」を12台のLAN上のPCで対戦している様子を見たのは95年、米シリコンバレーのゲーム制作会社でのことです。この時の驚きは、既にグラフィクスが3DCGで作られていたこととそれを動かす200MHzCPUの驚異的なスピードを目の当たりにしたことでした。現代の感覚で言えば200MHzCPU搭載機などは秋葉原のジャンク・ショップであれば\10,000程度で売っているようなレベルですが、わずか7年前には超高速の最先端であったことを思うと恐ろしい位の進化のスピードです。このCPUスピードの驚異的な進化に比較して、通信環境の方はかなり遅れているという印象です。この7年前の時点ですらFTTH(家庭用の光ケーブル網)は米国では時間の問題だとの認識が一般的でした。ITバブルに突入してゆく頃のイケイケのアメリカでは当然のことだったかもしれませんが、この頃のアメリカ各地で開かれたコンピューター関連のビジネスショーにでかけるとこうした「夢」のネットワーク社会の到来は西暦2000年をひとつの転機として一気に実現されるという論調で埋め尽くされていました。
さて、ネットワーク・ゲームの究極型は「マルチ・プレイヤー・オンライン・ゲーム」のバーチャル・ワールド・ソフトウェアだと直感したのは1997年にサン・ディエゴのスタジオでプレゼンテーションを受けた時でした。このプレゼンテーションは、一部の関係者にのみ行われたアメリカのソニー・オンラインという新会社のネットワーク・サービスの内容説明で、その目玉として紹介された「エバー・クエスト」のプロトタイプ・コンセプトでした。この「エバー・クエスト」は、ロールプレイング・ゲーム・スタイルのマルチ・プレイヤー・オンライン・ゲームの、現時点での最高傑作であると共に、最も成功した、また最もお金のかかっているゲームです。正式スタートから3年を経過した現在でも世界一のプレイヤー数を誇るゲームであり、かつバーチャル・ワールドの最大の具体例だとも言えるでしょう。ここで展開される「世界」はRPG定番の中世的世界ですが、いずれ近未来を想定した映画「ブレードランナー」のような世界で展開されるバーチャル・ワールドでのシミュレーション・タイプのRPGが登場する予定を聞いていますが、それが実現されると「仮想と現実」の境界がますます曖昧なものになってゆくような気がして、ちょっと恐ろしい気持ちになるのは私だけでしょうか。
バーチャル・ワールドのソフトウェアのアイディアは、これまでのところはコマーシャル性を求める結果、ハリウッド映画のアクション系作品のようなものが大半です。「マトリックス」「ブレイド」「MIB」などの近未来設定のハードコア・ムービータイプが多いために、「殺戮」や「戦闘」といったより一層生々しい「ゲーム・エレメント」が強調されがちです。リアリティが追求されればされるほどサディスティックな世界が展開され、非現実ではありながら異常者やサイコキラーのようなキャラクターがこれでもかというほどに登場する「ワールド」がネットに多数存在するようになるでしょう。エキセントリックなエンタテインメントであるとは言え、バーチャル・ワールドの「裏」の世界がそれほどまでに繁殖すると、ますます青少年への悪影響などが懸念される事態が想定されます。アメリカではゲーム・ソフトにもいわゆる「R指定」が存在しますが、映画やゲームとは比較にならないほど「バーチャル・ワールド」でのシミュレーションがもたらす人間への精神的・心理的な影響は大きいと思います。テクノロジーの進歩がもたらす「負」の効果として、バーチャル・ワールドには私たちがこれまでに未体験の領域が沢山含まれているだけに、時として大きな不安を感じます。PS2の「僕の夏休み」やアニメーションの「千と千尋」のような「仮想世界」が主流になってくれたらなぁ、と思いつつ、我らの「ポストペットパーク」の目指す「世界」の楽しさを、これからもっともっと多くの人に体験してもらいたいと願っています。
16(第二部)
現在のSo-net HPのメイン・コンテンツの一つに「ポストペットパーク」がありますが、この「パーク」が正式オープンしたのは97年の5月だったと思います。以来、「パーク」のメンバーは延べ200万人に達し、まさに「ビッグサイト」の一つに成長しました。「ポストペット」の面白さと魅力の半分は、この「パーク」の存在によると思います。電子メールソフトとしての「ポストペット」は「ポストペットパーク」によって単なるメール・アプリケーションとは違う、新しいエンタテインメントの世界を生み出しました。IT時代の到来によって様々な形で語られていた「バーチャル・ワールド」のまさに最も具体的な事例として、世界的にも例を見ないユニークなコンテンツ・サービスであると言うことが出来ます。
この「ポストペットパーク」のコンセプトは、大きく2つのアイディアによって形作られています。一つは「ポストペット」のアプリケーションとしての機能をウェブサイトを通して拡張するという事であり、もう一つは「ポストペットユーザー」同士の相互コミュニケーションをウェブサイトによって促進するという事です。そして、この2つのメイン・ファンクションをユーザーに幅広く活用してもらうための「仕掛け」の充実が「パーク」の楽しさを一層引き立てるということを、企画のメンバーは当初から「ディズニーランド」などのテーマパークの手法の中に見出していました。シーズン・イベント、キャラクター・ワールド、アトラクション・ゾーン、ショップ&イートといったテーマパークのエンタテインメント・レイアウトをバーチャルに展開するという構想が現実のウェブサイトとして皆さんの支持を得られたという例は他にはほとんど見ることが出来ません。その点でもたいへんユニークな存在であり、またオープン当初に大きな反響を呼び、業界的にも注目を集める事になったのだと思います。
ネットを利用して様々な情報やサービスを受けたり利用したりということは現在では当たり前の事になりました。かつての「VAN」や「WAN」といった言葉を知っている人もほとんどいなくなってしまう程に急速にネット社会は進化しています。ところが、こうしたネット・サービスの90%はリアル・ワールドの置き換えにすぎないのです。もちろん従来は不便であったものが飛躍的に便利になった例は沢山あります。それによって一部の人のものだったサービスが幅広い人に開かれたサービスに生まれ変わった例として最も端的なものは「オークション」でしょう。(私自身は「フリーマーケット」のネット版として捉えていますが、実は「古物」のオープンな販売には本来は行政への登録と許可証が必要なのです。現在のネット・オークションはあくまで「個人対個人の取引」という前提ですが、実際には多数の「業者」が存在します。「リサイクル・ショップ」同様、時代的な背景も手伝ってネット・オークションは急速に広がっていますが、ここでの「儲け」を所得として申告している人は少ないでしょう。)「ネット証券」は正規の手続きを踏んだ上で、小口の個人投資家を開拓することに大いに役立っています。証券会社のセールスを介さずに自主的に資金運用をしたい人には最適なシステムです。(もちろんここでの「儲け」は所得対象ですが、こちらの方は税金の支払をきちんと行うように「ネット証券会社」の指導も行き届いているようです。)航空券やホテルの予約といった「トラベル」サービスでは、旅行代理店を介さずにダイレクト・コンタクトをする人々が増えて来ました。各航空会社のサービスもダイレクト・コンタクト・ユーザーに色々なインセンティブを用意しています。しかし、こうした事例はいずれも従来のサービスをネットによってよりスピーディーに、より幅広くオープンで便利な姿に進化させていますが、あくまでもリアル・ワールドのサービスです。
「ポストペットパーク」は、リアルな「テーマパーク」を便利で、利用しやすいものにしたのとは全く違います。この「テーマパーク」は完全にバーチャルな「想像上」のパークですから、そこで楽しんでいるのは基本的には「ペット」であり、いわゆる「ベット・オーナー」であるユーザーは自分の楽しみ方をいわば「シュミレート」していることになります。コミックスや映画、ドラマ、ゲームと同様に「仮想現実」を追体験する面白さを楽しんでいるのですから、完全なエンタテインメントであって、言い換えれば具体的なメリット、つまりお金や情報、時間といったリアルなメリットはまったくありません。ここで得られるユーザーのメリットといえば「笑い」や「驚き」や「シンパシー」といった情緒的な感性の領域の事柄です。(唯一の例外が「メル友」探しでしょうか。)メールソフトとしての「ポストペット」は、電子メールを送受信するするためのアプリケーションであることはもちろんですが、その機能はむしろ二次的な、あるいはゼロ次的な機能です。もちろんメールでやり取りされる内容はリアルな世界の「メッセージ」として重要な意味を持っていますが、そのメールにくっついてくる「ペット」は全く別の世界の存在で、このリアルとバーチャルの組み合わせが他に例のないユニークなエンタテインメントとして、多くの皆さんに関心を持って頂いたのだと思います。そして「ポストペットパーク」は、メールを運んでくる「ペット」の存在を単なるメールのアクセサリーに留まらないバーチャルなリアリティを感じさせる存在に感じさせるための大切な「場」なのだと思います。
この「ポストペットパーク」のコンセプトは、大きく2つのアイディアによって形作られています。一つは「ポストペット」のアプリケーションとしての機能をウェブサイトを通して拡張するという事であり、もう一つは「ポストペットユーザー」同士の相互コミュニケーションをウェブサイトによって促進するという事です。そして、この2つのメイン・ファンクションをユーザーに幅広く活用してもらうための「仕掛け」の充実が「パーク」の楽しさを一層引き立てるということを、企画のメンバーは当初から「ディズニーランド」などのテーマパークの手法の中に見出していました。シーズン・イベント、キャラクター・ワールド、アトラクション・ゾーン、ショップ&イートといったテーマパークのエンタテインメント・レイアウトをバーチャルに展開するという構想が現実のウェブサイトとして皆さんの支持を得られたという例は他にはほとんど見ることが出来ません。その点でもたいへんユニークな存在であり、またオープン当初に大きな反響を呼び、業界的にも注目を集める事になったのだと思います。
ネットを利用して様々な情報やサービスを受けたり利用したりということは現在では当たり前の事になりました。かつての「VAN」や「WAN」といった言葉を知っている人もほとんどいなくなってしまう程に急速にネット社会は進化しています。ところが、こうしたネット・サービスの90%はリアル・ワールドの置き換えにすぎないのです。もちろん従来は不便であったものが飛躍的に便利になった例は沢山あります。それによって一部の人のものだったサービスが幅広い人に開かれたサービスに生まれ変わった例として最も端的なものは「オークション」でしょう。(私自身は「フリーマーケット」のネット版として捉えていますが、実は「古物」のオープンな販売には本来は行政への登録と許可証が必要なのです。現在のネット・オークションはあくまで「個人対個人の取引」という前提ですが、実際には多数の「業者」が存在します。「リサイクル・ショップ」同様、時代的な背景も手伝ってネット・オークションは急速に広がっていますが、ここでの「儲け」を所得として申告している人は少ないでしょう。)「ネット証券」は正規の手続きを踏んだ上で、小口の個人投資家を開拓することに大いに役立っています。証券会社のセールスを介さずに自主的に資金運用をしたい人には最適なシステムです。(もちろんここでの「儲け」は所得対象ですが、こちらの方は税金の支払をきちんと行うように「ネット証券会社」の指導も行き届いているようです。)航空券やホテルの予約といった「トラベル」サービスでは、旅行代理店を介さずにダイレクト・コンタクトをする人々が増えて来ました。各航空会社のサービスもダイレクト・コンタクト・ユーザーに色々なインセンティブを用意しています。しかし、こうした事例はいずれも従来のサービスをネットによってよりスピーディーに、より幅広くオープンで便利な姿に進化させていますが、あくまでもリアル・ワールドのサービスです。
「ポストペットパーク」は、リアルな「テーマパーク」を便利で、利用しやすいものにしたのとは全く違います。この「テーマパーク」は完全にバーチャルな「想像上」のパークですから、そこで楽しんでいるのは基本的には「ペット」であり、いわゆる「ベット・オーナー」であるユーザーは自分の楽しみ方をいわば「シュミレート」していることになります。コミックスや映画、ドラマ、ゲームと同様に「仮想現実」を追体験する面白さを楽しんでいるのですから、完全なエンタテインメントであって、言い換えれば具体的なメリット、つまりお金や情報、時間といったリアルなメリットはまったくありません。ここで得られるユーザーのメリットといえば「笑い」や「驚き」や「シンパシー」といった情緒的な感性の領域の事柄です。(唯一の例外が「メル友」探しでしょうか。)メールソフトとしての「ポストペット」は、電子メールを送受信するするためのアプリケーションであることはもちろんですが、その機能はむしろ二次的な、あるいはゼロ次的な機能です。もちろんメールでやり取りされる内容はリアルな世界の「メッセージ」として重要な意味を持っていますが、そのメールにくっついてくる「ペット」は全く別の世界の存在で、このリアルとバーチャルの組み合わせが他に例のないユニークなエンタテインメントとして、多くの皆さんに関心を持って頂いたのだと思います。そして「ポストペットパーク」は、メールを運んでくる「ペット」の存在を単なるメールのアクセサリーに留まらないバーチャルなリアリティを感じさせる存在に感じさせるための大切な「場」なのだと思います。
15(第二部)
「バーチャル・ペット」という言葉が流行りだした97年頃は、「マルチメディア」という言葉が徐々に古臭い表現に感じられるようになってきた頃でもありました。日本国内のPC市場はアメリカの動きに追随して急激な普及のペースに入り、その最大の原動力は言うまでもなく「インターネット」でした。そして、「マルチメディア」は「IT」に変わり今日に至っていますが、既に2002年の今年にはアメリカの「IT」バブル崩壊という経済情勢を受けて、表現としての「IT」という言葉も陳腐化してきたような気がします。一方「バーチャル・ペット」は、97年当時の「たまごっち」のレベルから大きく様変わりして、リアルなロボット犬「AIBO」の登場によっていよいよ本格的なバーチャル・リアリティのレベルに進化してきました。「癒し」待望の時代と言われる日本の現代社会の一面にどこかで繋がっているのかもしれません。「ポストペット」の発想の原点には、特に「癒し」を意識した考えはありませんでしたが、結果として多くのユーザーの皆さんからの反響の中には「ボストペット」キャラクターたちへの温かな思い入れの様子が述べられていて、そこには本物のペットに対するのと全く変わりない「主人」たちの姿、思いが表れていました。
さて、こうした「バーチャル・ペット」を考える場合には極めて重要な先端テクノロジーが必要となります。皆さんも良くご存知の「AI=人工知能」の技術です。一口に「AI」といっても、その中身やレベルには大きな幅があり、「思考ルーチン」と言われるプログラムは携帯型ミニゲームや家電のマイコンレベルの制御プログラムにも組み込まれていますが、一種の個性を感じる「キャラクター」を表現するようなプログラムになるとかなり高度なものが必要になります。「ポストペット」の場合も企画、開発の初期段階で、「キャラクター」の設定に関して多くの議論がありました。差出人の分身となる「キャラ」がメールを運ぶ、という設定には、まず最初に大きな二つの形式があります。一つは、差出人の完全な代理としての「キャラ」である場合です。この方法は「キャラ」は差出人が任意に設定する自分自身の完全な「代理」として、差出人自身の意志によって「性格」を制御します。このケースでは「AI」のレベルはそれほど高度ではありません。もう一つは、「キャラ」自身が意志を制御する高度な「AI」を組み込んだケースです。この場合、差出人は好みの「キャラ」を選択できますが、その行動を完全に自分の意志でコントロールすることは出来ません。プロジェクトでは、まずこの「AI」のレベルを巡って様々な議論が展開されました。グラフィカル・インターフェイスを伴った電子メールソフト、という単純な話ではなかったのです。「AI」のレベルによっては、このソフトのプログラムは際限のない巨大なものになってしまいます。時間も労力も、そして技術力も、すべての意味でこの「AI」レベルがソフトの中身を決めるといっても過言ではありません。
企画の初期段階では、もう一つの大きな課題がありました。OSの問題です。そもそも、「ポストペット」のプロトタイプはMacOS上で作られていました。電子メール・ソフトとしての通信関係のプログラムはMacOSとWindowsOSでは少し考え方が異なります。基本的にはTCP/IPプロトコルによるインターネット上の通信ソフトですが、「ポストペット」はメール本体と「キャラ」ファイルのセットで通信する前提ですので、いわばメールに特殊なプログラム・ファイルを常に添付して送受信する事になります。この特殊な添付ファイルは、データであると共に相手側のアプリケーション上で動作するプログラムを含んでいますが、様々なプロバイダーのメール・サーバーを経由して、正確にOSの互換性を取って相手側に届けるためにはいくつかの課題がありました。単なるテキスト・データのやり取りとはレベルの違うメール・ソフトとしての完成度が必要だったのです。このOSの互換性については、初期のユーザーの方々は特にご記憶だと思いますが、サンプル・プログラムの配付が始まった頃から約1年間はMacOSのみのアプリケーションとして発表されました。そして正式にパッケージとして発売された「ポストペットDX」のバージョンはver.1.11となっています。この1年余りの間、プログラムを担当した幸喜君を中心としたプログラム・チームは連日連夜の徹夜作業と言ってもよい程のハードワークを続けていました。そして、テスト・バージョン・ユーザーの皆さんからも本当に沢山の貴重なデータやアドバイスを頂きました。
「ポストペット」のアイディアは、こうして具体的な現実のアプリケーションとして完成して行くのですが、私をはじめとして、原作者の八谷さん、真鍋さん、そしてソネットの北村プロデューサーの構想は、単にアプリケーションとしての「ポストペット」の実現だけを考えていたのではありませんでした。先に触れた「AI」の問題と共に、WebSiteとしての「ポストペット」であり、ネット上のバーチャル・テーマパークとしての「ポストペット」ももう一つの大きなテーマであり「夢」だったのです。「ポストペットDX」は、1997年度のマルチメディアグランプリで栄えある「通産大臣賞=グランプリ」を受賞しましたが、この受賞の大きな評価ポイントは、アプリケーションとしての完成度に加えて、連動したWebSiteによる「ネットワーク・コンテンツ」としてのユニークさが注目されたからです。
次回は、このWebSiteとしての「ポストペット」について、書こうと思います。
さて、こうした「バーチャル・ペット」を考える場合には極めて重要な先端テクノロジーが必要となります。皆さんも良くご存知の「AI=人工知能」の技術です。一口に「AI」といっても、その中身やレベルには大きな幅があり、「思考ルーチン」と言われるプログラムは携帯型ミニゲームや家電のマイコンレベルの制御プログラムにも組み込まれていますが、一種の個性を感じる「キャラクター」を表現するようなプログラムになるとかなり高度なものが必要になります。「ポストペット」の場合も企画、開発の初期段階で、「キャラクター」の設定に関して多くの議論がありました。差出人の分身となる「キャラ」がメールを運ぶ、という設定には、まず最初に大きな二つの形式があります。一つは、差出人の完全な代理としての「キャラ」である場合です。この方法は「キャラ」は差出人が任意に設定する自分自身の完全な「代理」として、差出人自身の意志によって「性格」を制御します。このケースでは「AI」のレベルはそれほど高度ではありません。もう一つは、「キャラ」自身が意志を制御する高度な「AI」を組み込んだケースです。この場合、差出人は好みの「キャラ」を選択できますが、その行動を完全に自分の意志でコントロールすることは出来ません。プロジェクトでは、まずこの「AI」のレベルを巡って様々な議論が展開されました。グラフィカル・インターフェイスを伴った電子メールソフト、という単純な話ではなかったのです。「AI」のレベルによっては、このソフトのプログラムは際限のない巨大なものになってしまいます。時間も労力も、そして技術力も、すべての意味でこの「AI」レベルがソフトの中身を決めるといっても過言ではありません。
企画の初期段階では、もう一つの大きな課題がありました。OSの問題です。そもそも、「ポストペット」のプロトタイプはMacOS上で作られていました。電子メール・ソフトとしての通信関係のプログラムはMacOSとWindowsOSでは少し考え方が異なります。基本的にはTCP/IPプロトコルによるインターネット上の通信ソフトですが、「ポストペット」はメール本体と「キャラ」ファイルのセットで通信する前提ですので、いわばメールに特殊なプログラム・ファイルを常に添付して送受信する事になります。この特殊な添付ファイルは、データであると共に相手側のアプリケーション上で動作するプログラムを含んでいますが、様々なプロバイダーのメール・サーバーを経由して、正確にOSの互換性を取って相手側に届けるためにはいくつかの課題がありました。単なるテキスト・データのやり取りとはレベルの違うメール・ソフトとしての完成度が必要だったのです。このOSの互換性については、初期のユーザーの方々は特にご記憶だと思いますが、サンプル・プログラムの配付が始まった頃から約1年間はMacOSのみのアプリケーションとして発表されました。そして正式にパッケージとして発売された「ポストペットDX」のバージョンはver.1.11となっています。この1年余りの間、プログラムを担当した幸喜君を中心としたプログラム・チームは連日連夜の徹夜作業と言ってもよい程のハードワークを続けていました。そして、テスト・バージョン・ユーザーの皆さんからも本当に沢山の貴重なデータやアドバイスを頂きました。
「ポストペット」のアイディアは、こうして具体的な現実のアプリケーションとして完成して行くのですが、私をはじめとして、原作者の八谷さん、真鍋さん、そしてソネットの北村プロデューサーの構想は、単にアプリケーションとしての「ポストペット」の実現だけを考えていたのではありませんでした。先に触れた「AI」の問題と共に、WebSiteとしての「ポストペット」であり、ネット上のバーチャル・テーマパークとしての「ポストペット」ももう一つの大きなテーマであり「夢」だったのです。「ポストペットDX」は、1997年度のマルチメディアグランプリで栄えある「通産大臣賞=グランプリ」を受賞しましたが、この受賞の大きな評価ポイントは、アプリケーションとしての完成度に加えて、連動したWebSiteによる「ネットワーク・コンテンツ」としてのユニークさが注目されたからです。
次回は、このWebSiteとしての「ポストペット」について、書こうと思います。
14(第二部)
1995年に始まった「ポストペット」の最初のプロジェクトには、発案者の八谷和彦さんと真鍋奈見江さん、そしてプログラム担当の幸喜俊さんとそのバンド仲間でSMEの浅野耕一郎さん、ソネット・チームはプロデューサーの北村くんと私を含め6名がアテンドしました。後にスタッフの数はどんどん増えてゆくのですが、オリジナルのファースト・チームは10名。あれから7年が経過して、現在までに企画開発に関わった延べ人数はおよそ100名に及ぶでしょう。
インターネット用の電子メール・ソフトとして、95年当時は「EUDRA」などのMac派のアプリケーションに、 Win95の登場と共にAOLやNiftyの専用ソフトや「Becky!」「OutLook」などが徐々に勢力を拡大してきた、という状況でした。国内のパソコン通信での電子メール利用者は100万人程度と言われていましたが、ISDNの実験サービスが始まったばかりで、通信環境のほとんどは14.4Kアナログ・モデムからいよいよ28.8Kになろうかという段階でした。私もパソコン通信をやっていましたが、電子メールの便利さには大いに感激しましたが、いかんせんマニアのコミュニティの域を出ず、むしろNiftyのフォーラムなどでのマニア同士の不思議な連帯性などは、今から思えば一般人からは少し変わった奴等だと見られていたかも知れません。その頃のSMEにも一部にNiftyメンバーがいましたが、会社のPCでは通信環境がないため、自宅からメールやフォーラムなどを利用していたようです。海外とのコミュニケーションのためやアメリカから通信販売の買い物をしている部長さんなどもいました。
私がソネットの立ち上げに関わることになったのは、堤光生氏(楽歴書第2部8回にてご紹介)の新しい事業部への参加が直接のきっかけですが、いよいよアメリカで商用インターネットの公開が始まった頃からデジタル時代の新しいビジネスとして個人的にも強い関心を持っていたからです。プロバイダー事業参入については、ソニーの中にも賛否両論があったようです。既にNiftyの100万人に及ぶパソコン通信利用者があり、新規のベンチャー企業としてはBEKKOAME NETが先行していました。なによりもネットワークのバックボーンとなる巨大な通信インフラの確保と、全国に展開するアクセスポイントについてはNTTの協力なくしては成立しません。(ソネット計画の当初は全世界での展開も視野に入っていたのですが、結果的にソニーのプロバイダー事業としては日本とアジアの一部に限られているのは、こうした巨大な投資と通信企業との幅広いアライアンスが必要だからです。)
ソネット創設者の一人、現社長の山本泉二さんは、早くから通信事業としてのプロバイダーは過当競争によって急速に通信料金が下がることを予見していました。彼は一貫してサービス・プロバイダーとしてのコンテンツ・ビジネスにこそ活路があると主張し、ソニー・グループのコンテンツ事業とのシナジーを目指していました。オークションやバンキングなどのファイナンス事業、音楽や映像の配信事業、Niftyフォーラムのようなネット・コミュニティ事業など、インターネット接続業と同時にデジタル時代のサービス業としてコンテンツ・ビジネスをソネットの重要な柱と捉えていたのです。山本社長は、ソネットをソニー株式会社の単独事業としてではなく、ソニー・ミュージックとの合弁事業として提案し、ゲーム会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメントに続く、SONY&SMEの2つめの合弁会社として設立しました。そして、その受け皿として堤さん率いるSMEマルチメディア本部が関与することになり、私が送り込まれたのです。ソネット構想については、私は早い時期から堤さんと共に山本さんの考えを伺っていました。そして、インターネットにおけるコンテンツ・ビジネスの具体的なアイディアを、アメリカでの事例などを参考にそれこそ夜も昼も考え続けていましたが、そこに浅野さんから「ポストペット」のアイディアが持ち込まれたのです。
インターネット普及の第一の「訴求点」は、プラウザーによるHP閲覧ではなく、電子メールのビジュアル化によるパソコン通信とのインターフェイスの違いだ、と直感しました。そして、その直感を確信に変えさせたもう一つの要素は、当時小学生の間で静かなプームとなっていた「たまごっち」でした。世の中で「バーチャル・ペット」という言葉が浸透し始めた頃のことです。同じ頃に、ゲームボーイの「ポケットモンスター」(ポケモン)が大ヒットとなって、品切れが続出していました。3Dグラフィックスのプレイステーションとは対極にあたる携帯型ゲームのヒットであり、任天堂の快挙です。その後、「たまごっち」は急速に大人のおもちゃにまで浸透すると共に、一気に飽和して様々な「ニセモノ」が出回って、結局アッ!という間に収束してしまいましたが、「ポケモン」はよく練られたゲーム性にコレクション・ホビーとしての姿を同時に展開して見事にキャラクター化を果たし、TVアニメから大スター「ピカチュウ」を生み出しました。ハードウェアとしての「おもちゃ」に留まった「たまごっち」とソフト・コンテンツとしての「キャラクター」に育った「ポケモン」の差、これが「ポストペット」の大きな教訓になったことは、プロジェクトのすべてのメンバーの共通の基本認識でした。
インターネット用の電子メール・ソフトとして、95年当時は「EUDRA」などのMac派のアプリケーションに、 Win95の登場と共にAOLやNiftyの専用ソフトや「Becky!」「OutLook」などが徐々に勢力を拡大してきた、という状況でした。国内のパソコン通信での電子メール利用者は100万人程度と言われていましたが、ISDNの実験サービスが始まったばかりで、通信環境のほとんどは14.4Kアナログ・モデムからいよいよ28.8Kになろうかという段階でした。私もパソコン通信をやっていましたが、電子メールの便利さには大いに感激しましたが、いかんせんマニアのコミュニティの域を出ず、むしろNiftyのフォーラムなどでのマニア同士の不思議な連帯性などは、今から思えば一般人からは少し変わった奴等だと見られていたかも知れません。その頃のSMEにも一部にNiftyメンバーがいましたが、会社のPCでは通信環境がないため、自宅からメールやフォーラムなどを利用していたようです。海外とのコミュニケーションのためやアメリカから通信販売の買い物をしている部長さんなどもいました。
私がソネットの立ち上げに関わることになったのは、堤光生氏(楽歴書第2部8回にてご紹介)の新しい事業部への参加が直接のきっかけですが、いよいよアメリカで商用インターネットの公開が始まった頃からデジタル時代の新しいビジネスとして個人的にも強い関心を持っていたからです。プロバイダー事業参入については、ソニーの中にも賛否両論があったようです。既にNiftyの100万人に及ぶパソコン通信利用者があり、新規のベンチャー企業としてはBEKKOAME NETが先行していました。なによりもネットワークのバックボーンとなる巨大な通信インフラの確保と、全国に展開するアクセスポイントについてはNTTの協力なくしては成立しません。(ソネット計画の当初は全世界での展開も視野に入っていたのですが、結果的にソニーのプロバイダー事業としては日本とアジアの一部に限られているのは、こうした巨大な投資と通信企業との幅広いアライアンスが必要だからです。)
ソネット創設者の一人、現社長の山本泉二さんは、早くから通信事業としてのプロバイダーは過当競争によって急速に通信料金が下がることを予見していました。彼は一貫してサービス・プロバイダーとしてのコンテンツ・ビジネスにこそ活路があると主張し、ソニー・グループのコンテンツ事業とのシナジーを目指していました。オークションやバンキングなどのファイナンス事業、音楽や映像の配信事業、Niftyフォーラムのようなネット・コミュニティ事業など、インターネット接続業と同時にデジタル時代のサービス業としてコンテンツ・ビジネスをソネットの重要な柱と捉えていたのです。山本社長は、ソネットをソニー株式会社の単独事業としてではなく、ソニー・ミュージックとの合弁事業として提案し、ゲーム会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメントに続く、SONY&SMEの2つめの合弁会社として設立しました。そして、その受け皿として堤さん率いるSMEマルチメディア本部が関与することになり、私が送り込まれたのです。ソネット構想については、私は早い時期から堤さんと共に山本さんの考えを伺っていました。そして、インターネットにおけるコンテンツ・ビジネスの具体的なアイディアを、アメリカでの事例などを参考にそれこそ夜も昼も考え続けていましたが、そこに浅野さんから「ポストペット」のアイディアが持ち込まれたのです。
インターネット普及の第一の「訴求点」は、プラウザーによるHP閲覧ではなく、電子メールのビジュアル化によるパソコン通信とのインターフェイスの違いだ、と直感しました。そして、その直感を確信に変えさせたもう一つの要素は、当時小学生の間で静かなプームとなっていた「たまごっち」でした。世の中で「バーチャル・ペット」という言葉が浸透し始めた頃のことです。同じ頃に、ゲームボーイの「ポケットモンスター」(ポケモン)が大ヒットとなって、品切れが続出していました。3Dグラフィックスのプレイステーションとは対極にあたる携帯型ゲームのヒットであり、任天堂の快挙です。その後、「たまごっち」は急速に大人のおもちゃにまで浸透すると共に、一気に飽和して様々な「ニセモノ」が出回って、結局アッ!という間に収束してしまいましたが、「ポケモン」はよく練られたゲーム性にコレクション・ホビーとしての姿を同時に展開して見事にキャラクター化を果たし、TVアニメから大スター「ピカチュウ」を生み出しました。ハードウェアとしての「おもちゃ」に留まった「たまごっち」とソフト・コンテンツとしての「キャラクター」に育った「ポケモン」の差、これが「ポストペット」の大きな教訓になったことは、プロジェクトのすべてのメンバーの共通の基本認識でした。
13(第二部)
ここ3回に渡って、SME/マルチメディア本部時代のゲームビジネスのお話を書いてきました。その中で、PlayStationのソフトとして、現在まで語り継がれている伝説の大作「クーロンズ・ゲート」の開発について触れましたが、この自社開発チームを編成するに当たって、一人の実力派プランナーが加わりました。前回ご紹介した「クーロンズ・ゲート」の須藤プロデューサーがスカウトしてきた人物は、あのハドソンのヒットゲーム「桃太郎伝説」の開発メンバーの一人、浅野晃一朗君です。彼を初めて紹介された時に、私は直感的に全く異質なキャラクター性を感じたのですが、それは私がそれまでに出会ってきた人々とは根本的に視点の違う発想を持っていた点です。その後数年間に渡って浅野君には様々な形でお付き合い頂く事になるのですが、何と言っても彼との最大の関わりは「ポストペット」の誕生でしょう。
メディア・アーティストとして活躍中の八谷和彦さんとその学友である元セガのデザイナー真鍋奈見江さんが発案したバーチャル・ペットとメールソフトの合体した電子メールソフト「ポストペット」のアイディアを浅野君が私に話してくれたのは95年の春頃だったと記憶しています。当時、私はSo-netの設立に参画して、SME/マルチメディア本部と出来たばかりのSo-netのコンテンツ開発部を兼任し、様々なコンテンツ開発のプロデュースに携わっていました。浅野君はSMEのゲーム開発チームの一員で、私のスタッフの一人でしたが、彼のユニークな人脈の中で「ポストペット」発案者の二人と親しいプログラマー、幸喜さんがお茶のみ話としてこのアイディアを浅野君に話したのだそうです。私はこの素晴らしいアイディアに即座に「乗って」、その場でSo-netのコンテンツとして開発することを決めました。実は本来であれば、電子メールソフトというアプリケーションの開発はSo-netというよりはSMEのドメインに属するものだったのですが、その時期のSMEではPlayStation用ゲームソフトの自社開発に乗り出したばかりのところで、人材、資金、時間のすべての面で全く余裕がなかったのです。一方、So-netのコンテンツ開発も出来たばかりの会社であり、同じように人材も資金も乏しかったのですが、テーマという点では何か画期的なアイディアが欲しい状態でした。
So-netのコンテンツ開発にアテンドされた約10名のメンバーはいずれもSONY出身者で、ソフトウェア開発という点ではほとんどが未経験者ばかりでした。SMEからグループリーダーとして出向していた保科裕氏は、ソフトビジネスの全般について幅広い経験と知識をもった人格者であり、優れたマネージャーですが、ネットワーク・ビジネスのコンテンツ・ソフトウェアを開発するという仕事については、コンピューター・テクノロジーの知識も含めて初めて体験する要素が多かったため、現場のプロデューサーとして私がSMEと兼任してチームの企画・マーケティング面のマネージャーを担当していました。「ポストペット」のアイディアは私のSo-netでのプロジェクトとして取り上げることにして、広報や宣伝のグループからも人材を集めて、コンテンツ・グループの北村道雄君をリーダーに社内チームを編成しました。保科GMと当時No.2で現場の総責任者だった山本取締役(現So-net/CEO)のお二人は、私の提案を快く理解し、当時としてはかなりの開発予算を承認して下さいました。
So-netにとっては初めてのアプリケーション開発であり、同時にネットワーク・コンテンツとしての独自のWEB SITEでのビジネス・モデルを構築するプランは発案者のメンバー3人とSo-netの優秀な若手スタッフ5名、そしてSMEの浅野君も加わってスタート。深夜に及ぶブレーンストーミングが毎週のように行われ、徐々にキャラクター・マーチャンダイジング・ビジネスへの展開を含むユニークなビジネス・プランが練られてゆきました。特に、当時のSo-netのプロバイダー加入者の特徴であった「Macユーザー」にフォーカスした導入時のマーケティングは、SONYらしいアプローチの典型的なスタイルだと思います。
次回は、「ポストペット」誕生のプロセスでの知られざるエピソードなどをご紹介しましょう。
メディア・アーティストとして活躍中の八谷和彦さんとその学友である元セガのデザイナー真鍋奈見江さんが発案したバーチャル・ペットとメールソフトの合体した電子メールソフト「ポストペット」のアイディアを浅野君が私に話してくれたのは95年の春頃だったと記憶しています。当時、私はSo-netの設立に参画して、SME/マルチメディア本部と出来たばかりのSo-netのコンテンツ開発部を兼任し、様々なコンテンツ開発のプロデュースに携わっていました。浅野君はSMEのゲーム開発チームの一員で、私のスタッフの一人でしたが、彼のユニークな人脈の中で「ポストペット」発案者の二人と親しいプログラマー、幸喜さんがお茶のみ話としてこのアイディアを浅野君に話したのだそうです。私はこの素晴らしいアイディアに即座に「乗って」、その場でSo-netのコンテンツとして開発することを決めました。実は本来であれば、電子メールソフトというアプリケーションの開発はSo-netというよりはSMEのドメインに属するものだったのですが、その時期のSMEではPlayStation用ゲームソフトの自社開発に乗り出したばかりのところで、人材、資金、時間のすべての面で全く余裕がなかったのです。一方、So-netのコンテンツ開発も出来たばかりの会社であり、同じように人材も資金も乏しかったのですが、テーマという点では何か画期的なアイディアが欲しい状態でした。
So-netのコンテンツ開発にアテンドされた約10名のメンバーはいずれもSONY出身者で、ソフトウェア開発という点ではほとんどが未経験者ばかりでした。SMEからグループリーダーとして出向していた保科裕氏は、ソフトビジネスの全般について幅広い経験と知識をもった人格者であり、優れたマネージャーですが、ネットワーク・ビジネスのコンテンツ・ソフトウェアを開発するという仕事については、コンピューター・テクノロジーの知識も含めて初めて体験する要素が多かったため、現場のプロデューサーとして私がSMEと兼任してチームの企画・マーケティング面のマネージャーを担当していました。「ポストペット」のアイディアは私のSo-netでのプロジェクトとして取り上げることにして、広報や宣伝のグループからも人材を集めて、コンテンツ・グループの北村道雄君をリーダーに社内チームを編成しました。保科GMと当時No.2で現場の総責任者だった山本取締役(現So-net/CEO)のお二人は、私の提案を快く理解し、当時としてはかなりの開発予算を承認して下さいました。
So-netにとっては初めてのアプリケーション開発であり、同時にネットワーク・コンテンツとしての独自のWEB SITEでのビジネス・モデルを構築するプランは発案者のメンバー3人とSo-netの優秀な若手スタッフ5名、そしてSMEの浅野君も加わってスタート。深夜に及ぶブレーンストーミングが毎週のように行われ、徐々にキャラクター・マーチャンダイジング・ビジネスへの展開を含むユニークなビジネス・プランが練られてゆきました。特に、当時のSo-netのプロバイダー加入者の特徴であった「Macユーザー」にフォーカスした導入時のマーケティングは、SONYらしいアプローチの典型的なスタイルだと思います。
次回は、「ポストペット」誕生のプロセスでの知られざるエピソードなどをご紹介しましょう。
12(第二部)
私と私の師匠の一人であった堤光生(ツツミ・テルオ)氏とソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)の「マルチメディア本部」を立ち上げて、本格的にゲームソフトの制作・販売に乗り出したのは1995年のことでした。当初は「プレイステーション」の発売前であり、PC、SEGA/Mega-Drive、NEC/CD-Rom2などのプラットフォームを対象にいくつかのタイトルを開発しましたが、いずれも純粋なゲームソフトというよりはSME所属アーティストの「企画物」が主でした。これらのソフトの販売を担当する営業部隊もなかったため、私と田中延尚(現So-net広告宣伝担当マネージャー)さんの二人で全国のゲーム卸店等を回ってセールスしました。なかなかまともに取り合ってくれない場面が多かったのですが、やはり既に「プレイステーション」発売の情報が行き渡っていたため、「ソニー」を名乗れば門前払いを喰うことはありませんでした。
このセールス活動の中で分かったことは、ゲームソフトの流通が実にいい加減で古い体質のものであったか、ということでした。いわゆる任天堂の「ファミコン」と「スーファミ」によって築かれた業界だけに、基本的にはオモチャ業界の流通であり、それに「ヨドバシカメラ」や「T-Zone」などの量販店が加わった流通体制でした。ソフトは基板を用いたカセット式で、ロードスピートの速さはCDに勝っていましたが、大量生産には向いていなかったため、いつも過剰な在庫か長期間の品切れという両極端のリスクをはらんだビジネスでした。しかもソフトの製造はすべて任天堂による一括受注生産であったため、ゲームメーカーは生産量や在庫コントロールの自由がなく、機動的な体制をとることは全く出来ないまま、終始任天堂のペースに合わさざるを得なかったのです。フォーマット・ライセンサーとしてのメリットを最大限に利用し、しかもリスクなしのこのビジネスモデルで任天堂は利益を貪りました。そして、「初心会」と呼ばれた任天堂支配下のゲーム卸店は、この任天堂のモデルを支え、在庫のバッファ機能と価格コントロールの機能を握って、小売店に対し「抱合せ販売」などの違法行為を繰り返していました。
ソニーは任天堂のこうした流通体制を参考に、フォーマット・ライセンサーとしての手法を踏襲しながら、いわゆる「卸店」を排除して小売店との「直接契約」による流通体制を敷きました。CDをメデイアとして製造のリードタイムを短縮し、少ない追加注文にも1週間程度で対応する生産体制を目指しました。ゲームメーカーがプレイステーションに「乗った」もう一つの大きな条件がこの生産と流通の方法だったのです。ゲームメーカーは「卸店」の思惑注文に惑わされることがなくなり、大量の在庫や長期間の品切れから開放されるようになりました。また、営業部隊をもたず開発に専念するソフト・メーカーを育てるため、小売店との直接営業を行うセールス部隊を用意して販売を一本化、生産から流通、販売、物流に到る完全一貫体制によるマーケティングを実現して、新しいソフト・メーカーの参入を促しました。その結果、プレイステーション用のゲームを開発するライセンシーであるゲームソフト・メーカーは国内だけでおよそ一年足らずで300社以上に達し、大量のソフトが供給されるようになりました。
SMEのマルチメディア本部もこの300社の中の一社として「プレステ」向けゲームソフトの開発に着手することになりました。ゲームソフトの開発費は大半が人件費です。ゲームの内容にもよりますが、平均的なソフトの制作では、10名程度のスタッフが1年を費やして一つのタイトルを完成させます。一人当りの人件費を年間で約500万円としておよそ5,000万円かかる計算です。その他に機材費や作業場所代、CD製造費、宣伝費などを加えると1タイトルの発売までに約1億円の費用が必要です。ソフトの定価を3,800円とするとゲーム会社の収入はその約50%=1,900円ですから50,000枚を販売してやっと「元」が取れることになります。50,000枚の「損益分岐点」が高いか、低いか、現在の市場ではかなり高いハードルになっていますが、当時のブームの中では余程の「クソゲー」でなければクリアできる数字でした。実際、我々が手がけたタイトルもスタートの当初は順調に売れて、そこそこの利益を生んでくれましたが、一方で有能な制作会社がこぞって自立する方向になったために制作を委託するところがどんどん少なくなって、制作費や制作期間も条件がどんどん厳しくなっていきました。結局、プロデューサーの中心であった須藤朗(現So-netモバイルコンテンツ・マネージャー)さんは自前の制作チームを編成して大作を手がけることを決断し、無名ながら有能なスタッフを集めて、「プレステ」史上でいまだに語り継がれている超大作、フル3DムービーのシミュレーションRPG「クーロンズ・ゲート」の制作に乗り出しました。総制作費約5億円の大プロジェクトは周囲の注目を集め、企画段階から大きな期待をかけられましたが、その技術的なハードルは高く、完成までに約3年の歳月をかけることになりました。その間のスタッフの情熱や努力は計り知れないほどのレベルであり、連日の徹夜作業や議論など、未知の分野で日夜格闘する姿は今でも私の眼にありありと焼き付いています。体力と知力の限界に挑戦する若者たちの究極のチームは、彼等自身にとっても、もう二度と経験することが出来ない貴重な体験だったと思います。ゲームソフト・ビジネスの領域を越えて彼らは現在、それぞれの道を歩んでいますが、そのチームの記憶は消えることはないでしょう。「クーロンズ・ゲート」での経験を糧に、その後須藤プロデューサーは「プレステ2」のゲームソフト「天誅」で世界的なヒットを生み出します。
国内以上にアメリカで成功したこのソフトで、また新たな制作チームが誕生し、彼らはアメリカを代表するゲーム・メーカー「アクレイム」社の委託を受けて独立を果たしました。「クーロンズ・ゲート」の発売後に私はSMEを離れて新たな道を模索することになりましたが、あの時の興奮と感動は決して忘れることの出来ない経験でした。と同時に、この文の中でご紹介した田中さんと須藤さんの二人の存在は私にとって、確実に次の時代が来ている事を実感させられた経験でもありました。私自身のステップアップということを強く意識するようになったのです。
このセールス活動の中で分かったことは、ゲームソフトの流通が実にいい加減で古い体質のものであったか、ということでした。いわゆる任天堂の「ファミコン」と「スーファミ」によって築かれた業界だけに、基本的にはオモチャ業界の流通であり、それに「ヨドバシカメラ」や「T-Zone」などの量販店が加わった流通体制でした。ソフトは基板を用いたカセット式で、ロードスピートの速さはCDに勝っていましたが、大量生産には向いていなかったため、いつも過剰な在庫か長期間の品切れという両極端のリスクをはらんだビジネスでした。しかもソフトの製造はすべて任天堂による一括受注生産であったため、ゲームメーカーは生産量や在庫コントロールの自由がなく、機動的な体制をとることは全く出来ないまま、終始任天堂のペースに合わさざるを得なかったのです。フォーマット・ライセンサーとしてのメリットを最大限に利用し、しかもリスクなしのこのビジネスモデルで任天堂は利益を貪りました。そして、「初心会」と呼ばれた任天堂支配下のゲーム卸店は、この任天堂のモデルを支え、在庫のバッファ機能と価格コントロールの機能を握って、小売店に対し「抱合せ販売」などの違法行為を繰り返していました。
ソニーは任天堂のこうした流通体制を参考に、フォーマット・ライセンサーとしての手法を踏襲しながら、いわゆる「卸店」を排除して小売店との「直接契約」による流通体制を敷きました。CDをメデイアとして製造のリードタイムを短縮し、少ない追加注文にも1週間程度で対応する生産体制を目指しました。ゲームメーカーがプレイステーションに「乗った」もう一つの大きな条件がこの生産と流通の方法だったのです。ゲームメーカーは「卸店」の思惑注文に惑わされることがなくなり、大量の在庫や長期間の品切れから開放されるようになりました。また、営業部隊をもたず開発に専念するソフト・メーカーを育てるため、小売店との直接営業を行うセールス部隊を用意して販売を一本化、生産から流通、販売、物流に到る完全一貫体制によるマーケティングを実現して、新しいソフト・メーカーの参入を促しました。その結果、プレイステーション用のゲームを開発するライセンシーであるゲームソフト・メーカーは国内だけでおよそ一年足らずで300社以上に達し、大量のソフトが供給されるようになりました。
SMEのマルチメディア本部もこの300社の中の一社として「プレステ」向けゲームソフトの開発に着手することになりました。ゲームソフトの開発費は大半が人件費です。ゲームの内容にもよりますが、平均的なソフトの制作では、10名程度のスタッフが1年を費やして一つのタイトルを完成させます。一人当りの人件費を年間で約500万円としておよそ5,000万円かかる計算です。その他に機材費や作業場所代、CD製造費、宣伝費などを加えると1タイトルの発売までに約1億円の費用が必要です。ソフトの定価を3,800円とするとゲーム会社の収入はその約50%=1,900円ですから50,000枚を販売してやっと「元」が取れることになります。50,000枚の「損益分岐点」が高いか、低いか、現在の市場ではかなり高いハードルになっていますが、当時のブームの中では余程の「クソゲー」でなければクリアできる数字でした。実際、我々が手がけたタイトルもスタートの当初は順調に売れて、そこそこの利益を生んでくれましたが、一方で有能な制作会社がこぞって自立する方向になったために制作を委託するところがどんどん少なくなって、制作費や制作期間も条件がどんどん厳しくなっていきました。結局、プロデューサーの中心であった須藤朗(現So-netモバイルコンテンツ・マネージャー)さんは自前の制作チームを編成して大作を手がけることを決断し、無名ながら有能なスタッフを集めて、「プレステ」史上でいまだに語り継がれている超大作、フル3DムービーのシミュレーションRPG「クーロンズ・ゲート」の制作に乗り出しました。総制作費約5億円の大プロジェクトは周囲の注目を集め、企画段階から大きな期待をかけられましたが、その技術的なハードルは高く、完成までに約3年の歳月をかけることになりました。その間のスタッフの情熱や努力は計り知れないほどのレベルであり、連日の徹夜作業や議論など、未知の分野で日夜格闘する姿は今でも私の眼にありありと焼き付いています。体力と知力の限界に挑戦する若者たちの究極のチームは、彼等自身にとっても、もう二度と経験することが出来ない貴重な体験だったと思います。ゲームソフト・ビジネスの領域を越えて彼らは現在、それぞれの道を歩んでいますが、そのチームの記憶は消えることはないでしょう。「クーロンズ・ゲート」での経験を糧に、その後須藤プロデューサーは「プレステ2」のゲームソフト「天誅」で世界的なヒットを生み出します。
国内以上にアメリカで成功したこのソフトで、また新たな制作チームが誕生し、彼らはアメリカを代表するゲーム・メーカー「アクレイム」社の委託を受けて独立を果たしました。「クーロンズ・ゲート」の発売後に私はSMEを離れて新たな道を模索することになりましたが、あの時の興奮と感動は決して忘れることの出来ない経験でした。と同時に、この文の中でご紹介した田中さんと須藤さんの二人の存在は私にとって、確実に次の時代が来ている事を実感させられた経験でもありました。私自身のステップアップということを強く意識するようになったのです。
11(第二部)
「プレステ」の世界的な大ヒットは、一般家庭へ3DCGの世界を広めたこととテレビ・ゲーム(欧米ではビデオ・ゲームと呼びます)をより幅広い世代に浸透させたことの大きな二つの「変化」をもたらしました。一般家庭へのパソコンの普及のプロセスを横目に見ながら、このゲーム機はデジタル時代の「シンボル」のようにテレビと一体となって一気に普及しました。「プレイステーション」というネーミングのコンセプトは、既にIBMが1970年代から使い始めていたオフィス用の端末機器の総称「ワークステーション」に対するアンチテーゼです。パーソナルな「家庭」というフィールドでは、コンピュータは「ワークステーション」からの延長線上で「パーソナル・コンピュータ」としてダウンサイジングを進めてきましたが、任天堂はゲーム側からのアプローチにコンピュータを特化させて、「パーソナル・コンピュータ」に対して「ファミリー・コンピュータ」というネーミングでテレビ・ゲーム機を全世界のリビングに広めようとしました。その価格は玩具としては破格の高額でしたが、パソコン本体との比較で見れば1/8であり、しかもテレビをディスプレイとして利用するため、トータルで考えればわずか1/15の価格でした。この「ファミコン」(欧米ではNINTENDOと呼ばれていました)の登場した1984年頃の家庭用のテレビは29型ステレオ・テレビが発売された時期で、衛星放送が始まり、地上波放送でもステレオの番組が増えてきた時期にあたります。ところが、「コンピュータ」の世界ではまだ音の処理は稚拙で、「ファミコン」もモノラル仕様でした。リビングの中心に置かれ始めた真新しい大型テレビに対して「ファミコン」はどこか幼稚で貧弱な印象があり、また基本的には長時間の一人遊びの道具としての性格が強いことから、いつの頃からか「ファミコン」は買い替えられた古いモノラル・テレビに繋がれ子供部屋に移されていったのです。「ファミコン」の「ディスク・システム」が登場するとますます小学生の遊び道具となってゆきます。300円で新しいソフトに書き換えが出来るというシステムは子供たちの遊びとして適当な値段であり、「おもちゃ」としての性格が強くなってゆきます。
それでも「ファミコン」に夢中な青年たちはゲームマニアとして成長し、ゲームセンターとRPG系ゲームにはまってゆくと共に「おたく」と称される人種に色分けされ始め、高校生以上のゲームプレイヤーたちは次第に「ファミコン」に飽き足らず、パソコンに興味を移し始めました。SEGAのファンが次第に増えていったのもほぼ同じ頃で、NECの「PCエンジン」と共にゲームマニア・ライクな16ビット仕様のSEGA「メガドライブ」はゲーム好き青年の支持を集めて、特にアメリカでは単年度では「ファミコン」を抜く売上を記録し、いよいよ任天堂の独占時代が崩れ始めてきました。そこに満を持して登場したのが任天堂の16ビット機「スーパーファミコン」(欧米ではSuper Nintendo=NESと呼ばれます)です。「ファミコン」の2倍はあろうかという大型カセットのソフトで楽しむ擬似3Dのグラフィクスは衝撃的な美しさで音もステレオ、そして再びリビングの大型テレビに繋がれる存在に返り咲きました。一方でゲームの画質が向上するに伴ってソフトのデータ量も飛躍的に増え始め、この頃からメモリーとROMの容量が大きな課題として浮かび上がってきました。SEGAとNECはCD-ROMをソフトメディアに採用し、16ビット型のCD仕様機を投入、任天堂に対抗しましたが、時代のニーズはさらにその先のリアル3Dの実現に向かっていました。
任天堂とSonyが急速に近づいたのはこの頃です。任天堂は32ビット型次世代機にCD-ROMを採用することをほぼ決めてはいましたが、CD-ROMのデータ読み込み速度の遅さを懸念していました。一方Sonyは音楽用CDの普及に成功しましたが、CDプレイヤーの次の戦略商品として高速回転のCD-ROMプレイヤーに大きな市場を見ていました。おりしもパソコンの標準仕様としてCD-ROMプレイヤーが搭載され始め、NECとSonyはそのトップ・ブランドとして覇権を争っていましたが、Sonyは自社のパソコンでは完全に失敗し、あくまでCD-ROMパーツメーカーとしての拡販に集中していました。しかしAppleコンピュータへの完全導入は果たしましたが、その他のパソコン・メーカーではNEC、松下、さらに韓国、台湾などのパーツメーカーに押され気味で激しい価格競争に巻き込まれていました。その大きな突破口として任天堂の新型ゲーム機への高速回転のCD-ROMプレイヤー採用に向けて共同開発の提携を目論んだのです。
しかし、任天堂とSonyの提携はあっけなく終焉を迎えます。「スーパーファミコン」は全世界で健闘し、SEGAの「メガドライブ」と戦っていましたが、SEGAのCD-ROM搭載機「メガCD」の投入がなされた後でも大きな落ち込みを見せなかったのです。特に米国では、一時ナンバーワンの地位をSEGAに奪われましたが、すぐにトップに返り咲き「スーパーマリオ」はハリウッドの映画になる程のヒットキャラクターに成長していました。アーケード・ゲームではSEGAは大きな成功をしていましたが、家庭用では任天堂がリードしているという状況だったのです。真相は未だに謎ですが、任天堂は突然、Sonyとの提携を解消すると発表します。この発表の仕方を巡って、後々まで尾を引く確執が生まれるのですが、米国で発表されたこの報道で、米国Sonyの株価が一時急落しました。一方、米国任天堂の株価はむしろ上昇したのです。市場がこの提携をどのように見ていたのか、この時点ではっきりしたのです。
それでも「ファミコン」に夢中な青年たちはゲームマニアとして成長し、ゲームセンターとRPG系ゲームにはまってゆくと共に「おたく」と称される人種に色分けされ始め、高校生以上のゲームプレイヤーたちは次第に「ファミコン」に飽き足らず、パソコンに興味を移し始めました。SEGAのファンが次第に増えていったのもほぼ同じ頃で、NECの「PCエンジン」と共にゲームマニア・ライクな16ビット仕様のSEGA「メガドライブ」はゲーム好き青年の支持を集めて、特にアメリカでは単年度では「ファミコン」を抜く売上を記録し、いよいよ任天堂の独占時代が崩れ始めてきました。そこに満を持して登場したのが任天堂の16ビット機「スーパーファミコン」(欧米ではSuper Nintendo=NESと呼ばれます)です。「ファミコン」の2倍はあろうかという大型カセットのソフトで楽しむ擬似3Dのグラフィクスは衝撃的な美しさで音もステレオ、そして再びリビングの大型テレビに繋がれる存在に返り咲きました。一方でゲームの画質が向上するに伴ってソフトのデータ量も飛躍的に増え始め、この頃からメモリーとROMの容量が大きな課題として浮かび上がってきました。SEGAとNECはCD-ROMをソフトメディアに採用し、16ビット型のCD仕様機を投入、任天堂に対抗しましたが、時代のニーズはさらにその先のリアル3Dの実現に向かっていました。
任天堂とSonyが急速に近づいたのはこの頃です。任天堂は32ビット型次世代機にCD-ROMを採用することをほぼ決めてはいましたが、CD-ROMのデータ読み込み速度の遅さを懸念していました。一方Sonyは音楽用CDの普及に成功しましたが、CDプレイヤーの次の戦略商品として高速回転のCD-ROMプレイヤーに大きな市場を見ていました。おりしもパソコンの標準仕様としてCD-ROMプレイヤーが搭載され始め、NECとSonyはそのトップ・ブランドとして覇権を争っていましたが、Sonyは自社のパソコンでは完全に失敗し、あくまでCD-ROMパーツメーカーとしての拡販に集中していました。しかしAppleコンピュータへの完全導入は果たしましたが、その他のパソコン・メーカーではNEC、松下、さらに韓国、台湾などのパーツメーカーに押され気味で激しい価格競争に巻き込まれていました。その大きな突破口として任天堂の新型ゲーム機への高速回転のCD-ROMプレイヤー採用に向けて共同開発の提携を目論んだのです。
しかし、任天堂とSonyの提携はあっけなく終焉を迎えます。「スーパーファミコン」は全世界で健闘し、SEGAの「メガドライブ」と戦っていましたが、SEGAのCD-ROM搭載機「メガCD」の投入がなされた後でも大きな落ち込みを見せなかったのです。特に米国では、一時ナンバーワンの地位をSEGAに奪われましたが、すぐにトップに返り咲き「スーパーマリオ」はハリウッドの映画になる程のヒットキャラクターに成長していました。アーケード・ゲームではSEGAは大きな成功をしていましたが、家庭用では任天堂がリードしているという状況だったのです。真相は未だに謎ですが、任天堂は突然、Sonyとの提携を解消すると発表します。この発表の仕方を巡って、後々まで尾を引く確執が生まれるのですが、米国で発表されたこの報道で、米国Sonyの株価が一時急落しました。一方、米国任天堂の株価はむしろ上昇したのです。市場がこの提携をどのように見ていたのか、この時点ではっきりしたのです。
10(第二部)
今回から3回にわたって、ゲームビジネスのお話を書こうと思います。私のキャリアにとっては大きくは4回目の業界変化の体験であり、デジタル時代への転換という大きな社会変化に伴って、激しく動いている企業や市場のビビッドな様子をドキュメントしながら、現在の私にとって最大の試練でもあった時期を振り返ってみます。
32ビット型家庭用ゲーム機の登場は、16ビット型時代とは全く違う社会を生み出しました。ハードウェアの性能の面では、3Dグラフィックス表現の飛躍的な向上によってCGアニメーションが一般家庭レベルに普及したことが最大の特徴でしょう。また、Sonyの「プレイステーション」、SEGAの「サターン」、Panasonicの「REAL」、NECの「FX」の4機種がほぼ同時期に発売され、市場を大いに活性化させると共に激しい競争を展開しましたが、この4機種はいずれも「CD-ROM」をメディアとした点で、デシタル記録技術の第1期黄金時代を象徴しています。
それまでゲーム業界世界最大のメーカーとして君臨してきた任天堂は、この部分では独自路線を貫きます。一時はSonyのデジタル技術との連携を模索していながら、共同開発プロジェクトの中断と独自路線への転換を選択した背景には、したたかな京都流商人感覚と長年「子供&玩具市場」をベースに培ってきた独特な市場把握の感覚があり、「娯楽」としてのゲームと「エンタテインメント」としてのゲームの違いとでも言うか、まさに独自の嗅覚を持っているように感じられます。のちに「Gameboy」によって「ポケモン」のメガヒットを飛ばしますが、山内社長の説く「ゲーム性」を最も端的に表した成功事例だと言えるでしょう。任天堂は、32ビットをジャンプして一気に64ビット型の、しかもカセット式ゲーム機「Nintendo64」を発売しますが、それは「32ビットゲーム機戦争」と言われた1995年のクリスマス商戦からおよそ1年後のことでした。こうした一貫した独自路線によって、今でも世界No.1ゲームメーカーとしての地位を保ち続けている事自体が驚異的であり、一企業として見た場合も財務、資産、事業性においてずば抜けた超優良企業だということができます。規模の比較はできませんが、今年で創業以来103年を数える老舗の現在の姿は、世界最高企業と呼ばれる米国GE社をも彷彿とさせる趣があります。
一方、常に任天堂の後塵を拝していたとはいえ日本のゲームビジネスを世界に広げた新興ベンチャーの雄、SEGAはご承知のように現在一歩一歩自立再建の道を歩んでいますが、この10年間にSEGAの辿った道筋はまさに天国から地獄のような浮沈の連続でした。Sonyのゲーム業界への参入のきっかけを作ったのは他ならぬ任天堂でしたが、その直接かつ最大の影響を被ったのはSEGAでした。「プレステ」と「サターン」の戦いに集約した「32ビット戦争」は結論として「プレステ」の勝利に終わりましたが、その最大の勝因は市場へのアプローチの違いだったと思います。任天堂はSonyとの共同開発プロジェクトの進行の過程で、この基本的な「差」を察知して自らの進むべき路線を再確認したに違いありません。その結果、Sonyとの提携を破棄し32ビット型ゲーム機から一時的にせよ撤退して、CDの使用も意図的に避ける形で次なる機会をしたたかに待つ戦略を取ったのです。一方SEGAの側から見ると、既に16ビット型時代から培ってきたCDを使って3D表現を強化した32ビット機の導入は任天堂に先んずるためのかねてからのシナリオだったのですが、いざ蓋を開けてみると戦いの相手はいつのまにか任天堂ではなく、Sonyになっていた、という印象だったでしょう。
この頃、私はSMEのニューメディア本部に所属し、従来の路線を大幅に転換してゲームソフト制作に乗り出していました。同じソニーグループとしてのメリットを追求しながらも一方でサードパーティのソフトハウスとしての立場を建前として、Panasonic/REAL対応の「3DO/OSソフトライセンス」や「SEGA/SATURNソフトライセンサー」の契約も結びながら市場動向を注視していました。また、同時にSonyの新しいPCハードのプロジェクト{後のVAIOグループ}との交流も続け、技術系人材の派遣なども受けていました。さらに、IBM、マイクロソフト、アスキー、シリコングラフィクス、Adobe、Apple、等の後のIT系有力企業とのアライアンスも続けていました。しかし、ニューメディアやマルチメディアの分野だけでエンタテーメント系ソフトウェア・ビジネスの採算性を求めるのはたいへんに困難で、その最大の障害はPCの価格であり、使い方の難しさであることは現在でも本質的には変わりありません。逆説的に言えば、それは家庭用ゲーム機の最大のメリットであり、手軽にデジタル時代の新しい娯楽を一般大衆に普及させるという目的にもっとも適したハードであったのです。
ここで改めて「プレステ」が登場するまでのゲーム業界を見直してみると、任天堂とSEGAのスタンスの違いが浮き彫りになってきます。SEGAの基本的な考え方はマニア的なゲーム市場を一般大衆化することにありました。それは見方を変えるとゲームビジネスの市民権のようなものを求めていたとも考えられます。「ゲームセンターの楽しさを家庭で好きな時間に好きなだけ」というコピーはSEGAの大ヒットソフト「バーチャファイター」サターン版の頃のものですが、ここにSEGAの目指していた方向がはっきりと示されています。一方任天堂は、ゲームセンター用ソフトと家庭用{それもどちらかといえば小学生をコアターゲットに設定した}ソフトのマーケットは少し性格が違うことをよく理解していたことが窺えます。特に、後の「ポケモン」や当時のファミコン最大のヒット作「ドラクエ」と「FF」の2大RPGの存在がそれを裏付けています。結果として、Sonyの参入によってゲーム機は一気に家電製品として普及し、当時の一般流行商品となってしまったことで、SEGAの目指していた初期の目的は達成されたのですが、皮肉なことにその家電化のプロセスの中でSonyのブランド力とマーケティング力に圧倒される形で戦争はSEGAの敗北という形で終結してしまいました。今でもマニア的なゲーマーの間ではSEGAは根強い支持を受け続けています。また、ゲーム制作者の間ではハードウェアと開発用ソフトウェアの両面で「プレステ」よりも「サターン」を高く評価する人が少なくありません。「32ビットゲーム機戦争は世界の市場を変え、社会を変え、文化をも変えてしまいました。デジタル時代の扉を開き、人々の生活に大きな影響を与えながら、そのビジネスの飛躍的拡大の過程でSonyとSEGAの二つの企業が正反対の成果を得ることになったことは競争社会の凄まじさを象徴的に示す事実です。
32ビット型家庭用ゲーム機の登場は、16ビット型時代とは全く違う社会を生み出しました。ハードウェアの性能の面では、3Dグラフィックス表現の飛躍的な向上によってCGアニメーションが一般家庭レベルに普及したことが最大の特徴でしょう。また、Sonyの「プレイステーション」、SEGAの「サターン」、Panasonicの「REAL」、NECの「FX」の4機種がほぼ同時期に発売され、市場を大いに活性化させると共に激しい競争を展開しましたが、この4機種はいずれも「CD-ROM」をメディアとした点で、デシタル記録技術の第1期黄金時代を象徴しています。
それまでゲーム業界世界最大のメーカーとして君臨してきた任天堂は、この部分では独自路線を貫きます。一時はSonyのデジタル技術との連携を模索していながら、共同開発プロジェクトの中断と独自路線への転換を選択した背景には、したたかな京都流商人感覚と長年「子供&玩具市場」をベースに培ってきた独特な市場把握の感覚があり、「娯楽」としてのゲームと「エンタテインメント」としてのゲームの違いとでも言うか、まさに独自の嗅覚を持っているように感じられます。のちに「Gameboy」によって「ポケモン」のメガヒットを飛ばしますが、山内社長の説く「ゲーム性」を最も端的に表した成功事例だと言えるでしょう。任天堂は、32ビットをジャンプして一気に64ビット型の、しかもカセット式ゲーム機「Nintendo64」を発売しますが、それは「32ビットゲーム機戦争」と言われた1995年のクリスマス商戦からおよそ1年後のことでした。こうした一貫した独自路線によって、今でも世界No.1ゲームメーカーとしての地位を保ち続けている事自体が驚異的であり、一企業として見た場合も財務、資産、事業性においてずば抜けた超優良企業だということができます。規模の比較はできませんが、今年で創業以来103年を数える老舗の現在の姿は、世界最高企業と呼ばれる米国GE社をも彷彿とさせる趣があります。
一方、常に任天堂の後塵を拝していたとはいえ日本のゲームビジネスを世界に広げた新興ベンチャーの雄、SEGAはご承知のように現在一歩一歩自立再建の道を歩んでいますが、この10年間にSEGAの辿った道筋はまさに天国から地獄のような浮沈の連続でした。Sonyのゲーム業界への参入のきっかけを作ったのは他ならぬ任天堂でしたが、その直接かつ最大の影響を被ったのはSEGAでした。「プレステ」と「サターン」の戦いに集約した「32ビット戦争」は結論として「プレステ」の勝利に終わりましたが、その最大の勝因は市場へのアプローチの違いだったと思います。任天堂はSonyとの共同開発プロジェクトの進行の過程で、この基本的な「差」を察知して自らの進むべき路線を再確認したに違いありません。その結果、Sonyとの提携を破棄し32ビット型ゲーム機から一時的にせよ撤退して、CDの使用も意図的に避ける形で次なる機会をしたたかに待つ戦略を取ったのです。一方SEGAの側から見ると、既に16ビット型時代から培ってきたCDを使って3D表現を強化した32ビット機の導入は任天堂に先んずるためのかねてからのシナリオだったのですが、いざ蓋を開けてみると戦いの相手はいつのまにか任天堂ではなく、Sonyになっていた、という印象だったでしょう。
この頃、私はSMEのニューメディア本部に所属し、従来の路線を大幅に転換してゲームソフト制作に乗り出していました。同じソニーグループとしてのメリットを追求しながらも一方でサードパーティのソフトハウスとしての立場を建前として、Panasonic/REAL対応の「3DO/OSソフトライセンス」や「SEGA/SATURNソフトライセンサー」の契約も結びながら市場動向を注視していました。また、同時にSonyの新しいPCハードのプロジェクト{後のVAIOグループ}との交流も続け、技術系人材の派遣なども受けていました。さらに、IBM、マイクロソフト、アスキー、シリコングラフィクス、Adobe、Apple、等の後のIT系有力企業とのアライアンスも続けていました。しかし、ニューメディアやマルチメディアの分野だけでエンタテーメント系ソフトウェア・ビジネスの採算性を求めるのはたいへんに困難で、その最大の障害はPCの価格であり、使い方の難しさであることは現在でも本質的には変わりありません。逆説的に言えば、それは家庭用ゲーム機の最大のメリットであり、手軽にデジタル時代の新しい娯楽を一般大衆に普及させるという目的にもっとも適したハードであったのです。
ここで改めて「プレステ」が登場するまでのゲーム業界を見直してみると、任天堂とSEGAのスタンスの違いが浮き彫りになってきます。SEGAの基本的な考え方はマニア的なゲーム市場を一般大衆化することにありました。それは見方を変えるとゲームビジネスの市民権のようなものを求めていたとも考えられます。「ゲームセンターの楽しさを家庭で好きな時間に好きなだけ」というコピーはSEGAの大ヒットソフト「バーチャファイター」サターン版の頃のものですが、ここにSEGAの目指していた方向がはっきりと示されています。一方任天堂は、ゲームセンター用ソフトと家庭用{それもどちらかといえば小学生をコアターゲットに設定した}ソフトのマーケットは少し性格が違うことをよく理解していたことが窺えます。特に、後の「ポケモン」や当時のファミコン最大のヒット作「ドラクエ」と「FF」の2大RPGの存在がそれを裏付けています。結果として、Sonyの参入によってゲーム機は一気に家電製品として普及し、当時の一般流行商品となってしまったことで、SEGAの目指していた初期の目的は達成されたのですが、皮肉なことにその家電化のプロセスの中でSonyのブランド力とマーケティング力に圧倒される形で戦争はSEGAの敗北という形で終結してしまいました。今でもマニア的なゲーマーの間ではSEGAは根強い支持を受け続けています。また、ゲーム制作者の間ではハードウェアと開発用ソフトウェアの両面で「プレステ」よりも「サターン」を高く評価する人が少なくありません。「32ビットゲーム機戦争は世界の市場を変え、社会を変え、文化をも変えてしまいました。デジタル時代の扉を開き、人々の生活に大きな影響を与えながら、そのビジネスの飛躍的拡大の過程でSonyとSEGAの二つの企業が正反対の成果を得ることになったことは競争社会の凄まじさを象徴的に示す事実です。
9(第二部)
私の師匠と言えるお二人、丸山茂雄氏(元SME代表取締役)と堤光生氏(元SME取締役)はかつてはEPICソニーの邦楽と洋楽のそれぞれの中心としてライバル関係にあり、その後デジタル時代に入ってからも「ニューメディア」ビジネスの二つの部門リーダーとして各々独自の路線を指向して、SMEにとっての新しいビジネス・モデルの構築に尽力されました。既にご紹介したように、丸山さんはPlaystationの生みの親の一人として大きな成果を上げられ、また堤さんはSo-netの立ち上げを通じてネット時代のコンテンツビジネスの先鞭を付けました。
娯楽業界→芸能界→音楽業界→レコード業界というビジネスドメインにおける邦楽系と洋楽系に専門化/特化して、お二人はそれぞれの業界における有名人として日本を代表するプロデューサーになられました。しかし、お二人ともその立場に甘んじることなく常に新しいフィールドに関心を払い、娯楽市場全般に対する興味を抱きながら、共にソフトウェア・クリエーターの視点でいつも時代と世の中を深く見つめておられました。カルチャーとしてのエンターテインメントとそれを取り巻く様々なクリエイテイブな活動には、音楽、映像、デザイン、シナリオ、演出といった各専門分野のアーテイストやクリエーターの多様なアイデアが総合化されています。古くはワーグナーの目指したオペラ(彼は「歌劇」から「楽劇」という形の総合芸術化を目指した)、現代ではハリウッド映画やRPGゲーム、テーマパークなど、建築家やインテリアデザイナーなどの造形作家も加わって、テクノロジーやエンジニアリングの領域とも深い関係を持ちながら進化を続けています。娯楽産業全体の規模は放送や通信などのメディアも含めると米国で約25兆円、EU全体で13兆円、日本では5兆円と言われていますが、さらにファッション・デザイナーや建築家、広告業界などを加えた全世界のクリエーターの数は一体どの位になるのでしょうか。プロスポーツの娯楽化も急速に進んでいますし、キャラクタービジネスなども加えれば市場規模はさらに広がるでしょう。
こうした娯楽産業に特化したビジネス・モデルの典型的な企業がソニーであり、エレクトロニクスとソフト・コンテンツの連動によってハードウェアとサプライ系消費財(記録メディアや電池など)、そしてエンターテインメント・ソフトウェアの総合メーカーとして、グローバルな巨大企業に成長しました。
80年代初頭のハリウッドの映画会社コロンビア・ピクチュアーズ、そしてCBSのレコード部門の買収についてはアメリカ国内でかなりの批判的な論調も見られましたが、一般的には高いブランド・イメージによって大衆や社会全般での定着にはさして時間はかかりませんでした。むしろ株式市場などでは評価が高まり、ソニー全体としては真にグローバルな会社として広く認められることになったと考えられます。とりわけデジタル時代への変革のプロセスの中では、その中心的な存在としてIBM、Microsoftなどと共に新興勢力(AOLやCisco Systemsなど)と上手く歩調を合わせて成長してきた経緯があります。日本の他の家電メーカーとの違いは、とりわけソフトウェアの部分で顕著であり、またエンタテインメント・ビジネスを機軸とする点でもビジネス・モデルに大きな違いがあり、例えばNECや松下との違いはこうした部分で明らかでしょう。
そのエンタテインメント・ソフトウェア・ビジネスの担い手として、ソニーのハードウェアとのシナジーを積極的に推進したのが元ソニー会長の大賀典雄さんです。大賀さんの強烈な個性と卓越したビジネス・センスは、井深さんと盛田さんによって築き上げられたソニーをさらに大きなものに育て上げました。そして、その大賀さんのソニー・ミュージックにおける愛弟子とも言えるのが丸山さんと堤さんなのです。ソニー・ミュージックでの大賀さんの忠実な大番頭役は元ソニー・ミュージック会長の小沢敏男さんでしたが、小沢さんはクリエィティブなセンスを持った新しいタイプの経営者の育成に力を注がれました。丸山さんと堤さんはその代表的な存在で、EPICソニーでのライバル関係から始まって、お二人ともに90年代の後半にSMEの取締役として経営の中核にまで出世されました。そして、ソニー・グループにとっての現在の重要なビジネスに育ったプレイステーションとソネットに結びついているのです。
私自身は、主に堤さんの部下として10数年を共に過ごさせて頂き、クリエイティブ・ワークとビジネスの結びつきの基本と言えるコミュニケーション・マーケティングを徹底的に叩きこまれました。特にメディアやクリエーターとの付き合い方については、言葉遣いや立ち居振舞いに至るまで事あるごとに細かい注意や指導を受けましたし、外国人との接し方や国際ビジネスの進め方についても豊富な経験に基づいた実戦的なノウハウを色々と教えて頂きました。特に、ミュージシャンやアーティストとの付き合い方やマネージャーやディレクターとのネゴシエーションの方法などは、現場に同席して様々なケース・スタディをさせて頂きました。堤さん自身がかつてはレコーディング・ミュージシャンであったこともあり、業界のしきたりから業界用語に至るまで、日本とアメリカの違いを踏まえながら日米の両業界について幅広い知識と見識をもっておられましたので、極めて現場主義的な立場からの具体的な指示、指導が今でも強く印象に残っています。そして、心から音楽を愛し、また新しいものを好み、テクノロジーへの飽くなき興味を持ち続けておられ、それは現在でも変わることがありません。あらゆる意味で率直で、少年のようなピュアな気持ちの持ち主として、まさにクリエーターの心を全く失わずにおられることは、ソフトウェア・ビジネスマンとしての極意と言えるかも知れません。
娯楽業界→芸能界→音楽業界→レコード業界というビジネスドメインにおける邦楽系と洋楽系に専門化/特化して、お二人はそれぞれの業界における有名人として日本を代表するプロデューサーになられました。しかし、お二人ともその立場に甘んじることなく常に新しいフィールドに関心を払い、娯楽市場全般に対する興味を抱きながら、共にソフトウェア・クリエーターの視点でいつも時代と世の中を深く見つめておられました。カルチャーとしてのエンターテインメントとそれを取り巻く様々なクリエイテイブな活動には、音楽、映像、デザイン、シナリオ、演出といった各専門分野のアーテイストやクリエーターの多様なアイデアが総合化されています。古くはワーグナーの目指したオペラ(彼は「歌劇」から「楽劇」という形の総合芸術化を目指した)、現代ではハリウッド映画やRPGゲーム、テーマパークなど、建築家やインテリアデザイナーなどの造形作家も加わって、テクノロジーやエンジニアリングの領域とも深い関係を持ちながら進化を続けています。娯楽産業全体の規模は放送や通信などのメディアも含めると米国で約25兆円、EU全体で13兆円、日本では5兆円と言われていますが、さらにファッション・デザイナーや建築家、広告業界などを加えた全世界のクリエーターの数は一体どの位になるのでしょうか。プロスポーツの娯楽化も急速に進んでいますし、キャラクタービジネスなども加えれば市場規模はさらに広がるでしょう。
こうした娯楽産業に特化したビジネス・モデルの典型的な企業がソニーであり、エレクトロニクスとソフト・コンテンツの連動によってハードウェアとサプライ系消費財(記録メディアや電池など)、そしてエンターテインメント・ソフトウェアの総合メーカーとして、グローバルな巨大企業に成長しました。
80年代初頭のハリウッドの映画会社コロンビア・ピクチュアーズ、そしてCBSのレコード部門の買収についてはアメリカ国内でかなりの批判的な論調も見られましたが、一般的には高いブランド・イメージによって大衆や社会全般での定着にはさして時間はかかりませんでした。むしろ株式市場などでは評価が高まり、ソニー全体としては真にグローバルな会社として広く認められることになったと考えられます。とりわけデジタル時代への変革のプロセスの中では、その中心的な存在としてIBM、Microsoftなどと共に新興勢力(AOLやCisco Systemsなど)と上手く歩調を合わせて成長してきた経緯があります。日本の他の家電メーカーとの違いは、とりわけソフトウェアの部分で顕著であり、またエンタテインメント・ビジネスを機軸とする点でもビジネス・モデルに大きな違いがあり、例えばNECや松下との違いはこうした部分で明らかでしょう。
そのエンタテインメント・ソフトウェア・ビジネスの担い手として、ソニーのハードウェアとのシナジーを積極的に推進したのが元ソニー会長の大賀典雄さんです。大賀さんの強烈な個性と卓越したビジネス・センスは、井深さんと盛田さんによって築き上げられたソニーをさらに大きなものに育て上げました。そして、その大賀さんのソニー・ミュージックにおける愛弟子とも言えるのが丸山さんと堤さんなのです。ソニー・ミュージックでの大賀さんの忠実な大番頭役は元ソニー・ミュージック会長の小沢敏男さんでしたが、小沢さんはクリエィティブなセンスを持った新しいタイプの経営者の育成に力を注がれました。丸山さんと堤さんはその代表的な存在で、EPICソニーでのライバル関係から始まって、お二人ともに90年代の後半にSMEの取締役として経営の中核にまで出世されました。そして、ソニー・グループにとっての現在の重要なビジネスに育ったプレイステーションとソネットに結びついているのです。
私自身は、主に堤さんの部下として10数年を共に過ごさせて頂き、クリエイティブ・ワークとビジネスの結びつきの基本と言えるコミュニケーション・マーケティングを徹底的に叩きこまれました。特にメディアやクリエーターとの付き合い方については、言葉遣いや立ち居振舞いに至るまで事あるごとに細かい注意や指導を受けましたし、外国人との接し方や国際ビジネスの進め方についても豊富な経験に基づいた実戦的なノウハウを色々と教えて頂きました。特に、ミュージシャンやアーティストとの付き合い方やマネージャーやディレクターとのネゴシエーションの方法などは、現場に同席して様々なケース・スタディをさせて頂きました。堤さん自身がかつてはレコーディング・ミュージシャンであったこともあり、業界のしきたりから業界用語に至るまで、日本とアメリカの違いを踏まえながら日米の両業界について幅広い知識と見識をもっておられましたので、極めて現場主義的な立場からの具体的な指示、指導が今でも強く印象に残っています。そして、心から音楽を愛し、また新しいものを好み、テクノロジーへの飽くなき興味を持ち続けておられ、それは現在でも変わることがありません。あらゆる意味で率直で、少年のようなピュアな気持ちの持ち主として、まさにクリエーターの心を全く失わずにおられることは、ソフトウェア・ビジネスマンとしての極意と言えるかも知れません。
8(第二部)
ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)は、92年頃から業績に不安な要素が見え始めていました。バブル崩壊という日本経済全体の停滞と同時に、国際的な音楽業界の再編成、国内音楽業界の競争環境変化、米国の好景気によって始まったITの急速な発展とそれに伴う娯楽市場の変化、等々・・・。こうした市場環境の変化に対して、SMEの二人のクリエイティブなリーダーである丸山茂雄氏(前SME社長)と堤光生氏(前SME取締役)はそれぞれに異なったアプローチであったとは言え、デジタル技術を背景とする新しいエンタテインメント市場の将来に強い関心と意欲を燃やしていました。現在、改めてお二人のアプローチを比べてみると、ビジネス・ライクな丸山さんとコンセプチュアル・ワークの堤さんという「対比」ができるかも知れません。
私は幸運にもこのお二人に仕える立場でおよそ15年間もご一緒に仕事をさせて頂きましたが、部下の立場から見て、お二人は各々ほぼ「対極」に位置する判断やアプローチをされるケースが多く、正直な所、その調整には骨を折りました。お二人に共通する特性は「直感主義」であり、共にクリエイティブな仕事をするプロの素質として絶対不可欠な卓越した「創造力」をもっておられます。と同時にテーマに対するどん欲な取組み姿勢はビジネスマンとして、また人間として常に前向きであり、情熱的であることは言うまでもありません。
従って、ある局面では真っ向から対立することもあり、EPICソニーの草創期以来、お二人は邦楽部門と洋楽部門の各々のリーダーとしていわば「宿命のライバル」だったのです。そして、このライバル関係がEPICソニーという会社を短期間に一流のレコード会社として成功させた原動力であったことは確かでしょう。
私は初めは堤さんの部下としてEPICソニーの洋楽部門で約10年間鍛えられたのですが、その後EPICソニーを離れてソニー・ミュージックコミュニケーションズ(SMC)の立ち上げに加わった後、4年振りに再び堤さんの始められる新しい事業部に参加することになりました。この時、当時のSMEの松尾社長に呼ばれ、「堤君の新しいチャレンジを是非成功させてやってくれ」と異例とも言える直々の指示を頂きました。
一方、既にこの時期に丸山さんはSMEにおけるデジタル・エンタテインメントの先駆けとも言える新事業をスタートさせ、任天堂の「ファミコン」向けゲームソフトの制作を始めていました。当時EPICソニーの所属アーティストであった所ジョージや小室哲哉のオリジナル・グループTMネットワーク、またCBSソニーの所属アーティストですがデーモン小暮率いる聖飢魔IIなどのゲームが発売されました。丸山さんはキャラクター性の強いアーティストにゲームという新しいメディアを与えて、表現とビジネスの両面で新たなチャンスを模索していたのです。また、この事業によってSMEの中にゲーム制作やマーケティングの新しい人材が育ち始めて、後のソニーコンピュータエンタテインメント(SCE)の中核になってゆきます。
堤さんの新事業部は全く別のアプローチを考えていました。「堤流」で言うなら「ファミコン」は「おもちゃ」であり、本当の意味でのデジタル・エンタテインメントは「PC」によって実現されると考えていたのです。堤さんにとってはデジタル技術を使った新しい表現の革命こそがミュージシャンやアーティストに新しい表現とビジネス・チャンスをもたらすという信念がありました。また、それまでの音楽ビジネスが取り込むことの出来なかった新しい表現者やクリエーターの発掘にも強い関心を持っていました。世界に先駆けて「デジタル・エンタテインメント」という「表現」を最初に使い出したのは、この堤さんの新事業部だと思います。プロジェクトチームとして発足した堤さんの「ニューメディア室」は約1年間の調査・研究期間を経て、私の参加と同時に「本部」に昇格して本格的にビジネスに乗り出したのは93年のことです。
丸山さんのグループもまた93年に新しい局面に入っていました。ソニーと任天堂はCD-ROMを使った32ビット型次世代ゲーム機の開発を進めていたのですが、任天堂との決裂によって話はご破算になりかけていました。ソニー側で指揮をとっていたのが久多良木健さん(現SCE社長)であり、丸山さんは久多良木さんと共に ソニー製ゲーム機による業界参入を考え始めていました。ハードとソフトの両輪が噛み合ってこそのゲームビジネスであり、丸山さんのグループは「ファミコン」ゲームソフト制作での実績を背景にソニー製新型ゲーム機用の次世代ゲームソフトの開発に乗り出したのです。ゲーム業界からの人材発掘も進め、既にCD-ROMを使う32ビット型次世代ゲーム機の開発を宣言していたセガ、NEC、そしてソニーと決別して32ビット型カセットタイプゲーム機に心変えした任天堂の3社に対抗して、いよいよソニーの参入が発表されようとしていました。まさに「プレイステーション」前夜といった時期です。時を同じくして、ソニーの宿敵とも言える松下はCD-ROMを使う32ビット型家庭用次世代ハードのOSとして米国3DO社と契約、こちらはテレビとコントローラーを使う家庭用マルチメディア機という位置付けで当時のパソコンの性能の50倍の表現力をもつという「3D」エンジンを搭載した新型機として大々的なキャンペーンを仕掛けようとしていました。そしてさらに、PCのOSをリードするマイクロソフトはWindows95の発売を控え、その中核的な新機能としてのインターネットはアメリカの情報ハイウエイ構想の中核技術として急速に普及し始めようとしていました。新しいメディアと新しいハード、そして新しいOSと新しいソウトウェア、デジタル技術が日常の生活に急速に浸透し、新しい社会の到来を予感させる華々しい時代が始まる直前のムードは、アメリカの好景気を背景としてパプル崩壊後の日本経済の立ち直りのまさに最大のきっかけになるかのような希望に溢れたものでした。
私は幸運にもこのお二人に仕える立場でおよそ15年間もご一緒に仕事をさせて頂きましたが、部下の立場から見て、お二人は各々ほぼ「対極」に位置する判断やアプローチをされるケースが多く、正直な所、その調整には骨を折りました。お二人に共通する特性は「直感主義」であり、共にクリエイティブな仕事をするプロの素質として絶対不可欠な卓越した「創造力」をもっておられます。と同時にテーマに対するどん欲な取組み姿勢はビジネスマンとして、また人間として常に前向きであり、情熱的であることは言うまでもありません。
従って、ある局面では真っ向から対立することもあり、EPICソニーの草創期以来、お二人は邦楽部門と洋楽部門の各々のリーダーとしていわば「宿命のライバル」だったのです。そして、このライバル関係がEPICソニーという会社を短期間に一流のレコード会社として成功させた原動力であったことは確かでしょう。
私は初めは堤さんの部下としてEPICソニーの洋楽部門で約10年間鍛えられたのですが、その後EPICソニーを離れてソニー・ミュージックコミュニケーションズ(SMC)の立ち上げに加わった後、4年振りに再び堤さんの始められる新しい事業部に参加することになりました。この時、当時のSMEの松尾社長に呼ばれ、「堤君の新しいチャレンジを是非成功させてやってくれ」と異例とも言える直々の指示を頂きました。
一方、既にこの時期に丸山さんはSMEにおけるデジタル・エンタテインメントの先駆けとも言える新事業をスタートさせ、任天堂の「ファミコン」向けゲームソフトの制作を始めていました。当時EPICソニーの所属アーティストであった所ジョージや小室哲哉のオリジナル・グループTMネットワーク、またCBSソニーの所属アーティストですがデーモン小暮率いる聖飢魔IIなどのゲームが発売されました。丸山さんはキャラクター性の強いアーティストにゲームという新しいメディアを与えて、表現とビジネスの両面で新たなチャンスを模索していたのです。また、この事業によってSMEの中にゲーム制作やマーケティングの新しい人材が育ち始めて、後のソニーコンピュータエンタテインメント(SCE)の中核になってゆきます。
堤さんの新事業部は全く別のアプローチを考えていました。「堤流」で言うなら「ファミコン」は「おもちゃ」であり、本当の意味でのデジタル・エンタテインメントは「PC」によって実現されると考えていたのです。堤さんにとってはデジタル技術を使った新しい表現の革命こそがミュージシャンやアーティストに新しい表現とビジネス・チャンスをもたらすという信念がありました。また、それまでの音楽ビジネスが取り込むことの出来なかった新しい表現者やクリエーターの発掘にも強い関心を持っていました。世界に先駆けて「デジタル・エンタテインメント」という「表現」を最初に使い出したのは、この堤さんの新事業部だと思います。プロジェクトチームとして発足した堤さんの「ニューメディア室」は約1年間の調査・研究期間を経て、私の参加と同時に「本部」に昇格して本格的にビジネスに乗り出したのは93年のことです。
丸山さんのグループもまた93年に新しい局面に入っていました。ソニーと任天堂はCD-ROMを使った32ビット型次世代ゲーム機の開発を進めていたのですが、任天堂との決裂によって話はご破算になりかけていました。ソニー側で指揮をとっていたのが久多良木健さん(現SCE社長)であり、丸山さんは久多良木さんと共に ソニー製ゲーム機による業界参入を考え始めていました。ハードとソフトの両輪が噛み合ってこそのゲームビジネスであり、丸山さんのグループは「ファミコン」ゲームソフト制作での実績を背景にソニー製新型ゲーム機用の次世代ゲームソフトの開発に乗り出したのです。ゲーム業界からの人材発掘も進め、既にCD-ROMを使う32ビット型次世代ゲーム機の開発を宣言していたセガ、NEC、そしてソニーと決別して32ビット型カセットタイプゲーム機に心変えした任天堂の3社に対抗して、いよいよソニーの参入が発表されようとしていました。まさに「プレイステーション」前夜といった時期です。時を同じくして、ソニーの宿敵とも言える松下はCD-ROMを使う32ビット型家庭用次世代ハードのOSとして米国3DO社と契約、こちらはテレビとコントローラーを使う家庭用マルチメディア機という位置付けで当時のパソコンの性能の50倍の表現力をもつという「3D」エンジンを搭載した新型機として大々的なキャンペーンを仕掛けようとしていました。そしてさらに、PCのOSをリードするマイクロソフトはWindows95の発売を控え、その中核的な新機能としてのインターネットはアメリカの情報ハイウエイ構想の中核技術として急速に普及し始めようとしていました。新しいメディアと新しいハード、そして新しいOSと新しいソウトウェア、デジタル技術が日常の生活に急速に浸透し、新しい社会の到来を予感させる華々しい時代が始まる直前のムードは、アメリカの好景気を背景としてパプル崩壊後の日本経済の立ち直りのまさに最大のきっかけになるかのような希望に溢れたものでした。
5(第二部)
この原稿を書いている時間帯のTVのニュース番組では、イチローと新庄のニュース、サッカーの小野と稲本の話題、そして水泳世界選手権の各国選手の活躍が報道されています。ほんの数週間前に、2008年のオリンピック北京開催の決定報道があり、その中で、日本の各メディアは落選した大阪の誘致活動を巡る分析記事を掲載しましたが、その論調の中には、国際的な規模でスポーツを巡る大きなビジネス環境の変化が起こっていることが指摘されていました。そして、その数日後にはIOC会長の交代、丸山茂樹の米国プロ・ツア-での優勝、中田英寿のイタリアセリエAでのチーム移籍、と言ったようにスポーツ新聞のトップニュースはここ数年の中でも、特に2001年になって以来、ダイナミックに様変わりしているといって良いでしょう。
前回ご紹介した「アライ・スキー・リゾート」プロジェクトの計画段階から現在に至るビジネス上の「結果」について、こうした国際的な「スポーツ・エンタテインメント・ビジネス」の大きな変化が関与していることは疑いがありません。アメリカを中心として発達してきたプロ・スポーツのビジネス・モデルがあらゆるスポーツにプロ化の道を開き、さらにオリンピックの変質を促した「冷戦の終結」と共に一気に加速したことによって、日本のスポーツ界にも大きな変化をもたらしています。それは、日本のプロ・スポーツの歴史、すなわち「野球と相撲」という極端に異質な表ジャンルに、外人=悪役をベースとした「ボクシングとレスリング」という格闘技の裏ジャンルを 混在させた形で発展してきた一種異常な構造が完全に書きかえられたことを表わしています。これは、音楽業界を代表とする芸能界の構造変化と全く同質なもので、「興行」と呼ばれる「見世物商売」と勝者を当てる「賭博商売」という特殊な利権ビジネスが「エンタテインメント・ビジネス」というサービス業として、真に表の商売に生まれ変わったということでしょう。そして、その発展を促した2つの大きなファクターはテクノロジーの発展とマーケティングの進歩だといえます。
まずテクノロジーの効果について考えてみましょう。一口にテクノロジーと言っても様々な分野がありますが、最大の効用をもたらしたのはやはり「スポーツ医学」と「科学的トレーニング」だと思います。筋肉増強剤やドーピングの対象となる様な薬剤の問題もありますが、怪我や故障の治療技術や競技に適した筋肉の鍛錬法など、スポーツに特化したメディカル・ノウハウの研究開発の進歩は目覚しいものがあります。専門家の増加はプレイヤーをサポートするチームとして発達し、彼らの存在価値に対する経済的な評価が高まったことも大きな要因です。冷戦後には、特に東欧圏の優秀なドクターやコーチ、トレイナーが世界のレベルアップに貢献しており、冷戦時代に多額の国家予算で研究開発を続けていた東欧諸国のノウハウが国際市場に流通したことによって、特にウィンタースポーツや水泳、体操、陸上などの分野で世界的なレベルアップとプレイヤーのプロ化の流れが進んでいます。
このプレイヤーのプロ化の流れは、マーケティングの進歩の効果と言うことが出来ます。特に、スポーツ用品のメジャー化はそのシンボリックな傾向であり、中でもウェアとシューズは「スポーツ・ファッション」としてカジュアルウェアのメインストリームにまで成長しました。そのノウハウは、アメリカのプロ・ゴルフが発祥であり、プレイヤーブランドからスタートしたゴルフウェアとゴルフ用品が世界の中年男性のメジャーファッションになったように、ナイキやアディダスが世界のカジュアル・ウエア・ブランドとして巨大なビジネスを成功させています。世界のランキング・プレイヤーはプロ、アマを問わずこうしたスポーツ用品企業のスホンサードを受けており、さらにテクノロジーとの関係では様々な樹脂、繊維、金属などの素材開発やスポーツ飲料のような新分野の開拓に貢献しています。
メディアにとっては「スポーツ・エンタテインメント」はそもそも重要なコンテンツでしたが、オリンピック以外の国際競技イベントについても、スポンサーのグローバル化によってプログラムのバリエーションが増加し、アメリカのプロスポーツ発達のノウハウがリアルタイム配信技術の発達と共に世界のメディア地図を書き換えています。米ESPNチャンネルの急成長はCNN同様、TV局のビジネスモデルを大きく変えました。
このように改めて述べるまでもなく、「スポーツ・エンタテインメント・ビジネス」の急激な世界的変化とライフスタイルへの大きな影響は、人類の根源的なテーマである「生命と肉体」の「謎」に対する究極的な興味であり、その原理を解析しようとする遺伝子工学の急速な発達と無関係ではありません。それは「健康と環境」という地球的課題に対する関心と全く同じ次元のテーマであり、最早「見世物商売」や「賭博商売」という「興行」の背景にあった娯楽の欲求心理とは完全に異なったレベルに入ってきているということでしょう。「リゾート」や「観光」の欲求心理も同様に変化しており、自然への畏れと憧れ、遺跡や史跡の価値見なおし、異民族や異文化への関心などは情報のリアルタイム化に伴って強まっており、不景気風吹き荒れる日本で海外旅行者が益々増えていることに如実に現れていると思います。
盛田英夫氏との「アライ・スキー・リゾート」プロジェクトの仕事を通して私が体験したことの最大の意味は、自然に対する人間の関わりの問題を真剣に考えたことであり、具体的には環境の問題や健康の問題に対するマーケティング上の勉強を通じて、新しい時代の商品開発や市場開発について、それまでとは全く異なった観点から考え始めたことです。結果として、その後の数年間、私はITブームの到来によってマルチメディア・ビジネスにより深く関わることになったのですが、この「アライ・スキー・リゾート」プロジェクトと共にもう一件の重要なプロジェクトはその後のおよそ10年の間に、ITテクノロジーの勉強を絡めながら、私の中で一つの新しいテーマに集約して行くことになります。
次回は現在の私に繋がる、その「もう一件のプロジェクト」について書きたいと思います。
前回ご紹介した「アライ・スキー・リゾート」プロジェクトの計画段階から現在に至るビジネス上の「結果」について、こうした国際的な「スポーツ・エンタテインメント・ビジネス」の大きな変化が関与していることは疑いがありません。アメリカを中心として発達してきたプロ・スポーツのビジネス・モデルがあらゆるスポーツにプロ化の道を開き、さらにオリンピックの変質を促した「冷戦の終結」と共に一気に加速したことによって、日本のスポーツ界にも大きな変化をもたらしています。それは、日本のプロ・スポーツの歴史、すなわち「野球と相撲」という極端に異質な表ジャンルに、外人=悪役をベースとした「ボクシングとレスリング」という格闘技の裏ジャンルを 混在させた形で発展してきた一種異常な構造が完全に書きかえられたことを表わしています。これは、音楽業界を代表とする芸能界の構造変化と全く同質なもので、「興行」と呼ばれる「見世物商売」と勝者を当てる「賭博商売」という特殊な利権ビジネスが「エンタテインメント・ビジネス」というサービス業として、真に表の商売に生まれ変わったということでしょう。そして、その発展を促した2つの大きなファクターはテクノロジーの発展とマーケティングの進歩だといえます。
まずテクノロジーの効果について考えてみましょう。一口にテクノロジーと言っても様々な分野がありますが、最大の効用をもたらしたのはやはり「スポーツ医学」と「科学的トレーニング」だと思います。筋肉増強剤やドーピングの対象となる様な薬剤の問題もありますが、怪我や故障の治療技術や競技に適した筋肉の鍛錬法など、スポーツに特化したメディカル・ノウハウの研究開発の進歩は目覚しいものがあります。専門家の増加はプレイヤーをサポートするチームとして発達し、彼らの存在価値に対する経済的な評価が高まったことも大きな要因です。冷戦後には、特に東欧圏の優秀なドクターやコーチ、トレイナーが世界のレベルアップに貢献しており、冷戦時代に多額の国家予算で研究開発を続けていた東欧諸国のノウハウが国際市場に流通したことによって、特にウィンタースポーツや水泳、体操、陸上などの分野で世界的なレベルアップとプレイヤーのプロ化の流れが進んでいます。
このプレイヤーのプロ化の流れは、マーケティングの進歩の効果と言うことが出来ます。特に、スポーツ用品のメジャー化はそのシンボリックな傾向であり、中でもウェアとシューズは「スポーツ・ファッション」としてカジュアルウェアのメインストリームにまで成長しました。そのノウハウは、アメリカのプロ・ゴルフが発祥であり、プレイヤーブランドからスタートしたゴルフウェアとゴルフ用品が世界の中年男性のメジャーファッションになったように、ナイキやアディダスが世界のカジュアル・ウエア・ブランドとして巨大なビジネスを成功させています。世界のランキング・プレイヤーはプロ、アマを問わずこうしたスポーツ用品企業のスホンサードを受けており、さらにテクノロジーとの関係では様々な樹脂、繊維、金属などの素材開発やスポーツ飲料のような新分野の開拓に貢献しています。
メディアにとっては「スポーツ・エンタテインメント」はそもそも重要なコンテンツでしたが、オリンピック以外の国際競技イベントについても、スポンサーのグローバル化によってプログラムのバリエーションが増加し、アメリカのプロスポーツ発達のノウハウがリアルタイム配信技術の発達と共に世界のメディア地図を書き換えています。米ESPNチャンネルの急成長はCNN同様、TV局のビジネスモデルを大きく変えました。
このように改めて述べるまでもなく、「スポーツ・エンタテインメント・ビジネス」の急激な世界的変化とライフスタイルへの大きな影響は、人類の根源的なテーマである「生命と肉体」の「謎」に対する究極的な興味であり、その原理を解析しようとする遺伝子工学の急速な発達と無関係ではありません。それは「健康と環境」という地球的課題に対する関心と全く同じ次元のテーマであり、最早「見世物商売」や「賭博商売」という「興行」の背景にあった娯楽の欲求心理とは完全に異なったレベルに入ってきているということでしょう。「リゾート」や「観光」の欲求心理も同様に変化しており、自然への畏れと憧れ、遺跡や史跡の価値見なおし、異民族や異文化への関心などは情報のリアルタイム化に伴って強まっており、不景気風吹き荒れる日本で海外旅行者が益々増えていることに如実に現れていると思います。
盛田英夫氏との「アライ・スキー・リゾート」プロジェクトの仕事を通して私が体験したことの最大の意味は、自然に対する人間の関わりの問題を真剣に考えたことであり、具体的には環境の問題や健康の問題に対するマーケティング上の勉強を通じて、新しい時代の商品開発や市場開発について、それまでとは全く異なった観点から考え始めたことです。結果として、その後の数年間、私はITブームの到来によってマルチメディア・ビジネスにより深く関わることになったのですが、この「アライ・スキー・リゾート」プロジェクトと共にもう一件の重要なプロジェクトはその後のおよそ10年の間に、ITテクノロジーの勉強を絡めながら、私の中で一つの新しいテーマに集約して行くことになります。
次回は現在の私に繋がる、その「もう一件のプロジェクト」について書きたいと思います。
7(第二部)
先月は諸般の事情があり勝手ながら休載させて頂きました。ここで改めてお詫び致します。
その間に、米国での同時多発テロ事件が発生し、ニューヨークに在住している私の友人、知人の中にも身の周りの方で不幸にも被害に遭われた方がいるという知らせなどが入りました。とても現実のこととは思えないショッキングな事件でした。また、この事件を契機として国際経済、国内経済の両面で消費意識を中心として、心理的にはかなり広範囲にマイナス・マインドが広がったように感じます。
日本のビジネスとマーケットは10年以上に及ぶ景気低迷期の中で未だに出口の見えない状態にあります。各企業のオペレーションは合理化やリストラといった緊縮型のコスト削減を中心として、収益確保のための努力を続けていますが、一方で次の成長要因を見出すための研究開発投資の資金が不足していることもあって、マーケットでは限られた需要に対して同業他社との競合市場を巡るサバイバル戦の様相が色濃くなっています。これは言いかえれば、各企業の体力勝負、弱肉強食の熾烈な戦いが激化していることであり、今後数年の間に、より一層劇的な業界の再編成が起こり、企業の倒産、合従連衡、資本関係の変化などが急ピッチで進むと思います。
先週、私の上司が中国を視察してきましたが、「世界の工場」になりつつあると言われる中国南西部の工場地帯の現場に、たいへん大きな驚きと脅威を感じてこられたようです。経済のグローバル化は急速に進んでいて、一方情報のグローバル化によって、先のテロ事件などの国際事件が全世界に同時にインパクトを与える時代、すなわち地球全体が一つのシステムとして動くような時代へ進んでいることは、考えてみれば想像を遥かに凌ぐレベルで世界が難しい時代に向かって進んでいることを実感させます。民族、宗教、文化の違いを越える共通の価値観や原則を全世界の人が共通に認識し、同じレベルで生きる道を探ることはとてつもない努力と忍耐、また理解力を必要とするでしょう。情報技術革命と言われるテクノロジーがもたらした大きなメリットと、それによって急速に顕在化してきたアレルギー的な副作用。私はIT革命の現状を、特効薬とその副作用の関係のように捉え始めています。つまり、新薬の臨床試験のプロセスのように、IT革命は現在、まさに地球全体で臨床試験を続けている段階にあると考えているのです。
インターネットはそもそも世界の知識人と軍事関係者にとっての自主的なコミュニケーション・ネットワークとして構築されたものです。電話や手紙のデメリット(時差、通信コスト、一対一コミュニケーション、…)を克服して、安く、リアルタイムに、同報多方通信を実現する手段として放送や出版をも越える方法と考えられました。このインターネットの民生化/商用化に対応して、90年代に入ると共にアメリカの未曾有の好景気を支える新産業の主役として、情報通信技術産業は一躍脚光を浴びることになりました。いわゆるインターネット革命の世界的なキャンペーンが始まったのです。
当時、私はSMC(現ソニーミュージックコミュニケーションズ)の一員として、プロモーション&PRのエージェント・ビジネスにおけるマーケティングとコンサルティングを担当していました。前回まで色々とご紹介してきたように、私自身にとっては様々なビジネス、様々な業界の方々と出会うことの出来た有意義な5年間だったのです。同じ頃、会社にとって、本業のミュージック・ビジネスは芸能界や音楽業界の枠を越えて、広く国際的なエンタテインメント・ビジネスとして成長して行く大きな転機に差しかかっている時期でした。とりわけコンピュータ・ゲーム・ビジネスの急速な発展は、ソニーグループにとっては大きな脅威であり、また家電業界やメディア&ソフトウェア業界にとっても同様の恐るべきビックビジネスに育ってきていました。
ソニーミュージックグループの中で、こうしたニューメディア・ビジネスの将来を真剣に展望していたのはかつての私のEPICソニー時代の二人の上司でした。後のプレイステーションのソニーコンピュータエンタテインメント(SCE)の創設者の一人で、ソニーミュージックの代表も勤められた丸山茂雄さんとソネットでおなじみのソニーコミュニケーションネットワーク(SCN)の創業に尽力された堤光生さんのお二人です。丸山さんはソニーの久多良木健さん(現SCE代表CEO)とともに任天堂との提携の決裂を契機として、32bitゲームハードウェアを開発し業界に参入することを推進した立役者であり、一方堤さんは早くからインターネット時代を予見して、新しいソフトウェア流通のシステムを展望しておられ、ソニーの山本泉二さん(現SCN代表CEO)とご一緒にインターネットプロバイダービジネスを立ち上げられました。幸運にも私はこのお二人の部下としてSMEのニューメディア系新規ビジネスに早い時期からご一緒に仕事をさせて頂く機会を与えられました。二つの個性は際立っており、ビジネスマンとして、男として、また人間として、素晴らしく豊かで創造性に富んだ生き方を目の当たりにして、本当にたくさんの事を教えて頂きました。まさに、私にとっての人生の師匠であり、模範でもある方々なのです。
その間に、米国での同時多発テロ事件が発生し、ニューヨークに在住している私の友人、知人の中にも身の周りの方で不幸にも被害に遭われた方がいるという知らせなどが入りました。とても現実のこととは思えないショッキングな事件でした。また、この事件を契機として国際経済、国内経済の両面で消費意識を中心として、心理的にはかなり広範囲にマイナス・マインドが広がったように感じます。
日本のビジネスとマーケットは10年以上に及ぶ景気低迷期の中で未だに出口の見えない状態にあります。各企業のオペレーションは合理化やリストラといった緊縮型のコスト削減を中心として、収益確保のための努力を続けていますが、一方で次の成長要因を見出すための研究開発投資の資金が不足していることもあって、マーケットでは限られた需要に対して同業他社との競合市場を巡るサバイバル戦の様相が色濃くなっています。これは言いかえれば、各企業の体力勝負、弱肉強食の熾烈な戦いが激化していることであり、今後数年の間に、より一層劇的な業界の再編成が起こり、企業の倒産、合従連衡、資本関係の変化などが急ピッチで進むと思います。
先週、私の上司が中国を視察してきましたが、「世界の工場」になりつつあると言われる中国南西部の工場地帯の現場に、たいへん大きな驚きと脅威を感じてこられたようです。経済のグローバル化は急速に進んでいて、一方情報のグローバル化によって、先のテロ事件などの国際事件が全世界に同時にインパクトを与える時代、すなわち地球全体が一つのシステムとして動くような時代へ進んでいることは、考えてみれば想像を遥かに凌ぐレベルで世界が難しい時代に向かって進んでいることを実感させます。民族、宗教、文化の違いを越える共通の価値観や原則を全世界の人が共通に認識し、同じレベルで生きる道を探ることはとてつもない努力と忍耐、また理解力を必要とするでしょう。情報技術革命と言われるテクノロジーがもたらした大きなメリットと、それによって急速に顕在化してきたアレルギー的な副作用。私はIT革命の現状を、特効薬とその副作用の関係のように捉え始めています。つまり、新薬の臨床試験のプロセスのように、IT革命は現在、まさに地球全体で臨床試験を続けている段階にあると考えているのです。
インターネットはそもそも世界の知識人と軍事関係者にとっての自主的なコミュニケーション・ネットワークとして構築されたものです。電話や手紙のデメリット(時差、通信コスト、一対一コミュニケーション、…)を克服して、安く、リアルタイムに、同報多方通信を実現する手段として放送や出版をも越える方法と考えられました。このインターネットの民生化/商用化に対応して、90年代に入ると共にアメリカの未曾有の好景気を支える新産業の主役として、情報通信技術産業は一躍脚光を浴びることになりました。いわゆるインターネット革命の世界的なキャンペーンが始まったのです。
当時、私はSMC(現ソニーミュージックコミュニケーションズ)の一員として、プロモーション&PRのエージェント・ビジネスにおけるマーケティングとコンサルティングを担当していました。前回まで色々とご紹介してきたように、私自身にとっては様々なビジネス、様々な業界の方々と出会うことの出来た有意義な5年間だったのです。同じ頃、会社にとって、本業のミュージック・ビジネスは芸能界や音楽業界の枠を越えて、広く国際的なエンタテインメント・ビジネスとして成長して行く大きな転機に差しかかっている時期でした。とりわけコンピュータ・ゲーム・ビジネスの急速な発展は、ソニーグループにとっては大きな脅威であり、また家電業界やメディア&ソフトウェア業界にとっても同様の恐るべきビックビジネスに育ってきていました。
ソニーミュージックグループの中で、こうしたニューメディア・ビジネスの将来を真剣に展望していたのはかつての私のEPICソニー時代の二人の上司でした。後のプレイステーションのソニーコンピュータエンタテインメント(SCE)の創設者の一人で、ソニーミュージックの代表も勤められた丸山茂雄さんとソネットでおなじみのソニーコミュニケーションネットワーク(SCN)の創業に尽力された堤光生さんのお二人です。丸山さんはソニーの久多良木健さん(現SCE代表CEO)とともに任天堂との提携の決裂を契機として、32bitゲームハードウェアを開発し業界に参入することを推進した立役者であり、一方堤さんは早くからインターネット時代を予見して、新しいソフトウェア流通のシステムを展望しておられ、ソニーの山本泉二さん(現SCN代表CEO)とご一緒にインターネットプロバイダービジネスを立ち上げられました。幸運にも私はこのお二人の部下としてSMEのニューメディア系新規ビジネスに早い時期からご一緒に仕事をさせて頂く機会を与えられました。二つの個性は際立っており、ビジネスマンとして、男として、また人間として、素晴らしく豊かで創造性に富んだ生き方を目の当たりにして、本当にたくさんの事を教えて頂きました。まさに、私にとっての人生の師匠であり、模範でもある方々なのです。
6(第二部)
「アライ・スキーリゾート」プロジェクトと併行して、CBSソニーコミュニケーションズ(現ソニーミュージック・コミュニケーションズ)での大きな仕事は、当時新規に開拓したクライアントであったプラス株式会社とのプロジェクトです。プラス株式会社は、コクヨやオカムラ等と並んでオフィス用品の総合メーカーで、文房具や事務機、デスクなどのオフィス家具を販売するブランドメーカーとしては業界第4位に位置する中堅企業です。この楽歴書のはじめの頃に、私がCBSソニーに入社した当初、キャラクター・マーチャンダイジング会社のソニークリエイティブ・プロダクツに配属され、いわゆる「キャラクター文具」のマーケティングを担当していたことを書きましたが、当時の文具業界でもコクヨ、ライオンなどのオフィス用品のメーカーに比べてプラスは少し毛色の違うユニークな会社でした。「チームデミ」というヒット商品を持ち、各地の文具見本市でも何度か出展側の一社として展示ブースを見る機会がありました。そのプラスとの縁は、図らずも私のEPICソニーでのキャリアにきっかけがありました。EPICソニーは、その成り立ちの背景としてCBSソニーからスピンアウトした新しいレコード会社として独自のカラーとイメージを打ち出していました。その一つの表現として、オフィスのインテリア・デザインや家具の選定などにもCBSソニーとは違うアプローチを目指して、従来の方法とは異なるプレゼンテーション・コンペによる業者選定を行っていました。CBSソニーは創立時からオカムラのデスクや什器を使っていましたが、EPICソニーでは独自にオカムラの他にコクヨ、イトーキ等を加えてコンペを実施していたのです。私は、プラス株式会社との取引のきっかけ作りのために、EPICソニーの新しいオフィス開設の話を聞いて、当時のEPICソニーのトップだった丸山茂雄専務にプラスのコンペへの参加承認をお願いに行ったのです。このコンペの結果はプラスが委員会メンバーからトップの支持を獲得して、僅差の2位だったオカムラと共に主にデザイン性を重視する受付周りやミーティング・コーナー、デスクなどが採用されました。後になって知ったのですが、このコンペはプラスにとってはソニーグループの会社とのほぼ初めての取引ということでたいへんに大きなプロジェクトだったそうです。
このコンペの頃、つまり1986年当時は日本の高度成長期の最後のピークに向かっていた時代であり、都市開発に伴う高層ビルの着工件数が増え新しいオフィス需要も高まっていて、オフィスインテリアもモダンなデザインを積極的に取り入れ始めていました。プラスには「オフィス環境研究所」が設けられており、コクヨやオカムラにも同様の研究機関があって、アメリカで発達してきたファシリティ・マネジメントというコンセプトを中心として、新しいオフィスのあり方に関する学問的なアプローチも進んできていました。仕事をしやすくする快適なオフィスを目指して、企業イメージのアップや福利厚生としての意味、また合理的で効率的なスペースの使い方という側面も加味されて、現代用語で言えばオフィス用品メーカーにとっては「B to B」ビジネスの新たな展開が図られてきた時代でもあったのです。
プラスは当時、業界第4位、ないし第5位のメーカーでシェアにして5~6%程度の中堅企業でしたが、紙製品・文房具とオフィス家具を取り扱うオフィス用品総合商社の色合いが強いメーカーでした。最も近い業態の他社はコクヨ、ライオン、内田洋行の3社、オカムラ、イトーキ、はスチール家具メーカーというイメージが強く現在でも文具系は扱っていません。他に、名古屋地区のITO、大阪のナイキ、他に「テプラ」のキングジム、「物置」の稲葉製作所などの競合メーカーがあります。家具に限って言えば、現在も主流のスチールデスクのブランドメーカーは国内に10社余り存在し、その中で自社工場を持ち自社生産を行っているメーカーが6社、プラスは85年当時はまだ生産部門を持たない会社でした。
そのプラスが新たに群馬県前橋市に壮大な家具の生産拠点を設ける計画を打ち上げ、まず事務用チェアの自主開発と生産を始める事を知りました。この事務用チェア「アメノミクス・シリーズ」の販促用パンフレット制作の仕事がCBSソニーコミュニケーションズにとっての最初の提案だったのです。こちらは東急エージェンシーとのコンペに勝って採用となり、これをきっかけに家具製品開発のメンバーと知り合うようになりました。プラスへの営業活動の傍ら、新しい家具の生産拠点建設プロジェクト「プランランド構想」の内容を尋ね、そこで生産される予定のオフィスシステム家具のコンセプトなども詳しく聞くことが出来ました。「オフィス環境研究所」の研究員の方々、製品開発部門、そして当時家具ビジネスの本部長を勤めておられた副社長の今泉公二氏との出会いに繋がりました。私は単にパンフレット制作の仕事だけでなく、総合的なマーケティング・コンサルタントとして新しいシステム家具の製品開発から販売支援に至るトータルなプランニングに参加させてもらうべく、社内にプロジェクト・チームを編成し本格的な代理店業務の獲得を目指しました。CBSソニーコミュニケーションズにとってはソニーの関連会社以外で初めての大型クライアントとして総合代理店業務を任される存在になろうとしたのです。プラスには既にメディアAEとして電通、セールス・プロモーション担当として東急エージェンシー、さらに旭通信社とPRエージェント2社が取引していました。我々は新規参入であり、また代理店としての実績も乏しく人材も不足していましたが、プロジェクトのメンバーは新しいチャレンジに意欲的に取り組んで、プラスにとって最大規模の大型投資案件に関する製品開発、マーケティング、プロモーションの業務を担当することが出来ました。
その背景にEPICソニーとの取引があったことは大きな材料でした。プラスにとって、我々は逆の立場で重要な新規クライアントであり、CBSソニーコミュニケーションズが他社を排して「プラスランド」プロジェクトの仕事を獲得できたのは、ビジネス上のバーターが機能していたからです。その意味でも営業的な関係の構築と相互の真剣な仕事への取り組みの姿勢が大切であり、そこに企業同士、人間同士の信頼関係を築く基本があります。私は現在、プラス株式会社の一員として仕事をしています。先に述べた今泉公二氏との10年来のお付き合いの結果として、家具ビジネスの新たな展開のために「プラスランド」の第3次計画のスタートに参加しています。新たな家具製品の工場は2001年12月に完成し、12年前に開発されたオフィスシステム家具の次世代の製品を生み出すべく着々と準備を進めています。時代は12年前とは一変して、日本の企業は大きな構造変革の荒波の中にあり、ビジネス環境も大きく変わりました。OAからITへ、オフィス環境も変化し働き方も変わります。サテライト型オフィスやSOHOなどの新しい仕事場の登場で、仕事のための家具のあり方や使われ方も大きく変化するに違いありません。12年前のプロジェクト以来、私自身はまさにITビジネスの中心的な業界に身を置き、デジタル・ビジネスの最先端で活動していました。その間、私の関わったオフィスシステム家具「リンクス」はプラスの主力商品に育ちましたが、12年余りの時間を経て一つの転機を迎えているようです。そして私は改めて、この12年間の経験を生かして、新たなワーキング・ファニチャーを構想しようと思っています。
このコンペの頃、つまり1986年当時は日本の高度成長期の最後のピークに向かっていた時代であり、都市開発に伴う高層ビルの着工件数が増え新しいオフィス需要も高まっていて、オフィスインテリアもモダンなデザインを積極的に取り入れ始めていました。プラスには「オフィス環境研究所」が設けられており、コクヨやオカムラにも同様の研究機関があって、アメリカで発達してきたファシリティ・マネジメントというコンセプトを中心として、新しいオフィスのあり方に関する学問的なアプローチも進んできていました。仕事をしやすくする快適なオフィスを目指して、企業イメージのアップや福利厚生としての意味、また合理的で効率的なスペースの使い方という側面も加味されて、現代用語で言えばオフィス用品メーカーにとっては「B to B」ビジネスの新たな展開が図られてきた時代でもあったのです。
プラスは当時、業界第4位、ないし第5位のメーカーでシェアにして5~6%程度の中堅企業でしたが、紙製品・文房具とオフィス家具を取り扱うオフィス用品総合商社の色合いが強いメーカーでした。最も近い業態の他社はコクヨ、ライオン、内田洋行の3社、オカムラ、イトーキ、はスチール家具メーカーというイメージが強く現在でも文具系は扱っていません。他に、名古屋地区のITO、大阪のナイキ、他に「テプラ」のキングジム、「物置」の稲葉製作所などの競合メーカーがあります。家具に限って言えば、現在も主流のスチールデスクのブランドメーカーは国内に10社余り存在し、その中で自社工場を持ち自社生産を行っているメーカーが6社、プラスは85年当時はまだ生産部門を持たない会社でした。
そのプラスが新たに群馬県前橋市に壮大な家具の生産拠点を設ける計画を打ち上げ、まず事務用チェアの自主開発と生産を始める事を知りました。この事務用チェア「アメノミクス・シリーズ」の販促用パンフレット制作の仕事がCBSソニーコミュニケーションズにとっての最初の提案だったのです。こちらは東急エージェンシーとのコンペに勝って採用となり、これをきっかけに家具製品開発のメンバーと知り合うようになりました。プラスへの営業活動の傍ら、新しい家具の生産拠点建設プロジェクト「プランランド構想」の内容を尋ね、そこで生産される予定のオフィスシステム家具のコンセプトなども詳しく聞くことが出来ました。「オフィス環境研究所」の研究員の方々、製品開発部門、そして当時家具ビジネスの本部長を勤めておられた副社長の今泉公二氏との出会いに繋がりました。私は単にパンフレット制作の仕事だけでなく、総合的なマーケティング・コンサルタントとして新しいシステム家具の製品開発から販売支援に至るトータルなプランニングに参加させてもらうべく、社内にプロジェクト・チームを編成し本格的な代理店業務の獲得を目指しました。CBSソニーコミュニケーションズにとってはソニーの関連会社以外で初めての大型クライアントとして総合代理店業務を任される存在になろうとしたのです。プラスには既にメディアAEとして電通、セールス・プロモーション担当として東急エージェンシー、さらに旭通信社とPRエージェント2社が取引していました。我々は新規参入であり、また代理店としての実績も乏しく人材も不足していましたが、プロジェクトのメンバーは新しいチャレンジに意欲的に取り組んで、プラスにとって最大規模の大型投資案件に関する製品開発、マーケティング、プロモーションの業務を担当することが出来ました。
その背景にEPICソニーとの取引があったことは大きな材料でした。プラスにとって、我々は逆の立場で重要な新規クライアントであり、CBSソニーコミュニケーションズが他社を排して「プラスランド」プロジェクトの仕事を獲得できたのは、ビジネス上のバーターが機能していたからです。その意味でも営業的な関係の構築と相互の真剣な仕事への取り組みの姿勢が大切であり、そこに企業同士、人間同士の信頼関係を築く基本があります。私は現在、プラス株式会社の一員として仕事をしています。先に述べた今泉公二氏との10年来のお付き合いの結果として、家具ビジネスの新たな展開のために「プラスランド」の第3次計画のスタートに参加しています。新たな家具製品の工場は2001年12月に完成し、12年前に開発されたオフィスシステム家具の次世代の製品を生み出すべく着々と準備を進めています。時代は12年前とは一変して、日本の企業は大きな構造変革の荒波の中にあり、ビジネス環境も大きく変わりました。OAからITへ、オフィス環境も変化し働き方も変わります。サテライト型オフィスやSOHOなどの新しい仕事場の登場で、仕事のための家具のあり方や使われ方も大きく変化するに違いありません。12年前のプロジェクト以来、私自身はまさにITビジネスの中心的な業界に身を置き、デジタル・ビジネスの最先端で活動していました。その間、私の関わったオフィスシステム家具「リンクス」はプラスの主力商品に育ちましたが、12年余りの時間を経て一つの転機を迎えているようです。そして私は改めて、この12年間の経験を生かして、新たなワーキング・ファニチャーを構想しようと思っています。
4(第二部)
ソニー関連の仕事として、当時のCBSソニーコミュニケーションズ(現ソニーミュージックコミュニケーションズ/SMC)のマーケティング・ディレクターとして参加したもう一つのユニークなプロジェクトは、スキー場の建設です。この運営主体は、正確にはソニーではなく、ソニー創業者のお一人で「世界の盛田」として知られた故盛田昭夫氏の所有されていた会社の事業で、その代表はご長男の盛田英夫氏でした。盛田英夫氏は1951年生まれで、盛田家の当主として、先にご紹介した「株式会社盛田」の次期代表となられる立場の方で、図らずも私とは現ソニーミュージックのほぼ同期入社組でした。第1部でご紹介した(株)EPICソニーの創設メンバーの一人でもあり、洋楽部門の同じチームで草創期を共に過ごしてきた仲間でもあったのです。彼は、EPICソニーでの8年弱の活躍の後、ご実家の当主としての事業を継がれるためにソニーミュージックを退社されたのですが、その後も折に触れてお付き合いをさせて頂いています。その彼の手掛けたリゾート事業の一つが、この「スキー場建設」プロジェクトであり、彼の国際感覚と時代の先見性によって企画された構想として、また日本のスキーリゾート事業全体の大きな転換を促した仕事として現在でも大きな歴史的な意義を果たしています。
このプロジェクトの構想の背景には盛田英夫氏の国際感覚と共に、より具体的な目標として、長野冬季オリンピックの開催がありました。このオリンピックで新種目として正式に取り上げられることになったスノーボードを使った新しい種目は、既に欧米では一般的なスノースポーツとして専用ゲレンデが整備されるなど定着化が進んでいましたが、90年当時の国内のスキー場の大半はまだスノーボードへの対応はされておらず、プレイヤーにとってはまずはゲレンデ探しが第一の条件というような状況で、特に競技者を目指す人々は100%といって良いほど北米とヨーロッパに出向いていたのが実情でした。この辺りの事情を自ら優秀なスキーヤーでもある彼が熟知していたのは、まさに日常的に国際的な活動をベースとしていた生活感であり、また優れて世界中に広い人脈と情報網を持っていることの証左でしょう。彼の「スキー場建設プロジェクト構想」が生まれた背景にはこうした事情があったのです。
スキー場の具体的建設予定地として用地の取得が進められたのは、新潟県新井市の山岳の一部でした。長野五輪に向けて建設が進められていた信越自動車道の新設インターチェンジからの立地を考慮されたもので、またスキーの回転競技やスノーボードの滑降やジャンプ系の種目に適した勾配と雪質を最大の条件として、競技者のトレーニング用施設としての諸条件を整えて、併せて国内のコア・プレイヤーのメッカとしてイメージを定着させようというのが基本のコンセプトです。この新井市との第3セクターとして「アライ・スキーリゾート株式会社」が設立され、スキー場を中心としたリゾート施設、ホテル、観光レジャー施設の総合開発が実質的にスタートしたのは89年、まさにバブルの絶頂期のことであり、新井市も含めて、この第3セクターに関わった銀行、ゼネコン、ホテル、メディアなど各業界の優秀な人材のほとんどがこの構想の素晴らしさとコンセプトに心酔して、理想のスキーリゾート建設を夢見ていました。スタッフの一員としてPR/ADの協力の要請がSMCに寄せられ、私はマーケティングの担当として数年振りに盛田英夫氏と仕事をすることになりました。お互いにEPICソニー時代、同じ世代であり、共に駆けずり回ったことを思い返しながら、全く別のフィールドで新たなプロジェクトに関わることになったことは人と人との繋がりの大切さと暖かさを感じると同時に、各々の境遇の下で、それぞれに新しい目標と夢を実現するときにお互いの力を合わせられるパートナーが存在することは本当に貴重な財産だと改めて思いました。
とはいえ、このプロジェクトは結果として実は大変な難産となったのです。長野五輪が終了して現在に至るまで、理想とされたコンセプトは市場や社会の急激な変化の中で、当初の計画から大幅に後退する成果を生むに留まっており、それは単にバブル崩壊やその後の景気後退といった要因ばかりではありません。社会全体の価値観の変化やグローバリゼーションの急速な進展、また高度情報化といったインフラの変化もまたライフスタイルを含むエンタテインメント分野の構造的な変化を促しており、リゾートやレジャーといった余暇の過ごし方についても様々な様相の転換を迫っています。スポーツエンタテインメントというジャンルとしてマーケティングの観点から眺めた場合においても、この10年間に市場の様相は大きく変わりました。オリンピックを中軸としてのスポーツのプロ/アマ問題やプレイヤーと観客の関係、またそれを巡るメディアのあり方も、今や完全なグローバル・マーケティングの時代に入っており、東西対立/冷戦の終結を契機として、世界的な健康/環境問題とも深く関わりながら、スポーツは人間存在の根本である「肉体」と「生命」の命題に直結する本質的な価値対象として、全く新たな世界的関心事の局面に入ってきたと思われます。
このプロジェクトとの関係で言えば、環境問題、ウインタースポーツ&リゾートのニーズの背景、競争環境、コア・ユーザーのコアなニーズ自体の中身、などの要因が大きな変化の中で個々に、また各々のフェイズと方向性を内在しながら変容していくプロセスで、オリジナル・プランのアイディアが多分に楽観的な予想をベースとしたモデルであったことを立証する結果になったということができます。つまり、単にバブル崩壊以降の「失われた10年」」という日本経済の直接的な後退局面の影響ということだけではなく、時期を同じくして世界的な規模で起こっていた巨大な価値観のパラダイム転換が積算的に効果を及ぼしていた結果であるということが出来ます。
現在、毎日のスポーツ新聞を賑わしている「イチロー現象」をシンボルとして、メディアとビジネスを巻き込んだスポーツエンタテインメントの状況について、次回、このプロジェクトを通して学んだこととしてやや詳しく書きたいと思います。
このプロジェクトの構想の背景には盛田英夫氏の国際感覚と共に、より具体的な目標として、長野冬季オリンピックの開催がありました。このオリンピックで新種目として正式に取り上げられることになったスノーボードを使った新しい種目は、既に欧米では一般的なスノースポーツとして専用ゲレンデが整備されるなど定着化が進んでいましたが、90年当時の国内のスキー場の大半はまだスノーボードへの対応はされておらず、プレイヤーにとってはまずはゲレンデ探しが第一の条件というような状況で、特に競技者を目指す人々は100%といって良いほど北米とヨーロッパに出向いていたのが実情でした。この辺りの事情を自ら優秀なスキーヤーでもある彼が熟知していたのは、まさに日常的に国際的な活動をベースとしていた生活感であり、また優れて世界中に広い人脈と情報網を持っていることの証左でしょう。彼の「スキー場建設プロジェクト構想」が生まれた背景にはこうした事情があったのです。
スキー場の具体的建設予定地として用地の取得が進められたのは、新潟県新井市の山岳の一部でした。長野五輪に向けて建設が進められていた信越自動車道の新設インターチェンジからの立地を考慮されたもので、またスキーの回転競技やスノーボードの滑降やジャンプ系の種目に適した勾配と雪質を最大の条件として、競技者のトレーニング用施設としての諸条件を整えて、併せて国内のコア・プレイヤーのメッカとしてイメージを定着させようというのが基本のコンセプトです。この新井市との第3セクターとして「アライ・スキーリゾート株式会社」が設立され、スキー場を中心としたリゾート施設、ホテル、観光レジャー施設の総合開発が実質的にスタートしたのは89年、まさにバブルの絶頂期のことであり、新井市も含めて、この第3セクターに関わった銀行、ゼネコン、ホテル、メディアなど各業界の優秀な人材のほとんどがこの構想の素晴らしさとコンセプトに心酔して、理想のスキーリゾート建設を夢見ていました。スタッフの一員としてPR/ADの協力の要請がSMCに寄せられ、私はマーケティングの担当として数年振りに盛田英夫氏と仕事をすることになりました。お互いにEPICソニー時代、同じ世代であり、共に駆けずり回ったことを思い返しながら、全く別のフィールドで新たなプロジェクトに関わることになったことは人と人との繋がりの大切さと暖かさを感じると同時に、各々の境遇の下で、それぞれに新しい目標と夢を実現するときにお互いの力を合わせられるパートナーが存在することは本当に貴重な財産だと改めて思いました。
とはいえ、このプロジェクトは結果として実は大変な難産となったのです。長野五輪が終了して現在に至るまで、理想とされたコンセプトは市場や社会の急激な変化の中で、当初の計画から大幅に後退する成果を生むに留まっており、それは単にバブル崩壊やその後の景気後退といった要因ばかりではありません。社会全体の価値観の変化やグローバリゼーションの急速な進展、また高度情報化といったインフラの変化もまたライフスタイルを含むエンタテインメント分野の構造的な変化を促しており、リゾートやレジャーといった余暇の過ごし方についても様々な様相の転換を迫っています。スポーツエンタテインメントというジャンルとしてマーケティングの観点から眺めた場合においても、この10年間に市場の様相は大きく変わりました。オリンピックを中軸としてのスポーツのプロ/アマ問題やプレイヤーと観客の関係、またそれを巡るメディアのあり方も、今や完全なグローバル・マーケティングの時代に入っており、東西対立/冷戦の終結を契機として、世界的な健康/環境問題とも深く関わりながら、スポーツは人間存在の根本である「肉体」と「生命」の命題に直結する本質的な価値対象として、全く新たな世界的関心事の局面に入ってきたと思われます。
このプロジェクトとの関係で言えば、環境問題、ウインタースポーツ&リゾートのニーズの背景、競争環境、コア・ユーザーのコアなニーズ自体の中身、などの要因が大きな変化の中で個々に、また各々のフェイズと方向性を内在しながら変容していくプロセスで、オリジナル・プランのアイディアが多分に楽観的な予想をベースとしたモデルであったことを立証する結果になったということができます。つまり、単にバブル崩壊以降の「失われた10年」」という日本経済の直接的な後退局面の影響ということだけではなく、時期を同じくして世界的な規模で起こっていた巨大な価値観のパラダイム転換が積算的に効果を及ぼしていた結果であるということが出来ます。
現在、毎日のスポーツ新聞を賑わしている「イチロー現象」をシンボルとして、メディアとビジネスを巻き込んだスポーツエンタテインメントの状況について、次回、このプロジェクトを通して学んだこととしてやや詳しく書きたいと思います。
3(第二部)
「音楽専用電池」という、一見「ホントか?」と思うようなキャッチフレーズで展開したソニーの単三乾電池のマーケティングはかなりの成功を収めました。コマーシャルばかりではなく製品のパッケージにも大きくそのキャッチフレーズを表示して、他メーカーとは一線を画した店頭での展開は、特に乾電池の新しい販売拠点として成長してきたコンビニにおいて顕著に成果が現れました。当時、トレンディ・ドラマと呼ばれたTVドラマの主役級として人気が高かった国生さゆりをモデルに起用し、パッケージにまで彼女のポートレートをデザインするという手法は乾電池としては画期的なもので店頭では明らかに他メーカーの製品と差別化されて陳列され、それまで地味だった乾電池の売り場を様変わりさせる効果もあったようです。
このマーケティング・アイディアを理解し、私達の提案を支持して下さった恩人の一人で、私個人にとっても大切な先輩であり、師匠でもあったソニーの池田健太郎さんにはその後も色々とお世話になりました。池田さんは理論家でありながら、一方人情味溢れる熱血営業も展開するパワフルな人物で、その幅広い人脈と豊富なマーケティングの知識にはいつも大いに勉強させられました。また、池田さんの上司で、当時このソニー・エナジーテック株式会社の故角田社長には、国際感覚とソニー・スタイルの大切なエッセンスを教えて頂きました。このプロジェクトは私の会社にとっても、また私個人にとっても大変に大きな意味を持った仕事であり、音楽業界という特殊な社会から脱却して、より社会性の高い幅広い見識と経験を積んでゆくきっかけとなりました。同じソニーのグループ会社の中でもCBSソニーとソニーエナジーテックは最も距離の離れた異質な会社であったため、相互の理解を深めるためにはお互いが謙虚に、かつ冷静にそれぞれのビジネス・モデルとマーケティング手法を公開しじっくりと説明し合うことが如何に大切かを教えられました。コミュニケーションを前提とする提案型のビジネスを標榜していたCBSソニーコミュニケーションズという会社にとっては、まさに身近なところに格好のパートナーが見つかったということであり、その点からも今思い返せば大変に幸運だったと思います。
私のチームは、このソニーエナジーテックをメイン・クライアントとして、その後もソニー・グループ企業を中心に仕事を進めていました。ソニープラザ、ソニー生命、ソニーファイナンス、そして故盛田昭夫ソニー会長のご実家である「盛田株式会社」(この会社は名古屋を地盤とする醸造業の会社で酒や味噌の老舗です)の仕事などもさせて頂きました。これらのおつき合いの中で、ソニー関係の様々な人々と出会い、現在でも親しくおつき合いをさせて頂いている方々と巡り会うことができたことは私にとって大きな財産となっています。
そこで、次にその中でもユニークな経験をさせて頂いたプロジェクトを二つご紹介します。
まず一つ目は今や「幻の商品」とも言えるソニーの失敗作です。MDが登場する2年程前のことです。ソニーの当時「GA(ジェネラル・オーディオ)事業部」と言われていたセクションから新製品のマーケティングに関しての相談がありました。その製品はディスクマンの小型版で世界最小/最軽量を目ざすという期待の製品でした。早速、品川のラボに伺ったのですが、そこで見た試作機は何とも目を疑うような物でした。その頃、CDの普及が進んでCDシングルも軌道に乗り始めた時期だったのですが、この新型CDウォークマンはそのCDシングルのサイズだったのです。(現代で言えばMDウォークマンの原形であり、この時期に既にソニーはMDサイズのウォークマンを完成させていたと言うことになります。)音質も申し分なく、大きさ、軽さも予想以上のものでした。ところが、CDシングル専用のディスクマンが果たして売れるのか?これが大きな問題だったのでしょう。そこで、この製品の企画者達はディスクの装填方法を新たに考案し、ハンバーガー方式にしていたのです。つまりディスクを中に収めて蓋をするという一般的なスタイルではなく、ディスクを蓋の部分と本体で挟むように入れて固定するという設計になっていたのです。従って、まるでハンバーガーのようにデイスクはマシンの蓋部分と本体との間のスキマから見える状態であり、さらに12cmのCDもかかるようになっていたのです。もちろんマシン本体のサイズはCDシングル大ですから12cmCDをかければ当然マシンからはみ出してしまいます。この姿は、まるで旋盤の機械のようにプレイヤーの周囲からCDがそのままむき出しで回転して見えているという何とも奇妙な光景でした。感想を求められた私は思わず絶句してしまいました。世界的な技術力を誇るソニーの開発設計陣を前にして、目の前で実現している「世界最小/最軽量のディスクマン」についての意見を求められても、実際にはこの12cmCDのはみ出した姿は何とも評価のしようがありません。私はその技術力に驚くと共に、CDシングルについてのソニーの技術陣の捉え方に対する現実を見せられた思いがしました。結論として、私はシングル盤の市場について、またその楽しみ方や使い方についてのレポートを提出し、あくまで「世界最小/最軽量のディスクマン」を切り口としたプロモーション展開を提案しました。実は歴史的に見ると、その昔コンパクトな持ち運びの出来る小形のレコードプレイヤーというものはかなり売れていて、17cmシングル盤サイズのターンテーブルで時にはオーバーハングした30cmのLPも聞いていたのです。小さな機械の上に二周りも大きなレコードがかかっている姿は明らかに不安定でしたが、例えば小学校の運動会などでは本部席でそんな光景をしばしば見ることが出来ました。技術者達はそんな話も持ち出してディスクがはみ出している状態の不自然さを是認するような意見も出されましたが、ウォークマンやディスクマンは持ち運び型と言うよりも携帯型であり、単に持ち運びの出来る小形プレイヤーとは使い方が根本的に違います。しかも、ウォークマン・ユーザーの多くは長時間のカセットに好きなアルバム2-3枚分をダビングして持ち歩きながら聞いているというのが当たり前の姿であり、CDシングルを次々ににかけかえるという手間をかけることは全く現実性がありません。そんな訳でこのディスクマンは発売されたもののほとんど成果を得られないまますぐに中止になりました。しかし、私がプロモーションのお手伝いをさせて頂く中で、テレビや雑誌などのメディアに紹介し「世界最小/最軽量のディスクマン」ということでソニーの高い技術力をアピールすることは出来ました。そして、当時の事業部長、大曽根幸三氏と懇意にさせて頂くことになったきっかけがこのプロジェクトでした。
このマーケティング・アイディアを理解し、私達の提案を支持して下さった恩人の一人で、私個人にとっても大切な先輩であり、師匠でもあったソニーの池田健太郎さんにはその後も色々とお世話になりました。池田さんは理論家でありながら、一方人情味溢れる熱血営業も展開するパワフルな人物で、その幅広い人脈と豊富なマーケティングの知識にはいつも大いに勉強させられました。また、池田さんの上司で、当時このソニー・エナジーテック株式会社の故角田社長には、国際感覚とソニー・スタイルの大切なエッセンスを教えて頂きました。このプロジェクトは私の会社にとっても、また私個人にとっても大変に大きな意味を持った仕事であり、音楽業界という特殊な社会から脱却して、より社会性の高い幅広い見識と経験を積んでゆくきっかけとなりました。同じソニーのグループ会社の中でもCBSソニーとソニーエナジーテックは最も距離の離れた異質な会社であったため、相互の理解を深めるためにはお互いが謙虚に、かつ冷静にそれぞれのビジネス・モデルとマーケティング手法を公開しじっくりと説明し合うことが如何に大切かを教えられました。コミュニケーションを前提とする提案型のビジネスを標榜していたCBSソニーコミュニケーションズという会社にとっては、まさに身近なところに格好のパートナーが見つかったということであり、その点からも今思い返せば大変に幸運だったと思います。
私のチームは、このソニーエナジーテックをメイン・クライアントとして、その後もソニー・グループ企業を中心に仕事を進めていました。ソニープラザ、ソニー生命、ソニーファイナンス、そして故盛田昭夫ソニー会長のご実家である「盛田株式会社」(この会社は名古屋を地盤とする醸造業の会社で酒や味噌の老舗です)の仕事などもさせて頂きました。これらのおつき合いの中で、ソニー関係の様々な人々と出会い、現在でも親しくおつき合いをさせて頂いている方々と巡り会うことができたことは私にとって大きな財産となっています。
そこで、次にその中でもユニークな経験をさせて頂いたプロジェクトを二つご紹介します。
まず一つ目は今や「幻の商品」とも言えるソニーの失敗作です。MDが登場する2年程前のことです。ソニーの当時「GA(ジェネラル・オーディオ)事業部」と言われていたセクションから新製品のマーケティングに関しての相談がありました。その製品はディスクマンの小型版で世界最小/最軽量を目ざすという期待の製品でした。早速、品川のラボに伺ったのですが、そこで見た試作機は何とも目を疑うような物でした。その頃、CDの普及が進んでCDシングルも軌道に乗り始めた時期だったのですが、この新型CDウォークマンはそのCDシングルのサイズだったのです。(現代で言えばMDウォークマンの原形であり、この時期に既にソニーはMDサイズのウォークマンを完成させていたと言うことになります。)音質も申し分なく、大きさ、軽さも予想以上のものでした。ところが、CDシングル専用のディスクマンが果たして売れるのか?これが大きな問題だったのでしょう。そこで、この製品の企画者達はディスクの装填方法を新たに考案し、ハンバーガー方式にしていたのです。つまりディスクを中に収めて蓋をするという一般的なスタイルではなく、ディスクを蓋の部分と本体で挟むように入れて固定するという設計になっていたのです。従って、まるでハンバーガーのようにデイスクはマシンの蓋部分と本体との間のスキマから見える状態であり、さらに12cmのCDもかかるようになっていたのです。もちろんマシン本体のサイズはCDシングル大ですから12cmCDをかければ当然マシンからはみ出してしまいます。この姿は、まるで旋盤の機械のようにプレイヤーの周囲からCDがそのままむき出しで回転して見えているという何とも奇妙な光景でした。感想を求められた私は思わず絶句してしまいました。世界的な技術力を誇るソニーの開発設計陣を前にして、目の前で実現している「世界最小/最軽量のディスクマン」についての意見を求められても、実際にはこの12cmCDのはみ出した姿は何とも評価のしようがありません。私はその技術力に驚くと共に、CDシングルについてのソニーの技術陣の捉え方に対する現実を見せられた思いがしました。結論として、私はシングル盤の市場について、またその楽しみ方や使い方についてのレポートを提出し、あくまで「世界最小/最軽量のディスクマン」を切り口としたプロモーション展開を提案しました。実は歴史的に見ると、その昔コンパクトな持ち運びの出来る小形のレコードプレイヤーというものはかなり売れていて、17cmシングル盤サイズのターンテーブルで時にはオーバーハングした30cmのLPも聞いていたのです。小さな機械の上に二周りも大きなレコードがかかっている姿は明らかに不安定でしたが、例えば小学校の運動会などでは本部席でそんな光景をしばしば見ることが出来ました。技術者達はそんな話も持ち出してディスクがはみ出している状態の不自然さを是認するような意見も出されましたが、ウォークマンやディスクマンは持ち運び型と言うよりも携帯型であり、単に持ち運びの出来る小形プレイヤーとは使い方が根本的に違います。しかも、ウォークマン・ユーザーの多くは長時間のカセットに好きなアルバム2-3枚分をダビングして持ち歩きながら聞いているというのが当たり前の姿であり、CDシングルを次々ににかけかえるという手間をかけることは全く現実性がありません。そんな訳でこのディスクマンは発売されたもののほとんど成果を得られないまますぐに中止になりました。しかし、私がプロモーションのお手伝いをさせて頂く中で、テレビや雑誌などのメディアに紹介し「世界最小/最軽量のディスクマン」ということでソニーの高い技術力をアピールすることは出来ました。そして、当時の事業部長、大曽根幸三氏と懇意にさせて頂くことになったきっかけがこのプロジェクトでした。
2(第二部)
CBSコミュニケーションズ(現ソニーミュージックコミュニケーションズ-SMC-)は、ソニーミュージックグループの子会社としては特にユニークな歴史を持ち、その中で独特なノウハウを蓄積しながら、ソフト/サービス系業態にデジタル技術を巧みに組み込んだ企業としてのステイタスを築いてきました。
しかし、私が参画した設立の時期は試行錯誤の連続であり、個人のアイディアや力量に依存する状態の中で、事業の柱となるような組織的な新しいビジネスモデルを模索、探索している段階でした。製版事業という明確な一業種をベースとしながら、親会社のノウハウ、チャネル、ネットワークなどを活用しながらソフト&サービス系の新たなモデルを探る中で、私はプロモーションをベースとするマーケティング・サポート・サービスの事業化を考えていました。現代では既に常識化しているアメリカ生まれの科学的なマーケティング手法によるコンサルティングとサポート・サービスを合体させた事業です。
時代はコンビニエンス・ストアなどの新業態の定着や郊外型ショッピング・モールなどのアメリカ型大型流通業態をモデルとする新たなセールス・チャネルの開発/開拓が進み始めていました。つい先頃、その頃の過剰な拡大戦略によって経営破綻した「そごう」、「マイカル」、「ダイエー」などはその最先端で次々に積極策を打ち出していました。こうした時代背景の中で、マーケティングは最も重要な事業手法として脚光を浴びていて、マスメディアに「マーケティング・ディレクター」「マーケティング・プロデューサー」などの肩書きで登場する人物が現れたりもしました。商品開発、キャンペーン企画、異業種タイアップ・プロモーション、チャネル対策販売促進企画などをこうした人物や小規模な企画会社にアウトソーシングする大手企業も多く、さしずめ現代のIT関連のメディア・プロデューサーやマルチ・メディア・ディレクターなどとよく類似した状況があったのです。
私はSMCの唯一で、初の「マーケティング・ディレクター」としての名刺を持って、ソニー関連会社をはじめとして、新たなクライアント開拓に当たっていました。その中で今でも強く印象に残っているプロジェクトをいくつかご紹介したいと思います。
ソニーの関連会社で、電池とカセットテープを製造販売するソニーエナジーテック(SET)という会社がありました。ソニーブランドの電池とカセットテープは、特にカセットについては定着したシェアがありましたが、時代的にはカセット自体の末期に当たり価格が大幅にダウンしており、事業としては採算性が危ぶまれる状態でした。一方、電池については価格競争と技術競争の真っ只中にあり、消費需要は様々な携帯機器の普及で爆発的に拡大している成長市場で各社の競合が激しさを増していました。特に単三乾電池の需要増に対しては、コンビニエンス・ストアなどの新しい流通も成長し始めており、マーケティング戦略の良し悪しは各社のビジネスの成否を大きく左右していました。需要対象の主役はウォークマン、コンパクトカメラ、そして当時新登場のゲームボーイです。
それまでは電通に委託していたソニーの単三乾電池のマーケティングについて、SMCとして独自の企画を持ちこんでプレゼンテーション・コンペに参加したのです。グループ内の新しい会社であることに対する「ご祝儀」の要素もあったのですが、天下の電通と東急エージェンシーを相手とするコンペへの参加に現場は大いに気合を入れて臨みました。この時のコンセプトはSMCの基本に忠実に「音楽」としての切り口で、ターゲットをウォークマン・ユーザーに絞り込んだコピーに集約されていました。「音楽専用電池」というプロフィールを正面から打ち出すという戦略ですが、当然の事ながら営業系の役員からは懸念が表明されました。そもそも電池には用途の専用性は全くありません。カメラでもおもちゃでも関係無しに使えるものであり、メーカーによる品質の違いは若干あるにせよ、性能とサイズは単三乾電池としての統一規格があり、技術面の競争は専ら容器の容量に比例する秒単位の「発電時間」でしかありません。「音楽専用電池」というプロフィールは徒に用途を限定し、しかも本質的に「正しくない」表現なのです。
コンセプトのポイントは、競合する店頭でのブランド選別の「フェイズ」転換です。他社製品が一応に「容量=時間=パワー」という「定量的」競争の中にあって、唯一ソニーだけは「定性的」意味付けを行うことによって、どのような店頭陳列の状態であっても「はずせない」ブランドとしてプロファイルすることを目指したのです。もちろん背景にはAVブランドとしての「Sony」があり、「ウォークマン電池」という商品名も並行して使うことで、音楽ユースのイメージとクォリティ感に集約することを目指しました。
結論として、このプランが採用されてSMCは単三/単四乾電池のマーケティングと広告宣伝担当会社(Account Executive=AE)として、その後6年余り業務を委託されました。ソニーのシェアは、特に新興のコンビニエンス・ストアでの成功が寄与して3年間で3%余りUPしました。これらの商品、一般的に「コモディティ商品」とよばれる日用品分野では大きな成果であり、SMCの評価が大きく上がった仕事でした。
しかし、私が参画した設立の時期は試行錯誤の連続であり、個人のアイディアや力量に依存する状態の中で、事業の柱となるような組織的な新しいビジネスモデルを模索、探索している段階でした。製版事業という明確な一業種をベースとしながら、親会社のノウハウ、チャネル、ネットワークなどを活用しながらソフト&サービス系の新たなモデルを探る中で、私はプロモーションをベースとするマーケティング・サポート・サービスの事業化を考えていました。現代では既に常識化しているアメリカ生まれの科学的なマーケティング手法によるコンサルティングとサポート・サービスを合体させた事業です。
時代はコンビニエンス・ストアなどの新業態の定着や郊外型ショッピング・モールなどのアメリカ型大型流通業態をモデルとする新たなセールス・チャネルの開発/開拓が進み始めていました。つい先頃、その頃の過剰な拡大戦略によって経営破綻した「そごう」、「マイカル」、「ダイエー」などはその最先端で次々に積極策を打ち出していました。こうした時代背景の中で、マーケティングは最も重要な事業手法として脚光を浴びていて、マスメディアに「マーケティング・ディレクター」「マーケティング・プロデューサー」などの肩書きで登場する人物が現れたりもしました。商品開発、キャンペーン企画、異業種タイアップ・プロモーション、チャネル対策販売促進企画などをこうした人物や小規模な企画会社にアウトソーシングする大手企業も多く、さしずめ現代のIT関連のメディア・プロデューサーやマルチ・メディア・ディレクターなどとよく類似した状況があったのです。
私はSMCの唯一で、初の「マーケティング・ディレクター」としての名刺を持って、ソニー関連会社をはじめとして、新たなクライアント開拓に当たっていました。その中で今でも強く印象に残っているプロジェクトをいくつかご紹介したいと思います。
ソニーの関連会社で、電池とカセットテープを製造販売するソニーエナジーテック(SET)という会社がありました。ソニーブランドの電池とカセットテープは、特にカセットについては定着したシェアがありましたが、時代的にはカセット自体の末期に当たり価格が大幅にダウンしており、事業としては採算性が危ぶまれる状態でした。一方、電池については価格競争と技術競争の真っ只中にあり、消費需要は様々な携帯機器の普及で爆発的に拡大している成長市場で各社の競合が激しさを増していました。特に単三乾電池の需要増に対しては、コンビニエンス・ストアなどの新しい流通も成長し始めており、マーケティング戦略の良し悪しは各社のビジネスの成否を大きく左右していました。需要対象の主役はウォークマン、コンパクトカメラ、そして当時新登場のゲームボーイです。
それまでは電通に委託していたソニーの単三乾電池のマーケティングについて、SMCとして独自の企画を持ちこんでプレゼンテーション・コンペに参加したのです。グループ内の新しい会社であることに対する「ご祝儀」の要素もあったのですが、天下の電通と東急エージェンシーを相手とするコンペへの参加に現場は大いに気合を入れて臨みました。この時のコンセプトはSMCの基本に忠実に「音楽」としての切り口で、ターゲットをウォークマン・ユーザーに絞り込んだコピーに集約されていました。「音楽専用電池」というプロフィールを正面から打ち出すという戦略ですが、当然の事ながら営業系の役員からは懸念が表明されました。そもそも電池には用途の専用性は全くありません。カメラでもおもちゃでも関係無しに使えるものであり、メーカーによる品質の違いは若干あるにせよ、性能とサイズは単三乾電池としての統一規格があり、技術面の競争は専ら容器の容量に比例する秒単位の「発電時間」でしかありません。「音楽専用電池」というプロフィールは徒に用途を限定し、しかも本質的に「正しくない」表現なのです。
コンセプトのポイントは、競合する店頭でのブランド選別の「フェイズ」転換です。他社製品が一応に「容量=時間=パワー」という「定量的」競争の中にあって、唯一ソニーだけは「定性的」意味付けを行うことによって、どのような店頭陳列の状態であっても「はずせない」ブランドとしてプロファイルすることを目指したのです。もちろん背景にはAVブランドとしての「Sony」があり、「ウォークマン電池」という商品名も並行して使うことで、音楽ユースのイメージとクォリティ感に集約することを目指しました。
結論として、このプランが採用されてSMCは単三/単四乾電池のマーケティングと広告宣伝担当会社(Account Executive=AE)として、その後6年余り業務を委託されました。ソニーのシェアは、特に新興のコンビニエンス・ストアでの成功が寄与して3年間で3%余りUPしました。これらの商品、一般的に「コモディティ商品」とよばれる日用品分野では大きな成果であり、SMCの評価が大きく上がった仕事でした。
1(第二部)
CBSソニー(当時)の新しい子会社、CBSソニーコミュニケーションズはグループ内の子会社としては初めてと言ってもよいサービス業の会社であり、具体的な商品を持たない企業でした。それまでにもグループの中には芸能プロダクションや著作権管理会社などがありましたが、いずれも本業の音楽関連の業態であり、純粋な意味での企画サービス、技術サービスのみを行う「エージェント」的な業態は初の試みだったと思います。
この会社の母体となったのは印刷の前工程と言える「製版」を行う工場です。クリエイティブなセンスも必要とされる製版業は付加価値の高い業種の一つで、レコード産業のように商品パッケージがほぼ一定の形態である業種にとっては特にメリットが大きく、CBSソニーはかなり初期の頃から製版を内製していたのです。その経験とノウハウを生かして、既にCBSソニーコミュニケーションズとして独立した時点では、社内はもとより同業他社のジャケット製版も多数手がけており、事業としてかなりの成果を上げていました。親会社のソニーの仕事も沢山手がけていて、ソニー製品のパンフレットやポスターなどの宣伝/マーケティング・ツールやパッケージ、雑誌や新聞広告など、また多くのソニーグループ企業の様々な印刷物の製版工程を引き受ける形でソニーグループ全体の仕事を開拓していました。
CBSソニーコミュニケーションズとして独立した時期は「製版業」にデジタル技術の新しい波が訪れ、デスクトップ・パブリッシング(DTP)が一般化し始めた頃であり、「デジタル製版」の第1期に入った頃でした。新しい設備投資と先行するデジタル技術のノウハウを売り物にして、安価で早く、また校正や修正のしやすいサービスを一早く取り入れることで新しいクライアントの開拓も始めようという考えで事業の拡大を目指したのです。また、製版に至る前の工程と言えるデザイン工程、そのさらに前の段階である広告・宣伝企画全体を視野に入れて、セールス・プロモーションとマーケティング全体を包括した「広告代理店業」への参入も新規事業の一つとして考えられていました。
私はこの新会社の構想を提案した一人として参加することになったのですが、全社から集められた人材と既に存在していた製版事業の人々との間には同じ会社の人間でありながらも経験やノウハウの全く異なった文化があり、一つのチームとしてまとまって行くためには双方の努力が必要だと感じました。特に音楽業界、芸能界出身の人々と製版業のプロとして育ってきた人々の間には日常の行動パターン一つをとっても大きな隔たりがあり、またサービス業としてのビジネス・モデルをきっちりと理解して事業や経営の舵取りを行うマネジメントの体質や指導力も完全なものではありませんでした。「エージェント」事業としての収益の考え方や売上と利益管理の方法についても個人の裁量に任されるケースが多く、既に一定のビジネスモデルを確立していた製版業以外の新規事業はいずれも組織的な戦略的事業方針を掲げることが出来ず、個人ベースの企画開発に終始していました。今改めて振り返って見ると、一面でこの状況は不可避なものだったと思われます。マネジメント・チームを含めて製版事業以外の部門から集められた人材はそれぞれに実績と経験を備えた精鋭であり、独自のビジネス観と個々のキャリア上の目標を持っていました。ある意味で、各々が独り立ち出来るだけのベンチャー性と実力を持って、「個」としての活動を通して次世代型ビジネスモデルの実証実験を行っていたのだと解釈することが出来ます。トップはこれらの「個」の活動の中から次の組織的ビジネスの「ネタ」を探りながら、徐々にシステム的な事業モデルの構築を進めるためにマネジメント・チームを頻繁に交代させてきました。結果として、事業の安定化と着実な成長へのドメインが固まりグループ内でのユニークなポジションを確立すると共に、プロパーな人材を育てることも出来ました。
私個人にとっても、この会社での経験はその後の自分自身のビジネス・キャリアの上で大変に貴重なものでした。今日では「起業家」=アントレプレナーという言葉が一般化していますが、私がその部分での考え方を学んだのはまさにこの時代であり、およそ5年間のこの会社でのキャリアの中で築いた人脈は現在の私に直結しています。ソニーグループ以外の企業との積極的な交流はEPICソニーでの最後の2年間からさらに広がり、GMS、HC、コンビニなど大手流通系の勉強や「B to B」をベースとする業態の研究、また官公庁や特殊法人の人脈などもこの頃から広がり始めました。様々な業種のビジネスモデルを見聞し、その中でデジタル時代の幕開けという歴史的な構造変革が始まり、さらにバブル崩壊後のシビアな国内市場状況の中での消費低迷現象とレコード産業を支える若年層市場の変化は現在までの市場環境激変の明らかな「兆候」を感じ取ることが出来ました。新時代への移行過渡期的現象の数々は「危機とチャンス」が同居する時代であることを示し、守旧派と革新派のせめぎあい、世代交代の加速化、消費者至上主義の圧倒的支配、共存からサバイバルへの転換といった現代日本経済の構造変化のビビッドな局面そのものに立ち合う形で、情報技術の進展に対する自分自身のスキルアップも積極的に行ってきました。
次回からは、この時代に担当した具体的なプロジェクトをいくつかを取り上げながら、各々の企業の中でのドラマチックな変化のエピソードの一部でもご紹介できたらと思います。
この会社の母体となったのは印刷の前工程と言える「製版」を行う工場です。クリエイティブなセンスも必要とされる製版業は付加価値の高い業種の一つで、レコード産業のように商品パッケージがほぼ一定の形態である業種にとっては特にメリットが大きく、CBSソニーはかなり初期の頃から製版を内製していたのです。その経験とノウハウを生かして、既にCBSソニーコミュニケーションズとして独立した時点では、社内はもとより同業他社のジャケット製版も多数手がけており、事業としてかなりの成果を上げていました。親会社のソニーの仕事も沢山手がけていて、ソニー製品のパンフレットやポスターなどの宣伝/マーケティング・ツールやパッケージ、雑誌や新聞広告など、また多くのソニーグループ企業の様々な印刷物の製版工程を引き受ける形でソニーグループ全体の仕事を開拓していました。
CBSソニーコミュニケーションズとして独立した時期は「製版業」にデジタル技術の新しい波が訪れ、デスクトップ・パブリッシング(DTP)が一般化し始めた頃であり、「デジタル製版」の第1期に入った頃でした。新しい設備投資と先行するデジタル技術のノウハウを売り物にして、安価で早く、また校正や修正のしやすいサービスを一早く取り入れることで新しいクライアントの開拓も始めようという考えで事業の拡大を目指したのです。また、製版に至る前の工程と言えるデザイン工程、そのさらに前の段階である広告・宣伝企画全体を視野に入れて、セールス・プロモーションとマーケティング全体を包括した「広告代理店業」への参入も新規事業の一つとして考えられていました。
私はこの新会社の構想を提案した一人として参加することになったのですが、全社から集められた人材と既に存在していた製版事業の人々との間には同じ会社の人間でありながらも経験やノウハウの全く異なった文化があり、一つのチームとしてまとまって行くためには双方の努力が必要だと感じました。特に音楽業界、芸能界出身の人々と製版業のプロとして育ってきた人々の間には日常の行動パターン一つをとっても大きな隔たりがあり、またサービス業としてのビジネス・モデルをきっちりと理解して事業や経営の舵取りを行うマネジメントの体質や指導力も完全なものではありませんでした。「エージェント」事業としての収益の考え方や売上と利益管理の方法についても個人の裁量に任されるケースが多く、既に一定のビジネスモデルを確立していた製版業以外の新規事業はいずれも組織的な戦略的事業方針を掲げることが出来ず、個人ベースの企画開発に終始していました。今改めて振り返って見ると、一面でこの状況は不可避なものだったと思われます。マネジメント・チームを含めて製版事業以外の部門から集められた人材はそれぞれに実績と経験を備えた精鋭であり、独自のビジネス観と個々のキャリア上の目標を持っていました。ある意味で、各々が独り立ち出来るだけのベンチャー性と実力を持って、「個」としての活動を通して次世代型ビジネスモデルの実証実験を行っていたのだと解釈することが出来ます。トップはこれらの「個」の活動の中から次の組織的ビジネスの「ネタ」を探りながら、徐々にシステム的な事業モデルの構築を進めるためにマネジメント・チームを頻繁に交代させてきました。結果として、事業の安定化と着実な成長へのドメインが固まりグループ内でのユニークなポジションを確立すると共に、プロパーな人材を育てることも出来ました。
私個人にとっても、この会社での経験はその後の自分自身のビジネス・キャリアの上で大変に貴重なものでした。今日では「起業家」=アントレプレナーという言葉が一般化していますが、私がその部分での考え方を学んだのはまさにこの時代であり、およそ5年間のこの会社でのキャリアの中で築いた人脈は現在の私に直結しています。ソニーグループ以外の企業との積極的な交流はEPICソニーでの最後の2年間からさらに広がり、GMS、HC、コンビニなど大手流通系の勉強や「B to B」をベースとする業態の研究、また官公庁や特殊法人の人脈などもこの頃から広がり始めました。様々な業種のビジネスモデルを見聞し、その中でデジタル時代の幕開けという歴史的な構造変革が始まり、さらにバブル崩壊後のシビアな国内市場状況の中での消費低迷現象とレコード産業を支える若年層市場の変化は現在までの市場環境激変の明らかな「兆候」を感じ取ることが出来ました。新時代への移行過渡期的現象の数々は「危機とチャンス」が同居する時代であることを示し、守旧派と革新派のせめぎあい、世代交代の加速化、消費者至上主義の圧倒的支配、共存からサバイバルへの転換といった現代日本経済の構造変化のビビッドな局面そのものに立ち合う形で、情報技術の進展に対する自分自身のスキルアップも積極的に行ってきました。
次回からは、この時代に担当した具体的なプロジェクトをいくつかを取り上げながら、各々の企業の中でのドラマチックな変化のエピソードの一部でもご紹介できたらと思います。
profile(第二部)
[プロフィール]
吉川 成昭(よしかわ・しげあき)
CBSソニー(現SME)で、洋楽部門ディレクター、マルチメディア部門プロデューサーなどを歴任。その後、ソニーコミュニケーションネットワーク(So-net)の設立に参画し、PostPetなどを立ち上げる。現在、外資系コンテンツ開発会社の代表を経て、現在、プラス(株)にて同社の家具製品事業戦略、新製品開発に従事、ビジネス・コンサルタント、マーケティング・ディレクターとしても活動中。
『吉川さんの真似をしてパナマ帽を買った。
ただの麦わら帽子にしか見えなかった。
まだまだ勉強。』(PostPetプロデューサーきたむら談)
「私の楽歴書(第二部)」は、「月刊ポストペット2001」にて2001/04~2003/01の期間、掲載
吉川 成昭(よしかわ・しげあき)
CBSソニー(現SME)で、洋楽部門ディレクター、マルチメディア部門プロデューサーなどを歴任。その後、ソニーコミュニケーションネットワーク(So-net)の設立に参画し、PostPetなどを立ち上げる。現在、外資系コンテンツ開発会社の代表を経て、現在、プラス(株)にて同社の家具製品事業戦略、新製品開発に従事、ビジネス・コンサルタント、マーケティング・ディレクターとしても活動中。
『吉川さんの真似をしてパナマ帽を買った。
ただの麦わら帽子にしか見えなかった。
まだまだ勉強。』(PostPetプロデューサーきたむら談)
「私の楽歴書(第二部)」は、「月刊ポストペット2001」にて2001/04~2003/01の期間、掲載
27(第一部)
EPICソニー「ニューアーティスト・ショーケース」は、無名や新人のアーティストのライブ・ステージを楽しみ、自分なりの評価をしたいという洋楽のコア・ファンの着実なニーズを証明することになりました。また、洋楽業界全体の新しいビジネス・モデルを示唆するいくつかの重要な問題提起をしたとも考えられます。時代はバブルへ向かって進んでおり、価値観の多様化と有名ブランド志向が共存し、グルメブームとマネーゲームの情報が氾濫する中で日本全体が「ジュリアナ」カラーに染まって行くのですが、アナログからデジタルへ=レコードからCDへの変化に象徴される「軽薄短小」の時代感覚、ファミコンの爆発的なヒットによる「ゲーム世代」の台頭、その裏文化としての「オタク」や「フェチ」の登場など、バブル経済の崩壊後に表舞台へ出てくるサブ・カルチャー的な衣装を纏ったニュー・ビヘイビア・グループは既に80年代末期に着実に育っていました。
1989年を挟んで前後の3年間は、後に大事件を起こすオウムが急速に勢力を拡大した時期であり、世紀末論議、世界的な政治・経済の変化、西側の勝利=アメリカの復権というストーリーの流れの中で、日本経済の突然の崩壊が若年層/青年層にもたらしたインパクトは想像を越える大きなものでした。その若年層/青年層を主たる購買ターゲットとする音楽業界は常に時代感覚の先端で活動しなければならないビジネスとしての宿命を背負いながら、バブルを背景としてメディアや一般企業との関係を深めて行くプロセスの中で、その本質的な使命を果たしきれず、特に企業化した大手レコード会社は新しい時代の音楽を生み出し、発掘し、育てるという力を急速に失っていくことになります。
ソニー・ミュージックも例外ではなく、そのクリエイティブなパワーの象徴とも言える存在だったリーダーが「ゲーム・ビジネス」に最大の興味と関心を抱くことになってからは、本業のミュージック・ビジネスは徐々に力を失い、新興勢力の「エイベックス・トラックス」などにアーティスト諸共主役の座を奪われることになります。ソニーミュージックのアーティストの一部がファミコンソフトを企画し、発売したことを覚えていらっしゃる方もいることでしょう。皮肉なことに上場企業としての体裁と体制を整えた時期から日本経済が本格的な景気後退の局面に入り、それまでの「超優良企業」としてのイメージにも徐々に陰りが見え始めてきます。一方で、IT時代の先駆とも言える「デジタル」文化の象徴として、日本産の「ゲームビジネス」は任天堂のファミコンによる世界制覇から第2次(32ビット)時代へと移り変わる時期に差し掛かって、記憶に新しい「プレステ」vs「サターン」の激しい市場競争の時代へと進んで行きます。
EPICソニー「ニューアーティスト・ショーケース」に携わった私は、業界の抱える構造的な問題と「洋楽ビジネス」の限界、特に海外におけるアーティストとレコード会社の関係について新しい「ビジネス・モデル」が登場し始めてきたことやソニーのCBSレコード買収や松下によるMCA買収などのバブルを背景とした日本資本のアメリカ企業買収ブームに乗った一連の国際的なビジネス・フレームの大きな変化について、一種の困惑と洋楽ビジネスという日本市場向けのディストリビューション・ビジネスの考え方自体に限界を感じ始めていました。既に価格の安い輸入CDやTower RecordsやVirgin Megastoreなどの米、英の大型流通の進出によって「洋楽CD」の国内制作や国内プレスの必然性が益々希薄になってきたと考えはじめていたのです。
私自身のサラリーマンとしてのキャリア、そしてキャリアに見合った仕事のレベル、またマーケティングを軸とした新規事業開発に対する個人的な強い関心などの要素が相俟って、私がEPICソニー洋楽部門から離れることになったのは必然的な流れだったと思います。私のおよそ10年の音楽業界でのキャリアを通して、芸能界としての華やかな一面や国際ビジネスとしてのスケール、さらにメディアやエージェントのマーケティングに関する知識など現在の私自身の基礎とも言える大きく貴重な経験をすることが出来ました。また、ソニーミュージックの一員として新しいビジネスの開拓、会社の将来に寄与する新しいノウハウの蓄積など、ここでの経験を生かしながらソニーミュージックらしい新規事業を立ち上げるという興味深いミッションを与えられることになりました。
この「楽歴書」も音楽業界でのお話を終えて、2001年から現在の私にダイレクトにつながる第2部の「楽歴」に入って行きます。私自身、20世紀の後半を生きてきて、自分自身のキャリアを振り返りながら時代の総括を出来たことは大変に有意義でした。改めて、装いも新たに第2部を書き綴ってみたいと思っています。
1989年を挟んで前後の3年間は、後に大事件を起こすオウムが急速に勢力を拡大した時期であり、世紀末論議、世界的な政治・経済の変化、西側の勝利=アメリカの復権というストーリーの流れの中で、日本経済の突然の崩壊が若年層/青年層にもたらしたインパクトは想像を越える大きなものでした。その若年層/青年層を主たる購買ターゲットとする音楽業界は常に時代感覚の先端で活動しなければならないビジネスとしての宿命を背負いながら、バブルを背景としてメディアや一般企業との関係を深めて行くプロセスの中で、その本質的な使命を果たしきれず、特に企業化した大手レコード会社は新しい時代の音楽を生み出し、発掘し、育てるという力を急速に失っていくことになります。
ソニー・ミュージックも例外ではなく、そのクリエイティブなパワーの象徴とも言える存在だったリーダーが「ゲーム・ビジネス」に最大の興味と関心を抱くことになってからは、本業のミュージック・ビジネスは徐々に力を失い、新興勢力の「エイベックス・トラックス」などにアーティスト諸共主役の座を奪われることになります。ソニーミュージックのアーティストの一部がファミコンソフトを企画し、発売したことを覚えていらっしゃる方もいることでしょう。皮肉なことに上場企業としての体裁と体制を整えた時期から日本経済が本格的な景気後退の局面に入り、それまでの「超優良企業」としてのイメージにも徐々に陰りが見え始めてきます。一方で、IT時代の先駆とも言える「デジタル」文化の象徴として、日本産の「ゲームビジネス」は任天堂のファミコンによる世界制覇から第2次(32ビット)時代へと移り変わる時期に差し掛かって、記憶に新しい「プレステ」vs「サターン」の激しい市場競争の時代へと進んで行きます。
EPICソニー「ニューアーティスト・ショーケース」に携わった私は、業界の抱える構造的な問題と「洋楽ビジネス」の限界、特に海外におけるアーティストとレコード会社の関係について新しい「ビジネス・モデル」が登場し始めてきたことやソニーのCBSレコード買収や松下によるMCA買収などのバブルを背景とした日本資本のアメリカ企業買収ブームに乗った一連の国際的なビジネス・フレームの大きな変化について、一種の困惑と洋楽ビジネスという日本市場向けのディストリビューション・ビジネスの考え方自体に限界を感じ始めていました。既に価格の安い輸入CDやTower RecordsやVirgin Megastoreなどの米、英の大型流通の進出によって「洋楽CD」の国内制作や国内プレスの必然性が益々希薄になってきたと考えはじめていたのです。
私自身のサラリーマンとしてのキャリア、そしてキャリアに見合った仕事のレベル、またマーケティングを軸とした新規事業開発に対する個人的な強い関心などの要素が相俟って、私がEPICソニー洋楽部門から離れることになったのは必然的な流れだったと思います。私のおよそ10年の音楽業界でのキャリアを通して、芸能界としての華やかな一面や国際ビジネスとしてのスケール、さらにメディアやエージェントのマーケティングに関する知識など現在の私自身の基礎とも言える大きく貴重な経験をすることが出来ました。また、ソニーミュージックの一員として新しいビジネスの開拓、会社の将来に寄与する新しいノウハウの蓄積など、ここでの経験を生かしながらソニーミュージックらしい新規事業を立ち上げるという興味深いミッションを与えられることになりました。
この「楽歴書」も音楽業界でのお話を終えて、2001年から現在の私にダイレクトにつながる第2部の「楽歴」に入って行きます。私自身、20世紀の後半を生きてきて、自分自身のキャリアを振り返りながら時代の総括を出来たことは大変に有意義でした。改めて、装いも新たに第2部を書き綴ってみたいと思っています。
26(第一部)
音楽業界における「ショーケース」とは、ブレイク前の有望なアーティストのお披露目ライブのことです。ほとんどの場合、料金はタダに等しいためステージはクラブあるいはイベント会場であることが多く、まれにビッグ・アーティストの前座バンドとして大きなステージに抜擢されることがありますが、この場合は特に「ショーケース」とは表現しないようです。また、80年代の初め頃にアメリカのロック・ミュージック界でしばしばこの表現が使われましたが、日本国内では現在までほとんど定着していない用語であり、読者の皆さんにもあまり馴染みのない言葉かもしれません。
前回にもご説明したように、EPICソニーの洋楽部門は高騰する宣伝費の節減と合理化のために、新人のデビュー・キャンペーンに対するコスト・ダウンとリスク・ヘッジを狙って様々な仕掛けを考えていました。「ニューアーティスト・ショーケース」と名付けられた新人キャンペーンは、一つの新規事業としての狙いも併せ持った形で、世界の5組のアーティストを2ケ月間に集中的に来日させ、東京と大阪で立て続けに「ショーケース」を開いてメディアやユーザーの注目を集めようとして考え出されたものでした。しかも、本来は「無料」に近いチケットを2000円で販売して「ショーケース」という新しいコンサート形式を業界に提案する形で、コンサート興行を行う洋楽系音楽事務所や媒体を巻き込みながら、バブル時代の企業イベントとして典型的な「冠コンサート」の体裁を整えるという仕掛けでした。背景には、洋楽コンサートのチケット価格がかなり高騰しコンサート自体も企業の大型イベント化する流れが主流となっていたこと、逆に新人や中堅のコンサートの招聘機会が減少して新しいアーティストを育てる環境が徐々に少なくなってきた状況がありました。ここらあたりにも日本の「バブル時代」のお祭り的気運が音楽業界にも大きく影響していたことが窺えます。
EPICソニー「ニューアーティスト・ショーケース」によってピックアップされた世界の新人アーティストは次の5組のロック系グループでした。「ティル・チューズデイ/'til Tuesday」(米)、「プリファブ・スプラウト/Prefab Sprout」(英)、「フェイス・トゥ・フェイス/Face To Face」(加)、「ワワニー/Wa Wa Nee」(豪)、「ユーログライダーズ/Eurogliders」(ニュージーランド)、の以上5組です。あれから10数年が経過した現在でも活動を続けているグループは残念ながら1組もないと思いますが、この中では「ティル・チューズデイ」と「プリファブ・スプラウト」が当時の注目株で、特にニューウェーブ系ブリティッシュ・バンドの「プリファブ・スプラウト」は一足先にアルバムをリリースしており、国内でも一部マニアの評判も上がっていて、案の定チケットはほぼ完売する人気でした。これらのファンからは「2000円のコンサート」は画期的な企画として絶賛されて投書や激励の手紙なども頂戴しました。一方、ニュージーランドのポップ系グループ「ユーログライダーズ」は豪州ではかなりの人気をもっていたキャリアのあるバンドでしたが、日本ではまったく無名、チケットも50%に満たない売れ行きだったと記憶しています。
この「ショーケース」のチケットの販売方法も当時としては画期的なもので、ほぼ週1回/連続5回の割引通し券と各2000円のバラ売りを併用し、スポンサーやメディアの招待券やプレゼント券による動員を図りつつ、雑誌広告による通信販売と電話予約、担当した音楽事務所による「チケットぴあ」販売も行われました。特に連続5回の通し券は、企画段階では関係者のほぼ全員が否定的でしたが、実際には全体の20%程度に当たる有料動員を果たし、洋楽コア・ファンの確かなライブのニーズを証明する形になりました。例え無名や新人のアーティストであっても、ライブ・ステージを楽しみ、自分なりの評価をしたいというファンが着実に育っていることを実証したということができます。
実際の企画推進のためには音楽事務所の理解と協力は不可欠であり、興行の主体としての音楽事務所は小屋(ホール)の手配からチケットの販売、そしてアーティスト・ケアまでの一貫した作業の流れをつかさどるノウハウをすべて握っており、プロとしてのプライドとともにレコード会社に対して独特のスタンスを持っています。特に海外アーティストの招聘を扱う音楽事務所はレコード(CD)の販売実績に基づくマーケットのニーズを予測しながら、アーティストのマネジメントから「国際興行権」を譲り受けたプロモーターと日本での興行権を巡って競合他社との争奪戦を展開するのですが、コンサートの規模、回数、地域、ターゲットなどの判断を行う上で、レコード会社のマーケティング活動との連携を極めて重要視しています。彼らの協力を得ずして「ショーケース」の実現は不可能であり、同時にレコード会社との協力関係なくして彼らのビジネスも成立しないというギブ&テイクの関係を背景としながらも、ハイリスクでアドバンス資金を必要とするコンサート興行を業務とする音楽事務所は一般的に企業規模も小さいため、レコード会社の宣伝資金力を当てにしているケースが多く、お互いに予算を巡って牽制し合う関係でもあるのです。
前回にもご説明したように、EPICソニーの洋楽部門は高騰する宣伝費の節減と合理化のために、新人のデビュー・キャンペーンに対するコスト・ダウンとリスク・ヘッジを狙って様々な仕掛けを考えていました。「ニューアーティスト・ショーケース」と名付けられた新人キャンペーンは、一つの新規事業としての狙いも併せ持った形で、世界の5組のアーティストを2ケ月間に集中的に来日させ、東京と大阪で立て続けに「ショーケース」を開いてメディアやユーザーの注目を集めようとして考え出されたものでした。しかも、本来は「無料」に近いチケットを2000円で販売して「ショーケース」という新しいコンサート形式を業界に提案する形で、コンサート興行を行う洋楽系音楽事務所や媒体を巻き込みながら、バブル時代の企業イベントとして典型的な「冠コンサート」の体裁を整えるという仕掛けでした。背景には、洋楽コンサートのチケット価格がかなり高騰しコンサート自体も企業の大型イベント化する流れが主流となっていたこと、逆に新人や中堅のコンサートの招聘機会が減少して新しいアーティストを育てる環境が徐々に少なくなってきた状況がありました。ここらあたりにも日本の「バブル時代」のお祭り的気運が音楽業界にも大きく影響していたことが窺えます。
EPICソニー「ニューアーティスト・ショーケース」によってピックアップされた世界の新人アーティストは次の5組のロック系グループでした。「ティル・チューズデイ/'til Tuesday」(米)、「プリファブ・スプラウト/Prefab Sprout」(英)、「フェイス・トゥ・フェイス/Face To Face」(加)、「ワワニー/Wa Wa Nee」(豪)、「ユーログライダーズ/Eurogliders」(ニュージーランド)、の以上5組です。あれから10数年が経過した現在でも活動を続けているグループは残念ながら1組もないと思いますが、この中では「ティル・チューズデイ」と「プリファブ・スプラウト」が当時の注目株で、特にニューウェーブ系ブリティッシュ・バンドの「プリファブ・スプラウト」は一足先にアルバムをリリースしており、国内でも一部マニアの評判も上がっていて、案の定チケットはほぼ完売する人気でした。これらのファンからは「2000円のコンサート」は画期的な企画として絶賛されて投書や激励の手紙なども頂戴しました。一方、ニュージーランドのポップ系グループ「ユーログライダーズ」は豪州ではかなりの人気をもっていたキャリアのあるバンドでしたが、日本ではまったく無名、チケットも50%に満たない売れ行きだったと記憶しています。
この「ショーケース」のチケットの販売方法も当時としては画期的なもので、ほぼ週1回/連続5回の割引通し券と各2000円のバラ売りを併用し、スポンサーやメディアの招待券やプレゼント券による動員を図りつつ、雑誌広告による通信販売と電話予約、担当した音楽事務所による「チケットぴあ」販売も行われました。特に連続5回の通し券は、企画段階では関係者のほぼ全員が否定的でしたが、実際には全体の20%程度に当たる有料動員を果たし、洋楽コア・ファンの確かなライブのニーズを証明する形になりました。例え無名や新人のアーティストであっても、ライブ・ステージを楽しみ、自分なりの評価をしたいというファンが着実に育っていることを実証したということができます。
実際の企画推進のためには音楽事務所の理解と協力は不可欠であり、興行の主体としての音楽事務所は小屋(ホール)の手配からチケットの販売、そしてアーティスト・ケアまでの一貫した作業の流れをつかさどるノウハウをすべて握っており、プロとしてのプライドとともにレコード会社に対して独特のスタンスを持っています。特に海外アーティストの招聘を扱う音楽事務所はレコード(CD)の販売実績に基づくマーケットのニーズを予測しながら、アーティストのマネジメントから「国際興行権」を譲り受けたプロモーターと日本での興行権を巡って競合他社との争奪戦を展開するのですが、コンサートの規模、回数、地域、ターゲットなどの判断を行う上で、レコード会社のマーケティング活動との連携を極めて重要視しています。彼らの協力を得ずして「ショーケース」の実現は不可能であり、同時にレコード会社との協力関係なくして彼らのビジネスも成立しないというギブ&テイクの関係を背景としながらも、ハイリスクでアドバンス資金を必要とするコンサート興行を業務とする音楽事務所は一般的に企業規模も小さいため、レコード会社の宣伝資金力を当てにしているケースが多く、お互いに予算を巡って牽制し合う関係でもあるのです。
25(第一部)
新しいミッションとして与えられた海外アーティストを使った「事業開発」は、結果としてほとんど具体的な成果を上げることは出来ませんでした。一般企業との接点やメディアとのタイアップも従来からの関係のレベルを越えることはなかなか出来ず、私自身がレコード会社にとっての新たな収益源に育ってゆくような具体的な「事業イメージ」を全く描くことが出来なかったのです。
一方で洋楽部門は、限りある販売促進予算の中でリスクの高い新人のデビュー費用を捻出することが徐々に難しくなり始めて来ており、部門はその対策として新しい仕掛けを考えていました。それは業界内の利害関係を見渡して、その力関係と一種の政治力バランスを使って、さらに一般企業や広告代理店、メディアをも巻き込んだ大がかりな新人キャンペーンを展開しようという構想です。そしてその仕掛けの推進と実行のために私達の部隊が駆り出されました。
「ニュー・アーティスト・ショーケース」と名付けられたその新人デビューキャンペーンは、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアの新人ロックグループ5組を一気にデビューさせる目的で、5つのバンドを各々1週間づつ連続的に来日させてライブ・コンサートとプロモーション活動を、東京と大阪で、展開しようというものです。この連続コンサートのために協賛スポンサー、媒体、音楽興業事務所、音楽出版会社、そして各国のCBSをも巻き込み、有料のコンサートにすることで一定の収益を上げながら、デビューに当たってのプロモーション活動も同時に行うことで、従来から100%自己負担で進めてきたプロモーション来日の費用を削減し、あわよくば利潤を上げようという企画だったのです。対象となった5組のアーティストは、いずれも各々の自国でデビューしたて、ないしデビューから1年以内といった新人ばかりで日本国内ではほとんど無名のグループばかりでした。当時(現在でも)、そうした海外の新人アーティストの有料コンサートというものは全く常識はずれと考えられており、チケットが売れる見込みはほとんど無しというのが普通の考え方です。
そこで、この企画が生まれた当時の背景を振り返ってみましょう。日本の音楽界はEPICソニーの誕生の頃から大きく変化していました。「日本のロック」が定着し始め、各地のライブハウスが活性化して続々と新しいグループが登場してきました。レコード会社やプロダクション各社は全国各地のライブハウスをスカウトの場として捉えて専任スタッフを付けて新人の発掘を進めました。各社のオーディションやTVの新人ロックバンド発掘番組も人気を呼んで、いわゆる第3次バンドブームとなったのです。レコード・デビューを目指すロックグループは地元のライブハウスでの活動でファン作りを進めながら、オーディションやイベントへの出演などで評判を上げながらプロへの道を志すのですが、レコード会社やプロダクションのプロデューサーの目に止まるのが先ず第一のステップです。こうしたスタイルは海外では60年代以降当り前の姿でしたが、我が国ではフォークから派生したニューミュージックの時代にすでに同様なスタイルでアーティストの発掘をしていました。60年代半ばの第1次バンドブーム(グループサウンズ)、70年代後半の第2次バンドブーム(フォーク&ニューミュージック)が起こった時にも同じように多数のアマチュアグループが登場しましたが、プロを目指す意欲という点で、第3次ブームのジャパン・ロックの時代はかなり様子が違ってきました。また、そもそも海外生まれのロックについては、聴き手の側も「聴く耳」をもったファンが育ちつつあって、作品やアーティストに対して、高い質=音楽性を求めるようになってきたため全体としての音楽的レベルが大幅に向上してきました。
こうした国内のアーティスト発掘の動きの中で、海外の新人を売り込む立場の洋楽部門は単に自国での評判やメディアや評論家の評価だけを切り口にしたプロモーションでは一般ユーザーの興味や関心を喚起することが出来なくなってきました。従来、洋楽宣伝の基本的な切り口は、アメリカやイギリスといったロック先進国でその作品やアーティストがどの程度の評判を得ているかということが最も重要な情報となります。ソウル系やクラシック系などは現在でも本国での評判が最大のセールス・コピーとなりますが、ロック系については「ジャパン・ロック」の台頭に伴ってライブ中心の「観る」ロックが支持を集め、演奏の実力も重要なファクターとなってきました。レコードだけに頼る洋楽ロックにとっては厳しいマーケットになってきたのです。
「ニュー・アーティスト・ショーケース」は、このような国内のロック市場の動きに対応して海外の実力派新人アーティストのライブ・コンサートを企画し、「ジャパン・ロック」の台頭に対抗して本場の若手アーティスト達の実力を見せようと考えたのです。「ショーケース」とはデパートなどの商品陳列用ガラスケースのことですが、コンサート=ショーと掛けた意味の言葉としてアメリカの音楽業界で使われ始めた用語で、新人には限りませんが、ライブによってアーティストの実力をアピールする方法として定着し始めていました。
この「ショーケース」の形式は、既に人気を獲得しているアーティストの公演=コンサートとは違って、チケット代はタダか、日本流で言う「カンパ」方式か、あるいはライブハウスやクラブのような一律入場料形式のいずれかとされます。どちらにせよ、伝統的な前座バンドのような形式ではなく、観客も始めから無名であることを前提として聴きに来るのですから、自ずと聴衆の評価は厳しいと言われます。
次回は、私に与えられた「新事業開発」のミッションとこの日本初の海外新人の「ショーケース」の顛末をお話しすることにします。
一方で洋楽部門は、限りある販売促進予算の中でリスクの高い新人のデビュー費用を捻出することが徐々に難しくなり始めて来ており、部門はその対策として新しい仕掛けを考えていました。それは業界内の利害関係を見渡して、その力関係と一種の政治力バランスを使って、さらに一般企業や広告代理店、メディアをも巻き込んだ大がかりな新人キャンペーンを展開しようという構想です。そしてその仕掛けの推進と実行のために私達の部隊が駆り出されました。
「ニュー・アーティスト・ショーケース」と名付けられたその新人デビューキャンペーンは、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアの新人ロックグループ5組を一気にデビューさせる目的で、5つのバンドを各々1週間づつ連続的に来日させてライブ・コンサートとプロモーション活動を、東京と大阪で、展開しようというものです。この連続コンサートのために協賛スポンサー、媒体、音楽興業事務所、音楽出版会社、そして各国のCBSをも巻き込み、有料のコンサートにすることで一定の収益を上げながら、デビューに当たってのプロモーション活動も同時に行うことで、従来から100%自己負担で進めてきたプロモーション来日の費用を削減し、あわよくば利潤を上げようという企画だったのです。対象となった5組のアーティストは、いずれも各々の自国でデビューしたて、ないしデビューから1年以内といった新人ばかりで日本国内ではほとんど無名のグループばかりでした。当時(現在でも)、そうした海外の新人アーティストの有料コンサートというものは全く常識はずれと考えられており、チケットが売れる見込みはほとんど無しというのが普通の考え方です。
そこで、この企画が生まれた当時の背景を振り返ってみましょう。日本の音楽界はEPICソニーの誕生の頃から大きく変化していました。「日本のロック」が定着し始め、各地のライブハウスが活性化して続々と新しいグループが登場してきました。レコード会社やプロダクション各社は全国各地のライブハウスをスカウトの場として捉えて専任スタッフを付けて新人の発掘を進めました。各社のオーディションやTVの新人ロックバンド発掘番組も人気を呼んで、いわゆる第3次バンドブームとなったのです。レコード・デビューを目指すロックグループは地元のライブハウスでの活動でファン作りを進めながら、オーディションやイベントへの出演などで評判を上げながらプロへの道を志すのですが、レコード会社やプロダクションのプロデューサーの目に止まるのが先ず第一のステップです。こうしたスタイルは海外では60年代以降当り前の姿でしたが、我が国ではフォークから派生したニューミュージックの時代にすでに同様なスタイルでアーティストの発掘をしていました。60年代半ばの第1次バンドブーム(グループサウンズ)、70年代後半の第2次バンドブーム(フォーク&ニューミュージック)が起こった時にも同じように多数のアマチュアグループが登場しましたが、プロを目指す意欲という点で、第3次ブームのジャパン・ロックの時代はかなり様子が違ってきました。また、そもそも海外生まれのロックについては、聴き手の側も「聴く耳」をもったファンが育ちつつあって、作品やアーティストに対して、高い質=音楽性を求めるようになってきたため全体としての音楽的レベルが大幅に向上してきました。
こうした国内のアーティスト発掘の動きの中で、海外の新人を売り込む立場の洋楽部門は単に自国での評判やメディアや評論家の評価だけを切り口にしたプロモーションでは一般ユーザーの興味や関心を喚起することが出来なくなってきました。従来、洋楽宣伝の基本的な切り口は、アメリカやイギリスといったロック先進国でその作品やアーティストがどの程度の評判を得ているかということが最も重要な情報となります。ソウル系やクラシック系などは現在でも本国での評判が最大のセールス・コピーとなりますが、ロック系については「ジャパン・ロック」の台頭に伴ってライブ中心の「観る」ロックが支持を集め、演奏の実力も重要なファクターとなってきました。レコードだけに頼る洋楽ロックにとっては厳しいマーケットになってきたのです。
「ニュー・アーティスト・ショーケース」は、このような国内のロック市場の動きに対応して海外の実力派新人アーティストのライブ・コンサートを企画し、「ジャパン・ロック」の台頭に対抗して本場の若手アーティスト達の実力を見せようと考えたのです。「ショーケース」とはデパートなどの商品陳列用ガラスケースのことですが、コンサート=ショーと掛けた意味の言葉としてアメリカの音楽業界で使われ始めた用語で、新人には限りませんが、ライブによってアーティストの実力をアピールする方法として定着し始めていました。
この「ショーケース」の形式は、既に人気を獲得しているアーティストの公演=コンサートとは違って、チケット代はタダか、日本流で言う「カンパ」方式か、あるいはライブハウスやクラブのような一律入場料形式のいずれかとされます。どちらにせよ、伝統的な前座バンドのような形式ではなく、観客も始めから無名であることを前提として聴きに来るのですから、自ずと聴衆の評価は厳しいと言われます。
次回は、私に与えられた「新事業開発」のミッションとこの日本初の海外新人の「ショーケース」の顛末をお話しすることにします。
24(第一部)
さて、3回にわたってイギリスのファッショナブルな女性ヴォーカリスト、シャーデーのことを書き続けましたが、私のSMEでの洋楽ディレクターとしての現場の仕事はこの頃で終わり、配置転換による担当替えと管理者としての立場に移っていきました。洋楽セクションの中でも年齢、キャリアの両面から既にベテランの域に入ってきて、現場を離れる時期が来たのです。若いディレクターたちが育ち始め、新しい音楽シーンの中でニュースターも登場していました。
新たに私が命じられた仕事は洋楽部門における「事業開発」です。単にレコードのヒットとアーティストのブレイクを洋楽業界の枠組みの中だけで考えるのではなく、広く媒体や他業種とのタイアップやキャラクター・マーチャンダイジングへと拡大して、音楽の持つメディア的な価値とアーティストの持つ人材的な価値をビジネス化しようという試みです。一方で、こうした音楽とアーティストを使った「付加価値」の創造とともに、内部的には年々増大している宣伝費や販売促進費の節約という目的もありました。それまでにも楽曲のヒット作りのためにTV局やCM業界とのタイアップは日常的に行われていましたが、海外アーティストの場合は、国内のプロダクション業務のように日常的にアーティストの音楽以外での仕事を作りだすというようなことは出来ません。したがって、来日公演を機会として、日本滞在中に通常のプロモーション活動に加えて、TVコマーシャル用キャラクターとしての仕事や音楽番組以外のTV番組へのギャラ付きのゲスト出演、音楽セミナーの開催といった教育関係、自伝や写真集のような出版物の仕事、文化交流使節のような公益事業、さらには老人ホームや孤児院への慰問や地域振興イベントへの参加など、こちらから積極的に仕掛けてゆくこれらの活動は洋楽業界ではほとんど皆無に等しいことでした。
国内のタレントやアーティストの場合、彼らをマネージメントするプロダクションにとっては音楽以外の収入源を必要としないアーティストはごくわずかで、大半はタレント業としてTV局や広告業界からの収入を当てにしています。こうした収入が次の投資資金=新人の発掘資金を確保する手段であり、各プロダクションは自社のお抱えタレントのTV番組レギュラー取りのために、またレギュラー・スポンサー探しのために日夜営業活動を展開しています。海外アーティストの場合は本質的に本業で食べてゆくのが原則であり、日本のような芸能事務所はあまり存在しません。これは日本の興行界の歴史的な背景、つまり芸者さんと置屋の関係が未だにベースとなっているのです。80年代になって日本の音楽界にも欧米的なアーティストの事務所が多数誕生しましたが、それは多分に従来の芸能事務所の体質に対する反発から生まれたもので、海外アーティストのマネージメント会社とは本質的に異なっています。欧米の場合、アーティストのマネージメント会社の役割は主に著作権の管理とレコード会社や興行会社との契約代行業務、そして作品制作の経費とスケジュール管理業務で、日本のプロダクションのような副業的な営業活動は一切行いません。
アーティストは基本的にそれぞれが個人事業者であって、マネージメント会社は彼らに選ばれて雇われる存在です。時には、コンサルタントのような立場でアーティスト側に色々な提案を行いアーティストを雇うケースもありますが、この場合は大半がプロデュース業務を行っている会社でミュージカル業界やイベント業界などがこれに当たります。
このように日本と欧米の音楽業界、芸能界の背景に大きな違いがある中で、海外アーティストを使って極めて日本的なビジネスを「事業開発」するというミッションは、国内の専門事務所との競争の中に入ることでもあって、たいへんに困難な上に、具体的な成果を出しにくい仕事でした。何故このようなセクションが作られたのか、また何故私がそのリーダーに任命されたのか、その背景については追って書いてゆきますが、まず大きな前提として、レコード会社の事業というものが安定的な成長と収益を目指す事業としては極めてリスキーなビジネスである点を見逃してはいけません。海外を例にとるまでもなく、アーティストや楽曲の人気によって業績が大きく変化するレコード・ビジネスは、ヒットの歴史を重ねることによるコンテンツ(カタログ)の充実があって初めて長期的なビジョンが成り立つという性格をもっており、コストと収入のバランスは一つ一つのタイトルの収支だけでは予測できません。一般的に、レコード(今ならCD)の収支バランスは80%近くがマイナスであると言われています。つまり、100種類のタイトルのうち、レコード会社が利益を出している作品は20タイトル程度である、ということで、この20タイトルの中からいくつかの大きなヒットが生まれると、全体として十分な利益が確保できると言うことになります。SMEは高収益企業として89年に東証2部上場を果たしましたが、その他のレコード会社で当時の上場基準を満たすことの出来た会社は皆無でした。それ程に有名なブランドであっても、安定性には乏しい事業なのです。また、日本の音楽は極めて閉鎖的で、市場はほぼ日本国内に限られているという特徴もあります。やはり、言葉の問題が最大の文化障壁かもしれませんが、英米との根本的な違いは「映画業界」にも通じるものがあります。
新たに私が命じられた仕事は洋楽部門における「事業開発」です。単にレコードのヒットとアーティストのブレイクを洋楽業界の枠組みの中だけで考えるのではなく、広く媒体や他業種とのタイアップやキャラクター・マーチャンダイジングへと拡大して、音楽の持つメディア的な価値とアーティストの持つ人材的な価値をビジネス化しようという試みです。一方で、こうした音楽とアーティストを使った「付加価値」の創造とともに、内部的には年々増大している宣伝費や販売促進費の節約という目的もありました。それまでにも楽曲のヒット作りのためにTV局やCM業界とのタイアップは日常的に行われていましたが、海外アーティストの場合は、国内のプロダクション業務のように日常的にアーティストの音楽以外での仕事を作りだすというようなことは出来ません。したがって、来日公演を機会として、日本滞在中に通常のプロモーション活動に加えて、TVコマーシャル用キャラクターとしての仕事や音楽番組以外のTV番組へのギャラ付きのゲスト出演、音楽セミナーの開催といった教育関係、自伝や写真集のような出版物の仕事、文化交流使節のような公益事業、さらには老人ホームや孤児院への慰問や地域振興イベントへの参加など、こちらから積極的に仕掛けてゆくこれらの活動は洋楽業界ではほとんど皆無に等しいことでした。
国内のタレントやアーティストの場合、彼らをマネージメントするプロダクションにとっては音楽以外の収入源を必要としないアーティストはごくわずかで、大半はタレント業としてTV局や広告業界からの収入を当てにしています。こうした収入が次の投資資金=新人の発掘資金を確保する手段であり、各プロダクションは自社のお抱えタレントのTV番組レギュラー取りのために、またレギュラー・スポンサー探しのために日夜営業活動を展開しています。海外アーティストの場合は本質的に本業で食べてゆくのが原則であり、日本のような芸能事務所はあまり存在しません。これは日本の興行界の歴史的な背景、つまり芸者さんと置屋の関係が未だにベースとなっているのです。80年代になって日本の音楽界にも欧米的なアーティストの事務所が多数誕生しましたが、それは多分に従来の芸能事務所の体質に対する反発から生まれたもので、海外アーティストのマネージメント会社とは本質的に異なっています。欧米の場合、アーティストのマネージメント会社の役割は主に著作権の管理とレコード会社や興行会社との契約代行業務、そして作品制作の経費とスケジュール管理業務で、日本のプロダクションのような副業的な営業活動は一切行いません。
アーティストは基本的にそれぞれが個人事業者であって、マネージメント会社は彼らに選ばれて雇われる存在です。時には、コンサルタントのような立場でアーティスト側に色々な提案を行いアーティストを雇うケースもありますが、この場合は大半がプロデュース業務を行っている会社でミュージカル業界やイベント業界などがこれに当たります。
このように日本と欧米の音楽業界、芸能界の背景に大きな違いがある中で、海外アーティストを使って極めて日本的なビジネスを「事業開発」するというミッションは、国内の専門事務所との競争の中に入ることでもあって、たいへんに困難な上に、具体的な成果を出しにくい仕事でした。何故このようなセクションが作られたのか、また何故私がそのリーダーに任命されたのか、その背景については追って書いてゆきますが、まず大きな前提として、レコード会社の事業というものが安定的な成長と収益を目指す事業としては極めてリスキーなビジネスである点を見逃してはいけません。海外を例にとるまでもなく、アーティストや楽曲の人気によって業績が大きく変化するレコード・ビジネスは、ヒットの歴史を重ねることによるコンテンツ(カタログ)の充実があって初めて長期的なビジョンが成り立つという性格をもっており、コストと収入のバランスは一つ一つのタイトルの収支だけでは予測できません。一般的に、レコード(今ならCD)の収支バランスは80%近くがマイナスであると言われています。つまり、100種類のタイトルのうち、レコード会社が利益を出している作品は20タイトル程度である、ということで、この20タイトルの中からいくつかの大きなヒットが生まれると、全体として十分な利益が確保できると言うことになります。SMEは高収益企業として89年に東証2部上場を果たしましたが、その他のレコード会社で当時の上場基準を満たすことの出来た会社は皆無でした。それ程に有名なブランドであっても、安定性には乏しい事業なのです。また、日本の音楽は極めて閉鎖的で、市場はほぼ日本国内に限られているという特徴もあります。やはり、言葉の問題が最大の文化障壁かもしれませんが、英米との根本的な違いは「映画業界」にも通じるものがあります。
23(第一部)
シャーデーは、私が洋楽ディレクターとして担当したアーティストの中で私個人にとって最も大きな影響と結果をもたらしたアーティストでした。別の意味で、例えばマイケル・ジャクソンの場合のように、私に大きな影響と結果をもたらしたアーティスト達は他にもたくさんいましたが、シャーデーのケースは少し事情が違いました。既にシャーデーについては今回で3回にわたって書き続けていますが、私自身にとっては色々な意味で決して忘れることの出来ないアーティストなのです。
シャーデーのアメリカでの成功とその時期に前後したアーティスト自身の変化については前回触れましたが、その延長として、私が日本の一担当者の枠を越えてアーティストのプロデュースに関与するような動きを試みたことは、洋楽ディレクターとしての限界と会社組織の硬直性、海外アーティストに対する日本の会社のコンプレックスをもろに表面化させる結果になりました。
私は、CBS/カリフォルニアのラーキン・アーノルドという大物プロデューサーを訪ねました。彼は1986年当時38歳で、CBSのブラックミュージックカタログ充実のために招かれ、ロスアンゼルスで精力的な仕事をしていました。CBSはマイケル・ジャクソンとジャクソンズの大きな成功に刺激されて西海岸を中心としたブラックミュージックのアーティストの発掘に力を入れるためにラーキン・アーノルドに予算と権限を与えて、それまでのCBS契約アーティストの見直しや新人の発掘、他社からの移籍アーティストの獲得などを進めさせていました。結果として3年余の在任中に大きなヒットを出すことは出来ませんでしたが、彼の存在は当時のブラックミュージック界では極めて大きくなっていました。
私は、その頃新作を発表した直後のビル・ウィザースがロスアンゼルスを中心にライブツアーを始めたことを知り、シャーデーの最も敬愛するビル・ウィザースを一目生で見ておきたいと思って会社にアメリカ出張の申請を出しました。そして同時にラーキン・アーノルドとのミーティングをセッティングしたのです。この出張申請は一筋縄ではいきませんでした。出張の目的とその効果を巡って、上司や管理部などからチェックが入り、結局トップの一言でやっとお許しが出るという始末でした。この時の上司とのやり取りの中で、日本の洋楽ディレクター、一担当者としての限界を感じたのですが、要は日本の一担当者がアーティストや本国CBSに対して何らかの提案や相談を持ちかけることすらすべきではないという考え方です。そこにはお金の計算も絡んできて、出張の経費とその効果、つまり、この出張が具体的にどれだけ会社の売上につながるのかといった議論になってゆくにつれて、私の気持ちは急激に冷めてゆきました。
結果として、私はラーキン・アーノルドに面会し、また彼の取り計らいでビル・ウィザースのコンサートに2晩にわたって招待され、本人とマネージャーにも食事をしながら会うという機会に恵まれました。ラーキンは私の提案に真剣に耳を傾けて、しかし冷静に彼なりの判断を示してくれました。すなわち、こうしたアイディアはあくまでアーティスト同士の直感的なインスピレーションによるケースが多いこと、またプロデューサーの強い意向で実現させるにしても双方の利害に対する客観的な情報が必要なこと、そのプロジェクトの中心になる者は双方の利害に対するリスクをどれだけ取ることが出来るか、といった内容でした。またラーキン自身にその役割を演じるつもりがないかと尋ねたところ、彼はにこやかに微笑しながら、シャーデーには彼自身が全く興味がないと答え、ビル・ウィザースについては、プロデュースは全面的に本人に任せているので直接本人に聞いて欲しい、ということでした。私がビル・ウィザースと彼のマネージャーとの会食をすることになったのは、そうしたラーキンの判断と彼のセッティングによって実現したのです。
私はこの時のラーキン・アーノルドの態度、判断、その後のアクションの全てに感銘を受けました。全てが明快で、的確で、かつとてもスピーディーであったからです。そして、彼の一言、「このアイディアは君の物なのだから君がやるべきことだ」と言われた時にはまさに眼からウロコの心境でした。
ビル・ウィザースとの面会は感動的なものでしたが、残念ながら彼はシャーデーのことを全くと言ってよいほど知らなかったのです。私は、アルバムやカセット、パブリシティ・コピーなどの資料を持っていきましたが、彼のマネージャーが「スムース・オペレーター」を知っていた程度で、ほとんど彼女については知識も情報も関心も持っていませんでした。
ある意味では、ビル・ウィザースはモーリス・ホワイト(第16回参照)とは正反対の人物で、どこか浮世離れした芸術家のイメージが感じられる人物でした。コマーシャリズムとは一線を画した姿勢、実はシャーデーが敬愛する部分もまさにその点だったのかもしれません。
マネージャーからの質問はもっと現実的でした。彼は、シャーデーのコンサートやレコーディングに何らかの形で参加することをシャーデーから依頼されて来たのか、と私に尋ね、そして、その条件は?と聞いてきました。もちろん、その時は未だ私のアイディアの段階であり、シャーデー側から依頼されてきた訳でもない事を伝えましたが、彼の失望の様子はありありと分かりました。
このロスへの出張は、私のビジネス・キャリアの中でもとても大きな経験とショックを受けたものでした。アメリカ流の仕事のやり方、とくに個人の役割についての認識の違い、常に可能性を前提とした議論を行う姿勢、仕事の進め方と結論までのスピードの早さ・・・。現在の私にとってもとても重要な、海外とのビジネスを行う上での貴重な経験を積んだエピソードです。
シャーデーのアメリカでの成功とその時期に前後したアーティスト自身の変化については前回触れましたが、その延長として、私が日本の一担当者の枠を越えてアーティストのプロデュースに関与するような動きを試みたことは、洋楽ディレクターとしての限界と会社組織の硬直性、海外アーティストに対する日本の会社のコンプレックスをもろに表面化させる結果になりました。
私は、CBS/カリフォルニアのラーキン・アーノルドという大物プロデューサーを訪ねました。彼は1986年当時38歳で、CBSのブラックミュージックカタログ充実のために招かれ、ロスアンゼルスで精力的な仕事をしていました。CBSはマイケル・ジャクソンとジャクソンズの大きな成功に刺激されて西海岸を中心としたブラックミュージックのアーティストの発掘に力を入れるためにラーキン・アーノルドに予算と権限を与えて、それまでのCBS契約アーティストの見直しや新人の発掘、他社からの移籍アーティストの獲得などを進めさせていました。結果として3年余の在任中に大きなヒットを出すことは出来ませんでしたが、彼の存在は当時のブラックミュージック界では極めて大きくなっていました。
私は、その頃新作を発表した直後のビル・ウィザースがロスアンゼルスを中心にライブツアーを始めたことを知り、シャーデーの最も敬愛するビル・ウィザースを一目生で見ておきたいと思って会社にアメリカ出張の申請を出しました。そして同時にラーキン・アーノルドとのミーティングをセッティングしたのです。この出張申請は一筋縄ではいきませんでした。出張の目的とその効果を巡って、上司や管理部などからチェックが入り、結局トップの一言でやっとお許しが出るという始末でした。この時の上司とのやり取りの中で、日本の洋楽ディレクター、一担当者としての限界を感じたのですが、要は日本の一担当者がアーティストや本国CBSに対して何らかの提案や相談を持ちかけることすらすべきではないという考え方です。そこにはお金の計算も絡んできて、出張の経費とその効果、つまり、この出張が具体的にどれだけ会社の売上につながるのかといった議論になってゆくにつれて、私の気持ちは急激に冷めてゆきました。
結果として、私はラーキン・アーノルドに面会し、また彼の取り計らいでビル・ウィザースのコンサートに2晩にわたって招待され、本人とマネージャーにも食事をしながら会うという機会に恵まれました。ラーキンは私の提案に真剣に耳を傾けて、しかし冷静に彼なりの判断を示してくれました。すなわち、こうしたアイディアはあくまでアーティスト同士の直感的なインスピレーションによるケースが多いこと、またプロデューサーの強い意向で実現させるにしても双方の利害に対する客観的な情報が必要なこと、そのプロジェクトの中心になる者は双方の利害に対するリスクをどれだけ取ることが出来るか、といった内容でした。またラーキン自身にその役割を演じるつもりがないかと尋ねたところ、彼はにこやかに微笑しながら、シャーデーには彼自身が全く興味がないと答え、ビル・ウィザースについては、プロデュースは全面的に本人に任せているので直接本人に聞いて欲しい、ということでした。私がビル・ウィザースと彼のマネージャーとの会食をすることになったのは、そうしたラーキンの判断と彼のセッティングによって実現したのです。
私はこの時のラーキン・アーノルドの態度、判断、その後のアクションの全てに感銘を受けました。全てが明快で、的確で、かつとてもスピーディーであったからです。そして、彼の一言、「このアイディアは君の物なのだから君がやるべきことだ」と言われた時にはまさに眼からウロコの心境でした。
ビル・ウィザースとの面会は感動的なものでしたが、残念ながら彼はシャーデーのことを全くと言ってよいほど知らなかったのです。私は、アルバムやカセット、パブリシティ・コピーなどの資料を持っていきましたが、彼のマネージャーが「スムース・オペレーター」を知っていた程度で、ほとんど彼女については知識も情報も関心も持っていませんでした。
ある意味では、ビル・ウィザースはモーリス・ホワイト(第16回参照)とは正反対の人物で、どこか浮世離れした芸術家のイメージが感じられる人物でした。コマーシャリズムとは一線を画した姿勢、実はシャーデーが敬愛する部分もまさにその点だったのかもしれません。
マネージャーからの質問はもっと現実的でした。彼は、シャーデーのコンサートやレコーディングに何らかの形で参加することをシャーデーから依頼されて来たのか、と私に尋ね、そして、その条件は?と聞いてきました。もちろん、その時は未だ私のアイディアの段階であり、シャーデー側から依頼されてきた訳でもない事を伝えましたが、彼の失望の様子はありありと分かりました。
このロスへの出張は、私のビジネス・キャリアの中でもとても大きな経験とショックを受けたものでした。アメリカ流の仕事のやり方、とくに個人の役割についての認識の違い、常に可能性を前提とした議論を行う姿勢、仕事の進め方と結論までのスピードの早さ・・・。現在の私にとってもとても重要な、海外とのビジネスを行う上での貴重な経験を積んだエピソードです。
22(第一部)
1985年、シャーデー/SADEの鮮やかなアメリカ・デビューはシングル「スムース・オペレーター」のトップ10入りから始まりました。イースト・コーストからヒットし始めたこの曲は瞬く間に全米に飛び火して、あっという間にベスト5に入り、シングル・ヒットから間もないタイミングでアルバム「ダイヤモンド・ライフ」も発売されて、こちらもグングンとチャートをかけ上りました。イギリス本国や日本での大ヒットのニュースがアメリカのマスメディアの話題となっていたことが大きかったとはいえ、アメリカでのブレイクは予想をはるかに上回るスピードとスケールでした。ファースト・アルバムは米国で200万枚以上のセールスを記録してダブル・プラチナ・アルバムに認定され、シャーデーは一躍国際的なスターとして認知された訳です。
このアメリカでの急激な成功はグループ、スタッフそして本人に大きな変化をもたらすことになりました。米CBSのマーケティング戦略がどのようなものであったかは今となっては定かではありませんが、結果としてその商業的な成功があまり長い期間は続かなかったことを見ると、どこかに無理な要素があったように思えてなりません。シャーデーは、セカンド・アルバム「プロミス」(1986年)では全世界で100万枚以上のセールスを記録しましたが、サード・アルバム「ストロンガー・ザン・プライド」(1987年)ではアルバムの高いクォリティの割にセールスは伸び悩みました。熱狂的な支持者がたくさんいたことは確かですが、ポップなヒット・アーティストというよりは純粋にスタイリッシュなヴォーカリストとしての道を歩み始めて、いわゆるポップ・スターのようなマスコミへのコマーシャルなアクセスを意識的に避けるようになったようです。
こうした傾向は、実はアメリカ・デビューの直後に、というよりも既に日本でのキャンペーン来日の頃に、本人の言葉の端々から感じ取ることができました。マネージメントとレコード会社の考えは明らかに「ヒット志向」でした。実際に、彼らの音楽性やキャラクターは時代のニーズにマッチして、ビジネスとして世界的な成功に結びついたのですからアーティストに対するマネージメントとレコード会社の相対的な力関係は強まっていましたが、シャーデー本人としては、この成功を背景としたビジネス・サイドの強い意向に沿って今後の活動を続けることに対して少なからず反発があったのだと思います。
さて、シャーデーは尊敬するアーティストとしていつもビル・ウィザース/Bill Withers の名を挙げていました。ビル・ウィザースは黒人男性シンガーとして80年代には既にベテランの域に達していた実力派です。彼のヴォーカルの魅力は一言で言えば「渋さ」ですが、落ち着いた雰囲気とジャズのセンスを併せもったソウル・シンガーとして、現在でも一線で活躍しています。80年代の初めにCBS レーベルから質の高いアルバムを何枚か出していましたが、その作品で彼はヴォーカリストとしてだけでなくソングライターとして、またプロデューサーとしてもトップクラスの実力を発揮していました。そして、そのビル・ウィザースやCBSレーベルのその他のブラック系アーティストを一手に担当していたのは、CBSカリフォルニアの敏腕プロデューサーで、かつては自らもミュージシャンとして活躍していたラーキン・アーノルド/Larkin Arnold です。
私は一人のプロデューサーとして、シャーデーのアメリカでの成功の後の段階で、次の展開について色々と考えを巡らせていました。シャーデーの新しい境地をアーティスト的な面とビジネス的な面の両面でアピールし、さらに本格的なトップ・アーティストへと育てていくためには、それまでのCBS/UKとマネージメントのスタッフでは荷が重いのではないかと感じ始めていたのです。そこで思いついたのがラーキン・アーノルドのことでした。彼はシャーデーの担当ではありませんでしたが、ビル・ウィザースにとっては重要なアドバイザー的存在でしたので、私はシャーデーとビル・ウィザースの交流の可能性を探ろうと思ったのです。プロデュース、楽曲の提供、共演、ライブのゲスト、・・・、色々とこの二人のアーティストが直接、間接の関係を築くことが二人のどちらにとっても貴重なキャリアになると同時にコマーシャル的な効果ももたらすのではないかと考えたのです。
このアメリカでの急激な成功はグループ、スタッフそして本人に大きな変化をもたらすことになりました。米CBSのマーケティング戦略がどのようなものであったかは今となっては定かではありませんが、結果としてその商業的な成功があまり長い期間は続かなかったことを見ると、どこかに無理な要素があったように思えてなりません。シャーデーは、セカンド・アルバム「プロミス」(1986年)では全世界で100万枚以上のセールスを記録しましたが、サード・アルバム「ストロンガー・ザン・プライド」(1987年)ではアルバムの高いクォリティの割にセールスは伸び悩みました。熱狂的な支持者がたくさんいたことは確かですが、ポップなヒット・アーティストというよりは純粋にスタイリッシュなヴォーカリストとしての道を歩み始めて、いわゆるポップ・スターのようなマスコミへのコマーシャルなアクセスを意識的に避けるようになったようです。
こうした傾向は、実はアメリカ・デビューの直後に、というよりも既に日本でのキャンペーン来日の頃に、本人の言葉の端々から感じ取ることができました。マネージメントとレコード会社の考えは明らかに「ヒット志向」でした。実際に、彼らの音楽性やキャラクターは時代のニーズにマッチして、ビジネスとして世界的な成功に結びついたのですからアーティストに対するマネージメントとレコード会社の相対的な力関係は強まっていましたが、シャーデー本人としては、この成功を背景としたビジネス・サイドの強い意向に沿って今後の活動を続けることに対して少なからず反発があったのだと思います。
さて、シャーデーは尊敬するアーティストとしていつもビル・ウィザース/Bill Withers の名を挙げていました。ビル・ウィザースは黒人男性シンガーとして80年代には既にベテランの域に達していた実力派です。彼のヴォーカルの魅力は一言で言えば「渋さ」ですが、落ち着いた雰囲気とジャズのセンスを併せもったソウル・シンガーとして、現在でも一線で活躍しています。80年代の初めにCBS レーベルから質の高いアルバムを何枚か出していましたが、その作品で彼はヴォーカリストとしてだけでなくソングライターとして、またプロデューサーとしてもトップクラスの実力を発揮していました。そして、そのビル・ウィザースやCBSレーベルのその他のブラック系アーティストを一手に担当していたのは、CBSカリフォルニアの敏腕プロデューサーで、かつては自らもミュージシャンとして活躍していたラーキン・アーノルド/Larkin Arnold です。
私は一人のプロデューサーとして、シャーデーのアメリカでの成功の後の段階で、次の展開について色々と考えを巡らせていました。シャーデーの新しい境地をアーティスト的な面とビジネス的な面の両面でアピールし、さらに本格的なトップ・アーティストへと育てていくためには、それまでのCBS/UKとマネージメントのスタッフでは荷が重いのではないかと感じ始めていたのです。そこで思いついたのがラーキン・アーノルドのことでした。彼はシャーデーの担当ではありませんでしたが、ビル・ウィザースにとっては重要なアドバイザー的存在でしたので、私はシャーデーとビル・ウィザースの交流の可能性を探ろうと思ったのです。プロデュース、楽曲の提供、共演、ライブのゲスト、・・・、色々とこの二人のアーティストが直接、間接の関係を築くことが二人のどちらにとっても貴重なキャリアになると同時にコマーシャル的な効果ももたらすのではないかと考えたのです。
21(第一部)
80年代の半ば頃、洋楽ポップスの世界では多くのイギリスのアーティストが世界的にブレイクしました。ワム! (ジョージ・マイケル)、カルチャークラブ、シンプリーレッド、ABC、ハワード・ジョーンズ、ユーリズミックス・・・。個性的で魅力的なアーティストがどんどん登場して、アメリカや日本でもヒットを飛ばし、アメリカのマスメディアでは"British Invasion"といわれるぐらいに多数のイギリス出身のアーティストがチャートの上位を占めていました。
70年代の後半、イギリスでは不景気による社会不安と失業問題が深刻で、ポップスの世界でもパンク&ニューウェイブのアーティストが登場して政治的、メッセージ的な新しいロックミュージックの表現を模索する動きが活発になりました。それは、アメリカの60年代のベトナム反戦を契機として生まれたサイケデリック・ロックやフラワームーブメントなどと共通した背景を持っており、音楽のメッセージ性と社会性を通して新しい表現文化が生まれ始める契機となりました。パンク・ロックの破壊性と過激性は、60年代アメリカン・ロックのドラッグとの結びつきとは違って、暴力的なバイオレンスと結びついていったように思われます。
このパンクをきっかけとして新しいロック表現がポップスにも大きな影響を与え、特にサウンドやリズムのアイディアとして第3世界の音楽、とりわけジャマイカやプエルトリコの民族音楽との融合によって、後にレゲエの世界的な大ブームが起こります。70年代のブリティッシュ・パンクのトップ・アーティストといわれるセックス・ピストルズ、クラッシュ、ストラングラーズ等は多くのレゲエ・ナンバーを作っており、ボブ・マーレーを筆頭とする第3世界のミュージシャンとの密接な関係もよく知られています。
80年代の半ばになるとイギリスは徐々に経済も回復し、音楽業界もパンクやニューウェイブの刺激を受けた新しいアーティストの台頭によって世界的なスターを登場させました。私の場合はCBS/UKのアーティスト、特にワム!とシャーデーは今でも忘れられないアーティストです。
この2組のアーティストには重要な共通項があります。ポーカリストで主役の二人、ジョージ・マイケルとシャーデーが共にアメリカの60-70年代の黒人音楽に強い影響を受けていることです。ジョージ・マイケルはモータウンやフィラデルフィア・ソウルのソフトな感覚を身に付けていて、一方シャーデーはブルックリン・サウンドやアトランティツク・ソウルの影響を受けています。また共にミュージシャンや音楽好きの家系の育ちであり、子供時代からアダルトなアメリカ音楽に接して来たことから、二人とも年令の割にセクシーでソフィストケートされた歌い方を身に付けていました。二人のデビューの仕方は全く正反対で、それぞれはアイドルとジャズ系グループというイメージで登場しましたが、実は多くの点で共通するセンスがあったのです。
私はシャーデーの担当となったのですが、実はイギリスでのデビュー当時から特に注目していたと言う訳ではありませんでした。私の担当ジャンルは基本的にはアメリカの黒人音楽であったためにイギリスのアーティストには余り注意を払っていなかったのです。CBS/UKのリストの中にも何人かの才能ある黒人アーティスト(エディ・グラント、ビリー・オーシャンなど)がおり、彼等も私の担当ではあったのですが、シャーデーのデビューにはほとんど気が付かない状態でした。ナイジェリアの出身であることや彼女を取り巻くバンドのメンバー達がいずれもイギリスのスタジオ・ミュージシャンとしてハイレベルの実力を持っていたことなど、バイオグラフィーに記されていたことを実感したのは、デビューから半年以上も経ってからの事でした。
シャーデーは83年の秋に"Yuor Love Is King"というシングルでデビュー、このミディアムスローのラプソングは全英チャートをじわじわと上がってついにベストテン入りします。CBS/UKはプライオリティ・アーティストとしてのキャンペーンを開始、84年の初めから全英クラブツアーをスタートさせました。そして、同じ頃にロンドンに在住する一人の日本人カメラマンから手紙をもらったのです。彼はブリティッシュ・ロックをこよなく愛し、日本にイギリスのアーティストたちを多数紹介してきたユニークなカメラマンで、日本のロック雑誌や音楽メディアなどにしばしば彼の写真やコンサート・レポート等を発表していました。
その彼がシャーデーにいち早く注目して、日本でも必ずブレイクすると確信して私達に手紙をくれたのです。彼はシャーデーのツアーに自主的に同行して、ライブやオフの写真を撮り続けていました。その写真はとても印象的で、個性豊かなシャーデーの魅力、グループ全体のオシャレでスマートなイメージを見事に捉えたものでした。この彼の手紙をきっかけとして、私は初めてシャーデーの存在をはっきりと認識したのです。私は彼の勧めに応じて、早速CBS/UKを通じてシャーデーのライブを観に行くことにしました。
ツアーの予定地とCBS/UKのあるロンドン、またそのカメラマン、トシ矢島氏のスケジュール等を調整して、私は84年3月にロンドンを経由してエジンバラへ赴きました。まだ雪が残る市街、第2次大戦の戦火を免れた建物がイギリスの古い街の佇まいを漂わせているエジンバラのダウンタウンの煤けたようなビルの地下にあるクラブハウスで、シャーデーのライブは午後9時頃に始まりました。レコードのリリースはデビュー・シングル1枚にも関わらず、既に相当の知名度があったのか、ライブは最初から熱狂的な雰囲気の中でスタート、私はその反響に驚くと同時に、自分の認識不足と世界の広さ、凄さを改めて思い知らされました。私はそのコンサートの事前にアルバムのデモテープで3曲を聞いていましたが、実際のステージでは15曲余りが演奏され、全体的に私の先入観よりもずっとホットでエネルギッシュな内容でした。クールでスタイリッシュ、そしてアンニュイなシャーデーの雰囲気とアーバン・ジャズ・コンテンポラリーのサウンド、というオシャレなグループ・イメージが現在でも"SADE"の一般的な捉えられ方でしょうが、この時のライブでのプレイぶりはメンバー全体の若々しさが前面に出ていて、とても気持ちの良い"ノリ"に溢れていました。
ライブの終了後に矢島氏にメンバーを紹介され、初めてシャーデー本人と面会しましたが、その晩は初対面ということもあって彼女はほとんど何も話しませんでした。代わりにバンドのメンバー達が私に次々に日本の事を質問をし、矢島氏を通じてかなり色々な情報が伝わっていることを実感しました。矢島氏のような存在が日本への海外の新しいアーティストの発掘や紹介に大きな影響力をもっていること、また彼のように日本を離れて現地での厳しい競争の中でカメラマンとして欧米のトップクラスのアーティストと日常的に接触しアーティストの信頼を得て活動を続けることの凄さを見せつけられました。やがて矢島氏は"SADE"の専属オフィシャル・フォトグラファーとして認められ、アルバムのジャケットをはじめとしてメイン・ビジュアルのほとんどを手掛けることになりますが、世界的なスターとして育ってゆく過程を共に歩んでゆく立場として大きな喜びと責任を感じただろうと思います。
現在では欧米で活躍する日本人の数はあらゆる分野で飛躍的に多くなってきましたが、自分の感性と技術だけを武器として活動するクリエーターとしての生き方は日本の国内だけであっても大変な努力と情熱、そして才能が必要です。さらに「運」や「ツキ」もなければとても成功は出来ないでしょう。まして欧米の業界には世界中から有能な人々が集まっています。矢島氏とシャーデーの関係はカメラマンとミュージシャンのお互いの感性がマッチし、双方にとってクリエイティブな刺激を得られる理想的な組み合わせが実現されていたようでした。私は矢島氏を通して改めて日本と欧米のショービジネスのあり方の違いやクリエーターの生き様の凄さ、素晴らしさを知りました。
70年代の後半、イギリスでは不景気による社会不安と失業問題が深刻で、ポップスの世界でもパンク&ニューウェイブのアーティストが登場して政治的、メッセージ的な新しいロックミュージックの表現を模索する動きが活発になりました。それは、アメリカの60年代のベトナム反戦を契機として生まれたサイケデリック・ロックやフラワームーブメントなどと共通した背景を持っており、音楽のメッセージ性と社会性を通して新しい表現文化が生まれ始める契機となりました。パンク・ロックの破壊性と過激性は、60年代アメリカン・ロックのドラッグとの結びつきとは違って、暴力的なバイオレンスと結びついていったように思われます。
このパンクをきっかけとして新しいロック表現がポップスにも大きな影響を与え、特にサウンドやリズムのアイディアとして第3世界の音楽、とりわけジャマイカやプエルトリコの民族音楽との融合によって、後にレゲエの世界的な大ブームが起こります。70年代のブリティッシュ・パンクのトップ・アーティストといわれるセックス・ピストルズ、クラッシュ、ストラングラーズ等は多くのレゲエ・ナンバーを作っており、ボブ・マーレーを筆頭とする第3世界のミュージシャンとの密接な関係もよく知られています。
80年代の半ばになるとイギリスは徐々に経済も回復し、音楽業界もパンクやニューウェイブの刺激を受けた新しいアーティストの台頭によって世界的なスターを登場させました。私の場合はCBS/UKのアーティスト、特にワム!とシャーデーは今でも忘れられないアーティストです。
この2組のアーティストには重要な共通項があります。ポーカリストで主役の二人、ジョージ・マイケルとシャーデーが共にアメリカの60-70年代の黒人音楽に強い影響を受けていることです。ジョージ・マイケルはモータウンやフィラデルフィア・ソウルのソフトな感覚を身に付けていて、一方シャーデーはブルックリン・サウンドやアトランティツク・ソウルの影響を受けています。また共にミュージシャンや音楽好きの家系の育ちであり、子供時代からアダルトなアメリカ音楽に接して来たことから、二人とも年令の割にセクシーでソフィストケートされた歌い方を身に付けていました。二人のデビューの仕方は全く正反対で、それぞれはアイドルとジャズ系グループというイメージで登場しましたが、実は多くの点で共通するセンスがあったのです。
私はシャーデーの担当となったのですが、実はイギリスでのデビュー当時から特に注目していたと言う訳ではありませんでした。私の担当ジャンルは基本的にはアメリカの黒人音楽であったためにイギリスのアーティストには余り注意を払っていなかったのです。CBS/UKのリストの中にも何人かの才能ある黒人アーティスト(エディ・グラント、ビリー・オーシャンなど)がおり、彼等も私の担当ではあったのですが、シャーデーのデビューにはほとんど気が付かない状態でした。ナイジェリアの出身であることや彼女を取り巻くバンドのメンバー達がいずれもイギリスのスタジオ・ミュージシャンとしてハイレベルの実力を持っていたことなど、バイオグラフィーに記されていたことを実感したのは、デビューから半年以上も経ってからの事でした。
シャーデーは83年の秋に"Yuor Love Is King"というシングルでデビュー、このミディアムスローのラプソングは全英チャートをじわじわと上がってついにベストテン入りします。CBS/UKはプライオリティ・アーティストとしてのキャンペーンを開始、84年の初めから全英クラブツアーをスタートさせました。そして、同じ頃にロンドンに在住する一人の日本人カメラマンから手紙をもらったのです。彼はブリティッシュ・ロックをこよなく愛し、日本にイギリスのアーティストたちを多数紹介してきたユニークなカメラマンで、日本のロック雑誌や音楽メディアなどにしばしば彼の写真やコンサート・レポート等を発表していました。
その彼がシャーデーにいち早く注目して、日本でも必ずブレイクすると確信して私達に手紙をくれたのです。彼はシャーデーのツアーに自主的に同行して、ライブやオフの写真を撮り続けていました。その写真はとても印象的で、個性豊かなシャーデーの魅力、グループ全体のオシャレでスマートなイメージを見事に捉えたものでした。この彼の手紙をきっかけとして、私は初めてシャーデーの存在をはっきりと認識したのです。私は彼の勧めに応じて、早速CBS/UKを通じてシャーデーのライブを観に行くことにしました。
ツアーの予定地とCBS/UKのあるロンドン、またそのカメラマン、トシ矢島氏のスケジュール等を調整して、私は84年3月にロンドンを経由してエジンバラへ赴きました。まだ雪が残る市街、第2次大戦の戦火を免れた建物がイギリスの古い街の佇まいを漂わせているエジンバラのダウンタウンの煤けたようなビルの地下にあるクラブハウスで、シャーデーのライブは午後9時頃に始まりました。レコードのリリースはデビュー・シングル1枚にも関わらず、既に相当の知名度があったのか、ライブは最初から熱狂的な雰囲気の中でスタート、私はその反響に驚くと同時に、自分の認識不足と世界の広さ、凄さを改めて思い知らされました。私はそのコンサートの事前にアルバムのデモテープで3曲を聞いていましたが、実際のステージでは15曲余りが演奏され、全体的に私の先入観よりもずっとホットでエネルギッシュな内容でした。クールでスタイリッシュ、そしてアンニュイなシャーデーの雰囲気とアーバン・ジャズ・コンテンポラリーのサウンド、というオシャレなグループ・イメージが現在でも"SADE"の一般的な捉えられ方でしょうが、この時のライブでのプレイぶりはメンバー全体の若々しさが前面に出ていて、とても気持ちの良い"ノリ"に溢れていました。
ライブの終了後に矢島氏にメンバーを紹介され、初めてシャーデー本人と面会しましたが、その晩は初対面ということもあって彼女はほとんど何も話しませんでした。代わりにバンドのメンバー達が私に次々に日本の事を質問をし、矢島氏を通じてかなり色々な情報が伝わっていることを実感しました。矢島氏のような存在が日本への海外の新しいアーティストの発掘や紹介に大きな影響力をもっていること、また彼のように日本を離れて現地での厳しい競争の中でカメラマンとして欧米のトップクラスのアーティストと日常的に接触しアーティストの信頼を得て活動を続けることの凄さを見せつけられました。やがて矢島氏は"SADE"の専属オフィシャル・フォトグラファーとして認められ、アルバムのジャケットをはじめとしてメイン・ビジュアルのほとんどを手掛けることになりますが、世界的なスターとして育ってゆく過程を共に歩んでゆく立場として大きな喜びと責任を感じただろうと思います。
現在では欧米で活躍する日本人の数はあらゆる分野で飛躍的に多くなってきましたが、自分の感性と技術だけを武器として活動するクリエーターとしての生き方は日本の国内だけであっても大変な努力と情熱、そして才能が必要です。さらに「運」や「ツキ」もなければとても成功は出来ないでしょう。まして欧米の業界には世界中から有能な人々が集まっています。矢島氏とシャーデーの関係はカメラマンとミュージシャンのお互いの感性がマッチし、双方にとってクリエイティブな刺激を得られる理想的な組み合わせが実現されていたようでした。私は矢島氏を通して改めて日本と欧米のショービジネスのあり方の違いやクリエーターの生き様の凄さ、素晴らしさを知りました。
20(第一部)
今回は、前回まで2回に渡ってご紹介したジョージ・デュークとのエピソードの中にも登場した天才ベーシスト、スタンリー・クラークとのお話を書きたいと思います。
スタンリー・クラーク/Stanley Clarkeは、70年代の前半にデビューしたベーシストの中でも飛び抜けた才能の持ち主で、チック・コリア、マイルス・デイビスらとのセッションで世界的に注目を集めました。驚異的なテクニックはもちろんですが、音楽性の豊かさ、高い作曲能力から生み出されるメロディアスなベースは、従来のリズム・プレイヤーとしてのベーシストの立場を根底から覆すほどの強いインパクトを与えました。彼のプレイの基本はベースと言う楽器をリード楽器の一つとして捉えている点で、過去のベーシストとは一線を画しています。それまでのジャズ・インプロビゼーション(ジャズの即興演奏)においてもベースの即興パートはもちろん存在していましたが、それはあくまでもリズム楽器としての位置付けでした。特にアコースティック・ベースの音域特性から、メインパートの立場はなかなか取りにくく、チャールズ・ミンガスやロン・カーターといったバンド・リーダーとしての才能を持ったベーシスト以外にはベースのリーダー・アルバムはほとんどありません。一方で、エレキ・ベースのジャズ・プレイヤーはフェンダー社製の素晴らしい楽器が登場するまではほとんど存在せず、ライブとレコーディングのどちらにも対応できる楽器としての表現力が確立する70年代の前半になって、ベテランのベーシストもやっとエレキ・ベースを使うようになりました。
スタンリー・クラークはアコースティック・ベースのプレイヤーとしても素晴らしい技術と表現力をもっていますが、なんと言ってもエレキ・ベースの可能性を驚異的なテクニックで表現してみせた最初の人物であり、新しいジャズ/クロスオーバー・ミュージック/フュージョンの旗手として、チック・コリアのエレクトリック・ピアノとのコラボレーションで一世を風靡することになります。リターン・トゥ・フォーエバー/Return To Forever の衝撃的なデビューアルバムはジャズ・シーンに大きな転機を促した作品で、24才の天才ベーシスト、スタンリー・クラークを世界に知らしめた歴史的な作品です。
私がこのアルバムを聞いたのは大学2年生の時で、神戸のシャズ喫茶でアルバイトをしている時でした。実はこのアルパム以前にスタンリー・クラークの存在は既に知っていました、アコースティック・ベースにエレクトリック・アダプターを取り付けたスタイルで一聴して今までとは違うスタイルであることが分かるプレイぶりで大変印象深かった思い出があります。でも、チック・コリアのこの新作は余りにも華やかで、斬新でした。グループとしてのサウンドの新しさに加えて、スタンリーの驚異的なテクニック、とくに高音域での目まぐるしい程のスピードに乗ったメロディアスなプレイは圧倒的なインバクトを持っていて、当時、お店のリクエスト・チャートのトップを数カ月間独占していました。
私がEPICソニーに参加した時には、スタンリー・クラークはEPICレーベルの数少ないジャズ系アーティストの中で突出して有名な一人でした。実はEPICレーベルは、70年代の半ば頃、マイケル・ジャクソンとジャクソンズを筆頭として、そこそこの有名プラック・アーティストを抱えていましたが、ビジネスとしてはあまり成功していなかったのです。スタンリー・クラークも知名度の割には日米共にセールス的には大したことがなく、アーティストとしての実力は認められながらもレコード・セールスの面ではB級以下でした。でも私にとってはリターン・トゥ・フォーエバー以来の憧れのアーティストの一人であり、いずれ彼の担当者になるなどとは思ってもみなかったビッグな存在でした。
78年、スタンリーは田園コロシアムで開かれたサマー・ジャズ・フェスティバルに出演するために来日しました。私は当時の担当者と共にそのコンサートを観に出かけ、楽屋で初めて彼と対面しました。身長190cm余りの引き締まった体躯、無精髭をはやして全身真っ白なステージ衣装で現れた彼の大きな手! 間近で見るスタンリーはやはり大物の風格を漂わせ、同行して来た奥さんはプロンドの白人女性で、それにも驚きましたが、人柄はどこかシャイで人なつこさを持っていて大変に好印象でした。その時はほんの一言二言の挨拶を交わした程度でしたが、その後、私が直接の担当者になってからはジョージ・デューク同様かなり深い交流を持つようになりました。
80年にロスを訪れた時に、私はスタンリーに連絡を取り近況を聞かせてもらおうと思い、CBSの担当者に面会を申し入れたところ、彼は私の事を覚えていて快く自宅を訪問するようにと言ってくれました。CBSの担当者が住所のメモを渡してくれて、私はタクシーを手配し一人で彼の自宅を訪ねたのですが、それはハリウッドのスターたちの豪邸の建ち並ぶビバリーヒルズのど真ん中でプール、バスケットコート、リハーサル・スタジオを備えた素晴らしい建物でした。
私はリビングに通され、3人の子供達にも紹介されて、例のブロンドの奥さんも交えてのアフタヌーン・ティーに招待されていたのですが、私はそうしたイギリス的な習慣の事も全く知らず、まるで大統領に面会する日本の新聞社の駐在員のようにガチガチに緊張してしまっていたことを思い出します。
その後、彼との個人的な交流は度重なり、年に一、二度は面会してジャズとクラシックの関係の事、音楽教育と教材ビジネスのこと、ジョージ・デュークとの新しいプロジェクトの事、その他にも沢山の事を話し合ったり、相談したりしました。彼はほぼ毎年のように来日し、コンサートばかりでなく、映画音楽の制作、日本の若手ミュージシャンとのセミナー・セッション、音楽教育用のビデオ制作、CM音楽の録音など精力的に活動しました。アメリカでの活動と共に日本を大変に愛しているミュージシャンなのです。
彼との最もおかしなエピソードといえば「高麗人参騒動」でしょう。その頃、彼は東洋医学や漢方薬に凝っていて、来日の度に私に指圧や太極拳の手配を頼んで来たのですが、ある時「高麗人参」を大量に買いたいと言ったのです。「高麗人参」は日本でも高価ですが、アメリカでは入手自体が困難な上に大変に高価なもので、その貴重価値もあってスタンリーは"Magic Jinsen"と表現して私に購入の方法を尋ねたのです。仕事が終わって帰国までの1日オフの日、私は事前に下調べをして何軒かの漢方薬専門店に問い合わせて、二人で「高麗人参」を買いに出かけました。まず、門前仲町、ここには東京江東区の下町で有名な漢方薬屋があり、以前に私が住んでいた場所で馴染みがありました。そこに着くと同時にスタンリーは満面に笑みを浮かべて、まるで子供が玩具屋へ言った時のように半ば興奮状態で手当りしだい目に付くものについて質問を浴びせて来るのです。そして、お目当ての高麗人参はもちろんあったのですが、皆さんも御存じのように「高麗人参エキス」を抽出するために焼酎やアルコールに漬けた丸い大きな瓶詰めに目が行ったのです。店主も面白半分に、その酒を試飲させてくれるということになったのですが、実はスタンリーは大変に酒に弱いのです。私がそのことを店主に告げると店主はザラメを入れて彼に勧めました。普段でも彼は酒に弱いくせに勧められると断わらない性格で、この時もショットグラス一杯をを一気に流し込んでしまいました。御機嫌の彼はその瓶詰めの作り方を教えろとせがみ、焼酎も買いたいと言いだす始末。結局、最初のこの店で1時間半余りを過ごして在庫のすべてを買う事になりました。店主が驚いて計算すると、当時の金額でおよそ20万円余。ところが彼は現金を持っておらずクレジットカードで支払うつもりだったのです。その頃の漢方薬屋ではクレジットカードを扱っている所などあるはずもなく、結局私の名刺を置いて後から請求書を送ってもらうことになりました。この店を出る頃にホロ酔い状態のスタンリーは、つぎはどこだと私に尋ね、つぎの浅草のお店でもまた一杯御馳走になり、またまた在庫一掃10万円也。最後に京橋のお店でも10万円分を追加して、やっと満足したようで、「お前も東京も最高だ!」などと言って、今までに見せたこともないような笑顔を浮かべホテルへ御帰還です。
ホテルでは奥さんが心配そうに待っていました。総額で40万円余り、それでも大した量はありません。彼は楽しそうに一部始終を奥さんに話して聞かせました。実は彼の奥さんはかなりの実業家で、当時アメリカ西海岸地域のルイ・ヴィトン製品の独占販売権を持っていて、ビバリーヒルズのお金持ち向けに手広く商売をしていたらしく、この「高麗人参」の支払の事を聞くとすぐさまその場で小切手を切って私に渡してくれました。
とにかく私にとっては、スタンリー・クラーク夫妻は色々な面でびっくりさせられたことが多かった二人だと思います。
スタンリー・クラーク/Stanley Clarkeは、70年代の前半にデビューしたベーシストの中でも飛び抜けた才能の持ち主で、チック・コリア、マイルス・デイビスらとのセッションで世界的に注目を集めました。驚異的なテクニックはもちろんですが、音楽性の豊かさ、高い作曲能力から生み出されるメロディアスなベースは、従来のリズム・プレイヤーとしてのベーシストの立場を根底から覆すほどの強いインパクトを与えました。彼のプレイの基本はベースと言う楽器をリード楽器の一つとして捉えている点で、過去のベーシストとは一線を画しています。それまでのジャズ・インプロビゼーション(ジャズの即興演奏)においてもベースの即興パートはもちろん存在していましたが、それはあくまでもリズム楽器としての位置付けでした。特にアコースティック・ベースの音域特性から、メインパートの立場はなかなか取りにくく、チャールズ・ミンガスやロン・カーターといったバンド・リーダーとしての才能を持ったベーシスト以外にはベースのリーダー・アルバムはほとんどありません。一方で、エレキ・ベースのジャズ・プレイヤーはフェンダー社製の素晴らしい楽器が登場するまではほとんど存在せず、ライブとレコーディングのどちらにも対応できる楽器としての表現力が確立する70年代の前半になって、ベテランのベーシストもやっとエレキ・ベースを使うようになりました。
スタンリー・クラークはアコースティック・ベースのプレイヤーとしても素晴らしい技術と表現力をもっていますが、なんと言ってもエレキ・ベースの可能性を驚異的なテクニックで表現してみせた最初の人物であり、新しいジャズ/クロスオーバー・ミュージック/フュージョンの旗手として、チック・コリアのエレクトリック・ピアノとのコラボレーションで一世を風靡することになります。リターン・トゥ・フォーエバー/Return To Forever の衝撃的なデビューアルバムはジャズ・シーンに大きな転機を促した作品で、24才の天才ベーシスト、スタンリー・クラークを世界に知らしめた歴史的な作品です。
私がこのアルバムを聞いたのは大学2年生の時で、神戸のシャズ喫茶でアルバイトをしている時でした。実はこのアルパム以前にスタンリー・クラークの存在は既に知っていました、アコースティック・ベースにエレクトリック・アダプターを取り付けたスタイルで一聴して今までとは違うスタイルであることが分かるプレイぶりで大変印象深かった思い出があります。でも、チック・コリアのこの新作は余りにも華やかで、斬新でした。グループとしてのサウンドの新しさに加えて、スタンリーの驚異的なテクニック、とくに高音域での目まぐるしい程のスピードに乗ったメロディアスなプレイは圧倒的なインバクトを持っていて、当時、お店のリクエスト・チャートのトップを数カ月間独占していました。
私がEPICソニーに参加した時には、スタンリー・クラークはEPICレーベルの数少ないジャズ系アーティストの中で突出して有名な一人でした。実はEPICレーベルは、70年代の半ば頃、マイケル・ジャクソンとジャクソンズを筆頭として、そこそこの有名プラック・アーティストを抱えていましたが、ビジネスとしてはあまり成功していなかったのです。スタンリー・クラークも知名度の割には日米共にセールス的には大したことがなく、アーティストとしての実力は認められながらもレコード・セールスの面ではB級以下でした。でも私にとってはリターン・トゥ・フォーエバー以来の憧れのアーティストの一人であり、いずれ彼の担当者になるなどとは思ってもみなかったビッグな存在でした。
78年、スタンリーは田園コロシアムで開かれたサマー・ジャズ・フェスティバルに出演するために来日しました。私は当時の担当者と共にそのコンサートを観に出かけ、楽屋で初めて彼と対面しました。身長190cm余りの引き締まった体躯、無精髭をはやして全身真っ白なステージ衣装で現れた彼の大きな手! 間近で見るスタンリーはやはり大物の風格を漂わせ、同行して来た奥さんはプロンドの白人女性で、それにも驚きましたが、人柄はどこかシャイで人なつこさを持っていて大変に好印象でした。その時はほんの一言二言の挨拶を交わした程度でしたが、その後、私が直接の担当者になってからはジョージ・デューク同様かなり深い交流を持つようになりました。
80年にロスを訪れた時に、私はスタンリーに連絡を取り近況を聞かせてもらおうと思い、CBSの担当者に面会を申し入れたところ、彼は私の事を覚えていて快く自宅を訪問するようにと言ってくれました。CBSの担当者が住所のメモを渡してくれて、私はタクシーを手配し一人で彼の自宅を訪ねたのですが、それはハリウッドのスターたちの豪邸の建ち並ぶビバリーヒルズのど真ん中でプール、バスケットコート、リハーサル・スタジオを備えた素晴らしい建物でした。
私はリビングに通され、3人の子供達にも紹介されて、例のブロンドの奥さんも交えてのアフタヌーン・ティーに招待されていたのですが、私はそうしたイギリス的な習慣の事も全く知らず、まるで大統領に面会する日本の新聞社の駐在員のようにガチガチに緊張してしまっていたことを思い出します。
その後、彼との個人的な交流は度重なり、年に一、二度は面会してジャズとクラシックの関係の事、音楽教育と教材ビジネスのこと、ジョージ・デュークとの新しいプロジェクトの事、その他にも沢山の事を話し合ったり、相談したりしました。彼はほぼ毎年のように来日し、コンサートばかりでなく、映画音楽の制作、日本の若手ミュージシャンとのセミナー・セッション、音楽教育用のビデオ制作、CM音楽の録音など精力的に活動しました。アメリカでの活動と共に日本を大変に愛しているミュージシャンなのです。
彼との最もおかしなエピソードといえば「高麗人参騒動」でしょう。その頃、彼は東洋医学や漢方薬に凝っていて、来日の度に私に指圧や太極拳の手配を頼んで来たのですが、ある時「高麗人参」を大量に買いたいと言ったのです。「高麗人参」は日本でも高価ですが、アメリカでは入手自体が困難な上に大変に高価なもので、その貴重価値もあってスタンリーは"Magic Jinsen"と表現して私に購入の方法を尋ねたのです。仕事が終わって帰国までの1日オフの日、私は事前に下調べをして何軒かの漢方薬専門店に問い合わせて、二人で「高麗人参」を買いに出かけました。まず、門前仲町、ここには東京江東区の下町で有名な漢方薬屋があり、以前に私が住んでいた場所で馴染みがありました。そこに着くと同時にスタンリーは満面に笑みを浮かべて、まるで子供が玩具屋へ言った時のように半ば興奮状態で手当りしだい目に付くものについて質問を浴びせて来るのです。そして、お目当ての高麗人参はもちろんあったのですが、皆さんも御存じのように「高麗人参エキス」を抽出するために焼酎やアルコールに漬けた丸い大きな瓶詰めに目が行ったのです。店主も面白半分に、その酒を試飲させてくれるということになったのですが、実はスタンリーは大変に酒に弱いのです。私がそのことを店主に告げると店主はザラメを入れて彼に勧めました。普段でも彼は酒に弱いくせに勧められると断わらない性格で、この時もショットグラス一杯をを一気に流し込んでしまいました。御機嫌の彼はその瓶詰めの作り方を教えろとせがみ、焼酎も買いたいと言いだす始末。結局、最初のこの店で1時間半余りを過ごして在庫のすべてを買う事になりました。店主が驚いて計算すると、当時の金額でおよそ20万円余。ところが彼は現金を持っておらずクレジットカードで支払うつもりだったのです。その頃の漢方薬屋ではクレジットカードを扱っている所などあるはずもなく、結局私の名刺を置いて後から請求書を送ってもらうことになりました。この店を出る頃にホロ酔い状態のスタンリーは、つぎはどこだと私に尋ね、つぎの浅草のお店でもまた一杯御馳走になり、またまた在庫一掃10万円也。最後に京橋のお店でも10万円分を追加して、やっと満足したようで、「お前も東京も最高だ!」などと言って、今までに見せたこともないような笑顔を浮かべホテルへ御帰還です。
ホテルでは奥さんが心配そうに待っていました。総額で40万円余り、それでも大した量はありません。彼は楽しそうに一部始終を奥さんに話して聞かせました。実は彼の奥さんはかなりの実業家で、当時アメリカ西海岸地域のルイ・ヴィトン製品の独占販売権を持っていて、ビバリーヒルズのお金持ち向けに手広く商売をしていたらしく、この「高麗人参」の支払の事を聞くとすぐさまその場で小切手を切って私に渡してくれました。
とにかく私にとっては、スタンリー・クラーク夫妻は色々な面でびっくりさせられたことが多かった二人だと思います。
19(第一部)
アメリカのキーポード奏者/プロデューサーであるジョージ・デュークのお話がだいぶ長くなってきました。というのも、それだけ私にとっては大切な人物であり、また貴重な経験をさせてくれた素晴しい人であるからです。
彼の日本初(実は世界初)の単独コンサートツアーは、1984年の10月に東京、大阪、名古屋、札幌で計5回開かれました。メンバーはジョージ・デューク(リーダー/キーボード/ボーカル)、ポール・ジャクソンJr.(ギター)、ルイス・ジョンソン(ベース) 、スティーブ・フェローン(ドラムス)の4人の大物スター・プレイヤーに若手のギタリストとパーカッション、バックボーカルを加えた超豪華メンバーで、さしずめ「ジョージ・デューク・オールスターズ」ともいうべき編成のバンドでした。私は来日メンバーのリストが送られてきた時に思わず目を疑ってしまうほど驚いた記憶があります。さらに、来日スケジュールの最終的な詰めの段階で、それに輪をかけて驚くべき 連絡が入りました。2人のゲスト・ボーカリストを連れて行く、というのです。その2人とは、当時フィル・コリンズとの共演で全米 No.1のヒットを飛ばしていたアース・ウインド&ファイアーのフィリップ・ベイリーとジョージのプロデュースで新作を発表したばかりのデニース・ウィリアムスだったのです。
さかのぼること1年前、コンサートの計画を話すためにロスへ飛んだ時に、私はジョ ージにいろいろな提案と自分の「夢」を語りました。その中でジョージのボーカルについての私の考えを率直に述べたのです。私はボーカリストとしてのジョージの力量の限界とコンサートの成功のためには看板になるボーカリストが必要であることを説きました。こうした意見を面と向かって言うことはスターに対してはたいへん失礼なことですが、私たちは彼にとって初めてのリーダー・コンサートの実現のために何時間も真剣に腹を割って話しあったのです。彼は最終的に私の意見を聞き入れて、ゲスト・ボー カリストを選定し日本に連れて来るように動いてくれたのです。そのゲストがなんとフィリップ・ベイリーとデニース・ウィリアムスという願ってもないビック・ネームであり、さらにフィリップの単独来日もデニースの来日もいずれも初めてのことで、ファンにとってはまさに「夢の共演」が実現したのです。
私は彼のイメージ作りの基本を「新しい時代のヒット・プロデューサー」であると考えていました。その時代、日本では、まだプロデューサーの存在感は作品の評価にとってさほど大きなものとはなっていませんでした。今でこそ小室哲哉氏のようにプロデューサーが中心となってヒットが生まれることが、当たり前のこととして受け止められるようになってきましたが、当時は洋楽ファンのコアの人々や音楽評論家など一部の人だけが、作品に関する情報やデータが少ない中でプロデューサーのクレジットに注目していた程度でした。一般的には作品の評価はあくまでもパフォーマーによっていたのです。私は当時、プラック・ミュージック界でヒットを連発していたプロデューサーに注目し、音楽雑誌やFM番組などを通してプロデューサー特集を組む企画を進めていました。クインシー・ジョーンズ、プリンス、テリー・ルイス、ナイル・ロジャース、そしてジョージ・デュークなどのプロデュース作品を広く紹介するためです。私はEPICレコードの一ディレクターでしたが、レコード会社やレーベルの枠を越えてメディアにさまざまな企画提案を行うことでブラック・ミュージック市場の拡大と新しい音楽エンタテインメントの普及を目指していました。私にとっての目先のライバルは他社ではなく、ロック・ミュージック界だったのかもしれません。
ジョージ・デュークの初のコンサート・ツアーは5回の公演とも素晴らしい出来で評判は上々でした。客の入りは大阪、札幌が事前告知の不足や認知度の低さが原因でやや低迷したため全体として85%程度とソールドアウトにはなりませんでしたが、東京公演は熱気に溢れ、NHKのライブ・レコーディングも入るなど、初のコンサートとしては立派な結果だったと思います。本人としては正直なところ満点ではなかったようですが、彼のプロ意識からみれば当然でしょう。彼としては臨時編成のメンバーであることと、そのいずれもが売れっ子のスタジオ・ミュージシャンでもあり、リハーサルの時間が少なかったのだ、と釈明していました。彼のレベルからみれば確かにその通りでしょうが、我々の目と耳には流石に一流のプレイヤー達であることが随所に感じられ十分に内容の豊かなコンサートであったと思います。特に私にとってはコンサートの発案から実現までの全体をプロデュースした最初の経験であり、しかもアメリカのトップクラスのアーティストをこれだけ揃えた豪華なメンバーでの単独ツアーという企画は日本ではそれまでほとんど例のないものでした。それだけに一応の成功を収められたことに本当に安堵し、またジョージの温かい協力にとても感動しました。そして、ツアーが終わり見送りのために成田空港に同行した時、ジョージは「感謝している。来年もまたやろう」と言って、あの大きな手で強く握手してくれました。帰宅の途上、この仕事をしていて本当に良かった、と改めて思いました。
彼の日本初(実は世界初)の単独コンサートツアーは、1984年の10月に東京、大阪、名古屋、札幌で計5回開かれました。メンバーはジョージ・デューク(リーダー/キーボード/ボーカル)、ポール・ジャクソンJr.(ギター)、ルイス・ジョンソン(ベース) 、スティーブ・フェローン(ドラムス)の4人の大物スター・プレイヤーに若手のギタリストとパーカッション、バックボーカルを加えた超豪華メンバーで、さしずめ「ジョージ・デューク・オールスターズ」ともいうべき編成のバンドでした。私は来日メンバーのリストが送られてきた時に思わず目を疑ってしまうほど驚いた記憶があります。さらに、来日スケジュールの最終的な詰めの段階で、それに輪をかけて驚くべき 連絡が入りました。2人のゲスト・ボーカリストを連れて行く、というのです。その2人とは、当時フィル・コリンズとの共演で全米 No.1のヒットを飛ばしていたアース・ウインド&ファイアーのフィリップ・ベイリーとジョージのプロデュースで新作を発表したばかりのデニース・ウィリアムスだったのです。
さかのぼること1年前、コンサートの計画を話すためにロスへ飛んだ時に、私はジョ ージにいろいろな提案と自分の「夢」を語りました。その中でジョージのボーカルについての私の考えを率直に述べたのです。私はボーカリストとしてのジョージの力量の限界とコンサートの成功のためには看板になるボーカリストが必要であることを説きました。こうした意見を面と向かって言うことはスターに対してはたいへん失礼なことですが、私たちは彼にとって初めてのリーダー・コンサートの実現のために何時間も真剣に腹を割って話しあったのです。彼は最終的に私の意見を聞き入れて、ゲスト・ボー カリストを選定し日本に連れて来るように動いてくれたのです。そのゲストがなんとフィリップ・ベイリーとデニース・ウィリアムスという願ってもないビック・ネームであり、さらにフィリップの単独来日もデニースの来日もいずれも初めてのことで、ファンにとってはまさに「夢の共演」が実現したのです。
私は彼のイメージ作りの基本を「新しい時代のヒット・プロデューサー」であると考えていました。その時代、日本では、まだプロデューサーの存在感は作品の評価にとってさほど大きなものとはなっていませんでした。今でこそ小室哲哉氏のようにプロデューサーが中心となってヒットが生まれることが、当たり前のこととして受け止められるようになってきましたが、当時は洋楽ファンのコアの人々や音楽評論家など一部の人だけが、作品に関する情報やデータが少ない中でプロデューサーのクレジットに注目していた程度でした。一般的には作品の評価はあくまでもパフォーマーによっていたのです。私は当時、プラック・ミュージック界でヒットを連発していたプロデューサーに注目し、音楽雑誌やFM番組などを通してプロデューサー特集を組む企画を進めていました。クインシー・ジョーンズ、プリンス、テリー・ルイス、ナイル・ロジャース、そしてジョージ・デュークなどのプロデュース作品を広く紹介するためです。私はEPICレコードの一ディレクターでしたが、レコード会社やレーベルの枠を越えてメディアにさまざまな企画提案を行うことでブラック・ミュージック市場の拡大と新しい音楽エンタテインメントの普及を目指していました。私にとっての目先のライバルは他社ではなく、ロック・ミュージック界だったのかもしれません。
ジョージ・デュークの初のコンサート・ツアーは5回の公演とも素晴らしい出来で評判は上々でした。客の入りは大阪、札幌が事前告知の不足や認知度の低さが原因でやや低迷したため全体として85%程度とソールドアウトにはなりませんでしたが、東京公演は熱気に溢れ、NHKのライブ・レコーディングも入るなど、初のコンサートとしては立派な結果だったと思います。本人としては正直なところ満点ではなかったようですが、彼のプロ意識からみれば当然でしょう。彼としては臨時編成のメンバーであることと、そのいずれもが売れっ子のスタジオ・ミュージシャンでもあり、リハーサルの時間が少なかったのだ、と釈明していました。彼のレベルからみれば確かにその通りでしょうが、我々の目と耳には流石に一流のプレイヤー達であることが随所に感じられ十分に内容の豊かなコンサートであったと思います。特に私にとってはコンサートの発案から実現までの全体をプロデュースした最初の経験であり、しかもアメリカのトップクラスのアーティストをこれだけ揃えた豪華なメンバーでの単独ツアーという企画は日本ではそれまでほとんど例のないものでした。それだけに一応の成功を収められたことに本当に安堵し、またジョージの温かい協力にとても感動しました。そして、ツアーが終わり見送りのために成田空港に同行した時、ジョージは「感謝している。来年もまたやろう」と言って、あの大きな手で強く握手してくれました。帰宅の途上、この仕事をしていて本当に良かった、と改めて思いました。
登録:
投稿 (Atom)